
ニュートン1995.April Vol.15 No5より
本居宣長と古事記
小林秀雄の「本居宣長」
小林秀雄著「本居宣長」を読んでみようと思った。「新潮」に連載11年余、精魂こめて書き継がれた思索といわれ、畢生の大業といわれる小林秀雄、晩年の大作である。直観的思考と言うことを考えてゆくにつれて、「国学」というものの存在が、どうしても気になるからである。直観的思考と、「国学」が、どこかで接点を持つような気がしてならない。また、われわれが直観的思考を失ってしまったのは、何時からなのか、このことも気になってきたからである。
そのようわけで、難解なため、何度か読みかけては止めてしまった、小林秀雄の「本居宣長」を読んでみることにした。ただ、読む、というのは、おこがましいかぎりで、小林秀雄の深意に迫れたどうか確信はない。しかし、それでも 、ずいぶん、色々なことが分った。よりいっそう 、自分の考え方に自身を持つことができた。
この本は、直観的思考とは、どのようなものか、ということを、鋭く、深く、豊に教示してくれたので、何とかその魅力をお伝えしたいと思う。しかし、思いはあるるものの、 私の拙い能力では、どこまで、それが出来るか自信がない。だが、直観的思考を語るには、最適、最良の本であると思うので、表層を撫でるばかりになることを、承知の上で、小林秀雄の「本居宣長」の魅力を、幾分トリッキーな方法でご紹介することにする。
小林秀雄は「本居宣長」を書いた動機を、次のように述べている。
|
・・・或る時、宣長という独自の生まれつきが、自分はかう思ふ、と先づ発言したために、周囲の人々がこれに説得されたり、これに反発したりする、非常に生き生きとした思想の劇の幕が開いたのである。この名優によつて演じられたのは、わが国の思想史の上でも極めて高度な事件であった。・・・ ・・・私が、彼の日記を読んで、彼の裡に深く隠れている或ものを想像するのも、又、これを、かりに、よく信じられた彼の自己と、呼べるように考えるのも、この彼の自己が、彼の思想的作品の独自な魅力をなしていることを、私があらかじめ直知しているからである。この言い難い魅力を、何とか解きほぐしてみたいという私の希いは、宣長に与えられた環境という原因から、宣長の思想という結果を明らめようとする、歴史家に用いられる有力な方法とは、まったく逆な向きに働く。 本居宣長 小林秀雄著 新潮社(以下、特に指示がなければ、「本居宣長」より引用。また、原文のまま、旧字体としたが、HPに載せるため、漢字については新字体に直している。) |
『直知』、さらに『原因から結果を導き出す方法とは逆向きな方法に働く』、といっている。小林秀雄自身も、また自らの直観に導かれて「本居宣長」を書いているのである。
その直観を働かせるのには、心の工夫が必要になるはずなのだが、そのために「心法、心術の如何」が必要になる。
|
・・・学問する責任は、各自が負わねばならない。真知は普遍的なものだが、これを得るには、各自の心法、或は心術の如何による。それも、めいめいの「現在の心」に関する工夫であって、その他に、「向上神奇玄妙」なる理を求めんとする工夫ではない。・・・ ・・・書を読まずして、何故三年も心法を練るか。書の真意を知らんが為でる。それほど古典の価値は信じられていた事を想わなければ、彼らの言ふ心法という言葉の意味はわからない。彼等は、古典を研究する新しい方法を思い付いたのではない。心法を練るとは、古典に対する信を新たにしようとする苦心であった。仁斎は「語孟」を、契沖は「万葉」を、徂徠は「六経」を、真淵は「万葉」を、宣長は「古事記」をという風に、学問界の豪傑たちは、みな己に従つて古典の信を新たにする道を行なった。彼等に、仕事の上での恣意を許さなかつたものは、彼等の信であつた。無私を得んとする努力であつた。この努力に、言わば、中身を洞にして了つた今日の学問上の客観主義を当てるのは、勝手な誤解である。 |
仁斎は「語孟」を、契沖は「万葉」を、徂徠は「六経」を、真淵は「万葉」を、宣長は「古事記」と書かれているが、この人々、思想界の豪傑達は「心法」を用いて、古典を明めようとした。そして、この系譜によって、わが国の思想史に革命が起こったと、小林秀雄は言うのである。
|
・・・戦国時代を一貫した風潮を、「下克上」と呼ぶ事は誰もしつている。・・・日本の歴史は、戦国の試練を受けて、文明の体質の根本的な改造を行なつた。・・・ ・・・「下克上」の劇は、天下人秀吉の成功によつて幕が下りて了たわけではない。「下克上」といふ文明の大経験は、先ず行動の上で演じられたのだが、これが反省され自覚され、精神界の劇となつて現れるには、又時間を要したのである。・・・己れに克つといふ心の大きな戦ひには、家康とは全く別種の豪傑が要る、歴史の摂理は、もうこれを用意していたとは、恐らく秀吉の思ひも及ばぬとろであった。 |
『わが国の思想史の上でも極めて高度な事件』なのだとも書かれているが、この思想劇のキーとなるものが「心法」、すなわち、心を用いて、物事を考えるという、新たな方法論である。この新たな方法論が、思想界の下克上によって台頭してきたといっているのである。まさに、私の言う、直観的思考法と呼べるもの台頭なのだ。わが国の江戸時代中期に起こった思想劇は実に、ゾクゾクするほど、スリリングなのである。
もののあはれ
この心法を練るには、「もののあはれ」が判らなければならないという。では、「あはれ」とは何か。
|
阿波礼(礼は旧漢字)といふ言葉は、さまざまいひかたはかはりたれ共、其意は、みな同じ事にて、見る物、きく事、なすわざにふれて、情(こころ)の深く感ずることをいふ也。俗には、ただ悲哀をのみ、あはれと心得たれ共、さにあらず。すべてうれし共、おかし共、かなしとも、こひし共、情に感ずる事は、みな阿波礼也。されば、おもしろき事、おかしき事などをも、あはれといへることおほし。 |
今日の私達は「あはれ」の意味は、「かわいそう」とか「ふびん」を思い浮かべてしまうが、そうではない。本居宣長は『悲哀、うれし、おかし、かなし、こひし、おもしろき事、おかしき事』など『情に感ずる事は、みな阿波礼』なのだという。人の心を強く打つような感動や、しみじみとした趣(おもむき)など、『情に感ずる事』は、すべて「あはれ」なのである。
さて、「あはれ」とは以上のような意味なのだが、さらに「あわれとは何か」と突っ込んで尋ねられると、
|
或る人が宣長に、この「あはれ」と言ふのは、如何なる義かと訊ねた。・・・「物ノアハレヲ知ルガ、即チ人ノ心ノアル也、物ノアハレヲ知ラヌガ、即チ人ノ心ノナキナレバ、人ノ情ノアルナシハ、只物ノアハレヲ知ルト知ラヌニテ待レバ、此ノアハレハ、ツネニタダアハレトバカリ心得イルママニテハ、センナクヤ侍ン」と言った。 |
|
宣長曰はく、「予、心ニハ解(サト)リタルヤウニ覚ユレド、フト答フベキ言ナシ、ヤヤ思ヒメグラセバ、イヨイヨアハレト云言ニハ、意味フカキヤウニ思ハレ、一言二言ニテ、タヤスク対ヘラルベクモナケレバ、重ネテ申スベシト答へヌ、サテ其人ノイニケルアトニテ、ヨクヨク思ヒメグラスニ従ヒテ、イヨイヨアハレノ言(コトバ)ハ、タヤスク思フベキ事ニアラズ、古キ書又ハ古歌ナドニツカヘルヤウニ、オロオロ思ヒ見ルニ、大方其ノ義多クシテ、一カタ二カタニツカフノミニアラズ、サテ、彼レ是レ古キ書ドモヲ考ヘ見テ、ナオフカク按ズレバ、大方歌道ハ、アハレノ一言ヨリ外ニ、余義(ヨギ)ナシ、神代ヨリ今ニ至リ、末世無窮(ブキウ)ニ及ブマデ、ヨミ出ル所の和歌ミナ、アハレノ一言ニ帰ス、サレバ此道ノ極意ヲタヅヌルニ、又アハレノ一言ヨリ外ナシ、伊勢源氏ソノ外アラユル物語マデモ、又ソノ本意ヲタヅヌレバ、アハレノ一言ニテ、コレヲ蔽フベシ・・・」 |
「あはれ」は「あはれ」である、としか答えようがない、といっているのである。たしかに、このようにしか答られないもののようだ。「あはれとは何か」とは「お前は誰だ」と言う問いかけと、おなじような性質なのだろう。「お前は誰だ」と問いかけられたら、「俺は俺だ」と答えるしかないだろう。もちろん、何月何日生まれ、どこそこに住んで、職業はなんで、趣味は云々・・と答ることは出来るだろう。しかし、「それがお前なのか」と再び問われれば、「いや、それだけではない。他には・・・」とさらに言い継いでみても、どこまでも言葉を連ねようとも、満足することはあるまい。それらは「俺」の一部ではあって全てではないのだから。だから遂に、「俺は俺だ」と開き直るしかなくなってしまう。「あはれ」も又同じことで、「あはれ」とは何か、ということは、こうした根源的な問いかけと同じことになるのである。だから、次のような言葉が生まれてくる。
|
「あはれ」といふ言葉の本質的な意味合は何かといふ問ひのうちに掴まれた直観を、彼は、既に書いたやうに、「よろずの事の心を、わが心にわきまえ知り、その品にしたがひて感ずる」事、といふ簡単な言葉で言ひ現したが、「あはれ」の概念の内包を、深く突き詰めようとすると、その外延がひろがって行くといふ事になったのである。 |
しかし、この根源的な問いかけに、三原則的な枠組で答えることが出来るかもしれない。
すでに、「二原則と三原則の系譜」で、三原則とは、リシは「主体=知る者」、チャンダスは「客体=知られる者」、デヴァタは「認識、知るプロセス」を核とするのだと書いたが、「あはれ」はチャンダス(客体=知られる者)より、生まれてくるのだと思う。そして、おそらく、日本的な「和魂(にぎみたま)」、「幸魂(さきみたま)」、「奇魂(くしみたま)」の三つの魂の分類にしたがえば、「和魂(にぎみたま)」に相当するのだと思う。リシ(主体=知る者)は「奇魂(くしみたま)」、デヴァタ(認識、知るプロセス)が「幸魂(さきみたま)」となる。
いきなり、概念を飛躍させてしまったので、ビックリされたと思うが、TMのシディ瞑想を行っているものが、これを見れば「なるほど」と思うはずである。なぜなら、われわれは、これを毎日の瞑想の中で体験しているからである。といっても、シディ瞑想を行ったことのない人は、私が何をいっているのかさっぱりわからないと思う。しかし、私の言っていることは、たぶん間違っていないはずである。残念ながら、これ以上は話すことが出来ない。理由は二つある。
一つは、われわれはシディ瞑想を習う時に、この内容を口外しないと、誓約書まで書かされているからである。二つ目は、私も口外しない方が良いと思うからである。なぜなら、言葉でいくら説明しても絶対に伝わらないし、むしろ、疑念を抱かれる方が多いと思われるからである。このことを例えてみると、「リンゴ」を食べたことがない人に、リンゴは、さくさくして、甘くて、少し酸っぱくて、・・と説明するようなものだからだ。言葉をいくら連ねても、決してリンゴの味を説明は出来ない。リンゴを知るには、食べるより外に手はないのである。さらに、食する人にとっては、リンゴの味の説明は、認識の邪魔になるはずである。何の先入観もなしに、リンゴを食べればよい。その方が感動は深くなるからだ。シディ瞑想についても同じことが言えて、体験するしかない、のである。
だが、「あはれ」はチャンダス(客体=知られる者)より、生まれる、ということついては、もう少し言葉を連ねることが出来そうだ。本居宣長によれば、「あはれ」は「ああ、はれ」が縮められた言葉だそうである。この「はれ」は、「われ=我」のことなのだから、リシという主体がチャンダスという客体を認めたときに、思わずあらわれた感動の「ああ、はれ」が、「あはれ」なのではないか。「あはれ」というのは、もっとも究極的、根源的な心の感動なである。
ブリファット・アーランキャ・ウパニシャッド(世界創成に関する思弁)の中に、根元的な存在が、始めて自己を認識した時に発せられた音(ことば)は、「AHAM アハ(ム)」であったと書かれている。「M」は鼻濁音で、はっきりした音を持たないから、「アハ..」という発音になる。「私は」という意味で、これが英語の「I」となる。日本語の「われ=我」と根元的には同じ事を現しているのだ。
このようにみると、「あはれ」を知るとは、自分を知るということではないのか。別な言い方をすれば、こころの感受性を高める、ということになると思うのである。そして、
|
「ああ、はれ-----あはれ」といふ生の感動の声は、この声を「なげく」「ながむる」事によって、歌になる。 ・・・歌を、何もむつかしく定義しなくてもよい、あはれにたへ難い時に「其思ふすぢを、おぼえずいひづる」のが歌だ。 ・・・さうすると、「物のあはれ」は、この世に生きる経験の、本来の「ありやう」のうちに現れると言ふ事になりはしないか。宣長は、このあるがままの世界を深く信じた。この「実(マコト)の、「自然の」「おのづからなる」などといろいろに呼ばれている「事」の世界は、又「言(コト)」の世界でもあったのである。 |
やまと心とやまと魂
|
|
本居宣長の歌である。しかし、この歌の鑑賞にあたって、ある一群の人々は嫌悪を抱くかもしれない。また、ある一群の人々は、意識を昂揚されるかもしれない。嫌悪を抱く人々は、今次の大戦で、やまと魂という言葉のプロパガンダに踊らされて貴い命を散らしていった人々に思いを馳せて、意識を昂揚させる人々は、武勇の心を刺激されて。
しかし、ちょっと待って欲しい。嫌悪を抱く人は、もし、あなたが、第二次大戦の前に生まれていたら、おなじように、この歌に接して、嫌悪感を抱くであろうか。あるいは都会ではなく、農村に生まれ、素朴な人々に囲まれて育ったならば、どうであろうか。
また、意識を昂揚をされる人々は、あなたが、この歌が歌われた、江戸の時代に生まれたら、どうであろうか。まだ、平田篤胤が歴史の上に登場して、やまと魂に武烈の意識を添加しない前、したがって明治維新の英雄の業績も知らず、ましてや今回の大戦の神風特攻隊のことも知らなかったら。同じように武勇を刺激されるだろうか。
このことは、私たちが、詩などの芸術作品に接するときのみならず、すべての物事に接する時の、困難さを物語る。私たちの観念や経験が、じゃまをして、素直な気持ちで作品や物事と対峙することができないのである。
やまと心、やまと魂という言葉が生まれてくる背景は
|
真淵は、「やまと魂」といふ言葉を、万葉歌人によつて詠まれた、「丈夫(ますらお)の、ををしくつよき、高き、直(なお)き、こころ」といふ意味に解した。「万葉」のますらをの手ぶり」が、「古今」の「手弱女(たおやめ)のすがた」に変ずる「下れる世」となると、人々は「やまと魂」を忘れたと考えた。 しかし、「やまと魂」とか「やまと心」とかいふ言葉が上代に使はれていた形跡はないのであつて、真淵の言ふ「手弱女のすがた」となつた文学にうちに、どちらも初めて現れて来る言葉なのである。「やまと魂」は「源氏」に出て来るのが初見、「やまと心」は、赤染衛門の歌にあるのが初見といふ事になつていて、当時の日常語だつたと見ていいのだが、王朝文学の崩壊とともに、文学史から姿を消す。・・・では当時、どういふ意味の言葉であつたか。・・・ 「源氏」の中の「大和魂」の用例は一つしかないが、それは「乙女の巻」の源氏の言葉に見られる。「猶、才(ざえ)を本としてこそ、大和魂の世に用ひらるる方も、強う侍らめ」−−才(ざえ)は、広く様々な技芸を言ふが、ここでは、夕霧を元服させ、大学に入学させる時の話で、才は文才(もんざい)の意、学問の意味だ。学問といふものを軽んずる向きも多いが、やはり、学問といふ土台があつてこそ、大和魂を世間で強く働かす事が出来ると、源氏君は言ふので、大和魂は、才に対する言葉で、意味合いが才とは異なるものとして使はれている。才が、学んで得た知識に関係するのに対し、大和心の方は、これを働かす知恵に関係すると言つてよさそうである。 もう一つ。「今昔物語」に、・・・これで見ると、「大和魂」といふ言葉の姿は、よほどはつきりして来る、やはり学問を意味する才に対して使われていて、机上の学問に比べられた生活の知恵、死んだ理屈に対する、生きた常識といふ意味合いである。 ・・・大和心、大和魂が、普通、いつも「才」に対して使われているのは、元はと言へば、漢才(からざえ)、漢学に対抗する意識から発生した言葉であることを語っている・・・ ・・・彼は、「源氏」を真淵とは比較にならぬほど、熱心に、慎重に読んだ。真淵と違つて、この言葉の姿は、忠実に受取られていたと見てよく、この拾ひ上げられた言葉は「あはれ」といふ言葉の場合と同様に、これがはち切れんばかりの意味をこめて使はれていても、原意から逸脱して了ふといふ事はなかつたとみて見て差支えない。 ・・・宣長は還暦を迎へ(寛政二年)自画自賛の肖像を作つた。その賛が、名高い「しき島の やまとごごろを 人とはば 朝日ににほふ やまざくら花」の歌であつた。・・・儒家に宰領(著注:取り締まれた)された学界には、耳障りな新語と聞こえたであろうし、国粋主義を唱える為に思ひ附いた標語とも映じたのである。上田秋成のような鋭敏な神経には、もうそれだけで、我慢がならなかった。−−『やまとだましひと云ふことを、とかくにいふよ。どこの国でも、其国のたましひが、国の臭気也。おのが像の上に、書きしとぞ。敷島の やまと心を 道とへば 朝日にてらす やまざくら花、とはいかにいかに。おのが像の上には、尊大のおや玉也。そこで、しき島の やまと心の なんのかの うろんな事を 又さくら花、と答へた』、−−自画像の上に書かれた「やまと心」という言葉が、像を歪める。学者の顔を宣伝家の顔に変へる。宣長には思ひも及ばぬ事だつたと思われる。 標語を思ひ附くとか、掲げるときふやうな事は、宣長の学問の方法からしても、気質からしても、先ず考へられない事だ。彼は和学とか国学とかいふ言葉を嫌つた。そう言うふのが世間のならはしだが、『いたくわろきいひざま也、みづからの国のことなれば、皇国(みくに)の学こそ、ただ学問といひて、漢学こそ、分けて漢学といふべきことなれ、・・・昔より世の中おしなべて、漢学をむねとするならひによりて、万の事をいふに、ただかのもろこしを、みずからの国のごとく、内にして、皇国をば、返りて外(よそ)にするは、ことのこころたがひて、いみじきひがごと也』・・・ |
品が下がることをあえて承知だが、ラーメンを「そば」と呼び、「そば」をあえて「日本そば」と呼んでいて、おかしいと感じないくらいだから、現代人も狂ってしまっているといえるだろう。脱線はそのくらいにして、
|
わが国の古典を明きらめる、わが国の学者の心構へを、特に「やまと魂」と呼ぶには当たらぬ事だ。それは、内の事を「外にしたるいひやう」で、「わろきいひざま」であるが、残念乍ら、その心構へが、かたまつていないのだから、仕方なく、そういふ言ひ方をする。なぜ固まらないかと言ふと、漢意儒意に妨げられて、かたまらない。−−「からぶみをまじへよむべし、漢籍を見るも、学問のために益おほし、やまと魂だによく堅固(かた)まりて、動くことなければ、昼夜からぶみをのみよむといへども、かれに惑はさるるうれいはなきなり、然れども世の人は、とかく倭魂かたまりにくき物にて、から書を読めば、そのことよきにまどはされて、たぢろぎやすきならひ也、ことよきとは、その文辞を、麗(うるは)しとふにはあらず、詞の巧にして、人の思ひつきやすく、まどはされやすきさまなるをいふ也。すべてから書は、言巧にして、ものの理非を、かしこくいひまはしたれば、人のよく思ひつく也。すべて学問すじならぬ、よのつねの世俗の事にても、弁舌よく、かしこく物をいひまはす人の言には、人なびきやすき物なるが、漢籍もさやふなるものと心得居べし」−−「やまと心」とは何かと問はれても、説明が適わぬから歌を一首、歌の姿を素直に受取って貰えば、別に仔細はない、と宣長は言ふのである。 |
以上でわかるように、「やまと心」は「漢(から)心」に対する対語なのである。誰でも、一度ならず、寸法の合わない服を着た時の、なんとなく着心地が悪くて、心が落ち着かない、不愉快な感じを経験したことがあるだろう。日本人は漢字が渡来してからは、漢字ですべてを表記していたが、しかし、どこかに心地の悪さを感じていた。そこで、漢字を音訓を併用して書き表す古事記の表記法を生み出し、王朝文学があらわれるころには、平仮名は発明し、何とかその心地の悪さを補おうとしてきた。はじめは、その心地の悪さが、どこから来るのか、意識されていなかったが、江戸時代の鎖国政策によって、外よりも、自分たちの内側に意識が向けられた時に、すなわち賀茂真淵や本居宣長が現れる頃になると、それは、はっきりと姿を現して意識されるようになってきた。それが、「から心」に対しての「やまと心」なのである。
私の言う、中国的な二原則原理での思考法に限界を感じ始めてきたと言ってもいいと思う。そのような中で、わが国に本来の思考法である、三原則原理の直観的な思考法の必要性が意識されはじめてきた、このように考えても問題はないはずである。
そこで、「やまざくら花」の歌をもう一度、見直していただきたい。やわらかく、さわやかで、可憐で、すがすがしい、姿こそ、われわれ日本人の心であることが、しみじみと感じられてはこないだろうか。私にはそう思える。これが直観的思考の本来の姿なのだ。
古事記
その心が古典を照明した。賀茂真淵はその心で万葉集を研究し、その神髄を極めた。しかし、万葉の奥に、さらに高い境地のあることを発見する。それを、小林秀雄は「真淵晩年の苦衷」と書いた。その「苦衷」は真淵の『老衰と「万葉考」との重荷』のことではない。「万葉」のその奥に、「万葉」を生み出すもとになる、偉大な精神を直知して、
|
「彼は、これを「高く直きこころ」「ををしき真ごころ」「天つちのままなる心」「ひたぶるなる心」といふ風に様々に呼んでみるのだが、彼の反省的意識は安んずる事は出来なかった。「上古之人の風雅」、いよいよ「弘大なる意」を蔵するものと見えて来る。「万葉」の風をよくよく見れば、藤原の宮の人麿の妙歌も、飛鳥岡本の宮の正雅に及ばぬと見えて来る。源流を尋ねようとすれば、「それはた、空かぞふおほよそはしらべて、いひつたへにし古言(ふること)も、風の音のごととほく、とりをさめましけむこころも、日なぐもりおぼつかなくなんある」といふ想いに苦しむ。あれを思ひ、これを思って言葉を求めたが、得られなかった。 ・・・「人代を盡(つき)て、神代をうかがはんとするに老い極り遺憾なり」といふ真淵の嘆き・・・真淵の前に立ちはだかっているものは、実は死ではなく、「古事記」といふ壁である・・・。 |
この『「古事記」という越え難い絶壁』に、弟子である本居宣長が挑む。
このあたりから、『本居宣長』の小林秀雄の解説も佳境に入ってくるのだが、その魅力を一つ一つ伝えていては長文になる。それならば、私のつたない文のを読むよりは、この本を一冊まるごと読んでしまった方がよっぽど良い。いずれも、直感的思考を考える上には欠かせないものばかりだからだ。しかし、そうは言っても、そこまでする人は少ないだろう。そこで、古事記論のもっとも根本的な問題を取り上げてみることにする。
|
「古事記は、文学としては、興味あるものだが、歴史としては、信用するわけには参らない、今日では、さう考へるのが常識となつている。だが、「古事記」の神代之巻の荒唐無稽な内容は、近世に這入ると、もう歴史家達を当惑させていたのである。「大日本史」が神武始まつているのは、周知の事だが、幕府の命で「本朝通鑑」を修した林家にしても、やはり、先づ神代之巻は敬遠して、その正編を神武から始めざるを得なかつた。 |
神代之巻の荒唐無稽な内容というのは、
|
・・・二柱の男女神が、高天原から天浮橋に降り立ち、天の沼矛で、潮を畫く、其の矛の先から垂り落ちる潮が淤能碁呂島(オノゴロシマ)となつた。ついで、二神は、天之御柱をめぐる恋愛に失敗して、水蛭子(ヒルゴ)を生み、淡島を生むといふ物語・・・ |
で、これを、歴史とはいえないし、ましてや荒唐無稽すぎて、現実のものとも思えない、と考えるが普通である。それは、江戸時代の学者も、当惑していたと小林秀雄はいうのである。
|
これはなかなか厄介な問題だ。これまでも津田左右吉の意見を幾度か持ち出したが、これについても、同氏の意見が書かれているので、引用してみようと思う。問題が上手に解かれているからではない。むしろ、それは不手際で、見ようによつては、論者の当惑が現れているとも受取れ、それが、問題のまことに面倒な性質を、問わず語りに語っていると思われるからだ。−− 『徳川時代の学者などは、一種の浅薄なる支那合理主義から、事実で無いもの、不合理なものは、虚偽であり妄誕であって、何等の価値の無いものと考え、そうしてまた一種の尚古主義から、崇厳なる記紀の記載の如きは、勿論、虚偽や妄誕であるべき筈が無いから、それは事実を記したもので無くてはならぬと推断し、従って其の不合理な物語の裏面に潜む合理的な事実があり、虚偽妄誕に似た説話に包まれている真の事実がなければならぬ、と憶測したのである。そうしてそれがために、新井白石の如く、不合理な物語を強ひて合理的に解釈しようとして、事実と認め難いものに於いて無理に事実を看取しようとして、甚だしき索強附会の説をなすに至ったのである。之に反して本居宣長の如きは、古事記の記載を一々文字通りに事実と見なしたのであるが、それとても歴史的事実をそこに認めようする点に於いて、やはり事実でなければ価値がないといふ思想を有っていたことが窺われ、また人間のこととしては不合理であるが神のこととしては事実であるといふ点に於いて、人間については白石と同じような合理主義を抱いていたことが知られる。宣長の思想の根底に存在する一種の自然主義からも、そう考えねばならなかったろう。さて今日記紀を読む人には、宣長の態度を継承するものはあるまいが、其の所説に於いて必ずしも白石と同じで無いにせよ、なほ彼の先蹤に(意識して或はせずして)追従するものが少なくないからである』(古事記及び日本書紀の新研究)』 このように。白石と宣長とが、「記紀」の上代の記述につき、極端な説を成して謝つたのも、元を尋ねて行けば、やはり、儒学の考え方に捕らえられていたが為だ、と津田氏は見る。尚古主義と結んだ観念的な合理主義が、客観的な歴史研究への道を阻んだと見るのであるが、このように、歴史研究の方法の未熟という面から、問題を割切ろうとしても、二人がめいめい持って生まれた、身を投げかけるようにして、取組まねばならなかった歴史問題の実質には、触れないで過ぎて了ふやうに思われる。所謂実証主義的歴史観に立つ今日の歴史家は、奇怪な「記紀」の物語などに躓きはしないだろう。それは、津田氏の言い方で言えば、「実際上の事実」ではないが、「未開人の心理上の事実」であり、そう受け取れば、別に仔細はないようだ。しかし、歴史事実を、そのように二種類に分類出てみたところで、事は易しくはならない。却って、むつかしくなるだろう。津田氏も、同じ著作の結論で言っている「記紀の上代の物語は歴史では無くして寧ろ詩である。そうして詩は歴史よりも却ってよく国民の内生活を語るものである」と。では、歴史と詩とは、何処でどう違うのか、何処でどう関係するのか。この殆ど見越しの利かぬ難題のうちに、歴史家は投げ帰されるのである。」 |
この難題に挑戦してみようと思う。古事記の神代の巻が真実であるならば、現代の科学がとらえた真実とも一致するはずである。では、それを一致させてみよう。古事記では、このくだりが次のように書かれている。
|
ここに天つ神も諸(もろもろ)の命以(みことも)ちて、伊耶那岐(いざなぎ)の命伊耶那美(いざなみ)の命(みこと)の二柱の神に詔(の)りたまひて、この漂へる国を修理(をさ)め固め成せと、天の沼矛(ぬぼこ)を賜ひて、言依(よ)さしたまひき。かれ二柱の神、天(あめ)の浮橋(うきはし)に立たして、その沼矛(ぬぼこ)を指(さ)し下(おろ)てし畫きたまひ。塩をこをろこをろに畫き鳴(な)して、引き上げたまひし時に、矛の末(さき)より滴る塩の積りて成れる島は、淤能碁呂(おのごろ)島なり。 その島に天降(も)りまして、天の御柱を見立て八尋殿(やひろどの)を見立てたまひき。ここにその妹伊耶那美(いざなみ)の命に問ひたまひしく、「汝が身はいかに成れる、と問ひたまへば、答へたまはく、「吾が身は成り成りて、成り合はぬところ一処あり」とまをしたまひき。ここに伊耶那岐の命詔(の)りたまひしく、「我が身は成り成りて、成り剰れるところ一処あり。故(かれ)この吾が成り剰れる処を、汝が身の成り合はぬ処に刺し塞ぎて、国土生み成さむと思ほすはいがに」とのりたまへば、伊耶那美(いざなみ)の命答へたまはく、「しか善けむ」とまをしたまひき。ここに伊耶那岐の命詔(の)りたまひしく、「然らば吾(あ)と汝(な)と、この天の御柱を行き廻(めぐ)りあひて、美斗(みと)の麻具波比(まぐはひ)せむ」とのりたまひき。 かく契(ちぎ)りて、すなはち詔りたまひしく、「汝は右より廻り逢へ、我は左より廻り逢はむ」とのりたまひて、約(ちぎ)り竟(を)へて廻りたまふ時に、伊耶那美の命まづ「あなにやし、えをとこを」とのりたまひ、後に伊耶那岐の命「あなにやし、え娘子(おとめ)を」とのりたまひき。おのもおのものりたまひ竟(を)へて後に、その妹に告(の)りたまひしく、「女人(おみな)先立(さきだ)ち言へるはふさはず」とのりたまひき。然れども隠処(くみど)に興(おこ)して子水蛭子(みこひるこ)を生みたまひき。この子は葦船(あしぶね)に入れて流し去(や)りつ。次に淡島を生みたまひき。こも子の数に入らず。 ここに二柱の神議(はか)りたまひて、「今、吾が生める子ふさはず。なほうべ天つ神の御所(みもと)に白(まを)さな」とのりたまひて、すなはち共に参い上りて、天つ神の命(みこと)請ひたまひき。ここに天つ神の命(みこと)以ちて、太ト(ふとまに)にト(うら)ヘてのりたまひしく、「女(おみな)の先立ち言ひしに因りてふさはず、また還り降(あも)りて改め言へ」とのりたまひき。 かれここに降りまして、更にその天の御柱を往き廻りたまふこと、先の如くなりき。ここに伊耶那岐の命、まづ「.あなにやし、えをとめを」とのりたまひ、後に妹伊耶那美(いざなみ)の命、「あなにやし、えをとこを」とのりたまひき、かくのりたまひ竟(を)へて、御合(みあ)ひまして、子淡道(みこあはじ)の穂の狭別(さわけ)の島を生みたまひき。次に伊予の二名の島を生みたまひき。この島は身一つにして面(おも)四つあり。面ごとに名あり。かれ伊予の国を愛比賣(えひめ)といひ、讃岐(さぬき)の国を飯依比古(いひよりひこ)といひ、粟の国を、大宜都比賣(おおげつひめ)といひ、土左の国を建依別(たけよりわけ)といふ。次に隠岐(おき)の三子(みつご)の島を生みたまひき。またの名は天(あめ)の忍許呂別(おしころわけ)。次に筑紫(つくし)の島を生みたまひき。この島も身一つにして面四つあり。面ごとに名あり。筑紫の国を白日別(しらびわけ)といひ、豊(とよ)の国(くに)を豊日別(とよひわけ)といひ、肥の国を建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)といひ、熊曾(くまそ)の国を建日別(たけびわけ)といふ。次に伊岐の島を生みたまひき。またの名は天比登都柱(あめひとつはしら)といふ。次に津鳥(つしま)を生みたまひき、またの名は天(あめ)の狭手依比賣(さてよりひめ)といふ。次に佐渡(さど)の島を生みたまひき。次に大倭豊秋津島(おおやまととよあきつしま)を生みたまひき。またの名は天(あま)つ御虚空豊秋津根別(みそらとよあきつねわけ)といふ。かれこの八島のまづ生まれしに因りて、大八島国といふ。 然ありて後還ります時に、吉備(きび)の児島(こじま)を生みたまひき、またの名は建日方別(たけひがたわけ)といふ。次に小鳥豆(あづきしま)を生みたまひき。またの名は大野手比賣(おほのでひめ)といふ。次に大島(おほしま)を生みたまひき。またの名は大多麻流別(おほたまるわけ)といふ。次に女島(ひめじま)を生みたまひき。またの名は天一根(あめひとつね)といふ。次に知詞(ちか)の島を生みたまひき。またの名は天の忍男(おしを)といふ。次に両児(ふたご)の島を生みたまひき。またの名は天(あめ)の両屋(ふたや)といふ。吉備の児島より天の両屋の島まで并はせて六島。 ・・・こは妹伊耶那美の神、いまだ神避りまさざりし前に生みたまひき。ただ淤能碁呂島は生みたまへるにあらず、また蛭子と淡島とは子の例に入らず。ハ (角川文庫 古事記 武田祐吉 訳注)
|
では、これが現代の科学とどのように一致するのか。まず、伊耶那岐(イザナギ)の命伊耶那美(イザナミ)の神というのは、「いざなう=さそう」+「なみ=波」と「なぎ=凪(波を穏やかにさせる)」の働きで、この場合の神という言葉の意味は「働いた力」ということなになる。
雑誌、ニュートン1999.1月号「特集・宇宙はなぜ無から誕生したのか」では、
|
量子論によると、時間や空間さえない状態である「無」も、そのままではありえず、ゆらいでいる。その無のゆらぎから、宇宙は誕生したと考えられている。生まれたばかりの宇宙は真空だった。しかし、真空は「何もない空間」ではなく、さまざまな波長の微少な振動の波に満ちていた。 |
と書かれている。おそらく、伊耶那岐(イザナギ)、伊耶那美(イザナミ)神とは、こうした働きをあらわした名前であろう。
その波の働きによって宇宙が生まれたが、その波が回転運動を起こさなければ、銀河系も太陽系も生まれてはこない。「物質が回転運動をしてエネルギーとなり、エネルギーが回転運動をして物質となる。宇宙の時空間はその繰り返しである。」と言われているが、塩をコロコロかき回し、引き上げた時に、矛(ほこ)の末(さき)より滴る塩がつもって、淤能碁呂(おのごろ)島が出来た、ということは、銀河系や太陽系も星間物資の回転より誕生するのだから、自ら回転する島(淤能碁呂(おのごろ)島)は、銀河系や太陽系と言っても良いではないか。

ニュートン1995.April Vol.15 No5より
さて、その回転運動なのだが、太陽系惑星の公転は、ほとんどの場合、北極方向から見ると「反時計回り」なのだそうである。惑星の自転もほとんどが反時計回りで(*金星は除く、生成後時計回りになったようである)、月などの衛星の自転も「反時計回り」のようだ。確率的には、時計回りのシステムも反時計回りシステムも半分ずつあってもおかしくないのだそうだが、われわれの宇宙では「反時計回り」が圧倒的に多いということである。そうなる理屈は、風呂の栓を抜くときに、風呂の水に最初に与えた回転が、左回りならば、水の流れ出る渦も左回りになるのと同じ原理だということである。おそらく、銀河系を生んだ最初の回転が左回り(反時計回り)だから、そのに属する恒星系以下のシステムも、左回りに規制されてしまうのだろう。
古事記では、男女二神は天の御柱を回って、最初に右周りしてみたら、水蛭子(ひるこ)と淡島が生まれてしまったと言っている。ヒルのような子供、というのは、背骨をもたない子供という意味だろう。それは、星間物質を右回りして集めてみたが、星の核が出来ず、バラバラになったという意味のことではないか。その星は二つできたが、最初の子供は葦船(あしぶね)で流してしまったといっている。これは、彗星のことではかなろうか。ニュートン1995.April Vol.15 No5「完全保存版、太陽系のすべて」で、彗星の生成は次のように説明されている。(以下枠内の文はこれによる)
|
彗星の太陽起源説 氷を多く含むことから、彗星は太陽の熱で温まりすぎないように、外惑星の存在するところ、あるいはそれより遠くで粒子が集まってできたたと考えられる。しかし、逆に遠すぎると粒子が少なくなり、彗星はつくられにくい。せいぜい太陽から100天文単位はなれたところにできたのであろう。つくられて彗星は惑星の重力の影響で軌道をかえ、数万天文単位はなれた領域まで飛ばされる。 |
葦船で流した、とは太陽系の外へ飛ばしてしまったということなのではないか。次にできた核のない子供は淡島であるが、これは流したとは書かれていない。ということは太陽系にとどまったということであろう。そうすると、火星と木星の軌道の中間には、無数ともいえる小惑星が存在している。これは小惑星帯(アステロイド・ベルト)と呼ばれている。これが「あわき」「しま=星」で、淡島ではないのか。
「島」を「星」としたが、われわれも宇宙船を船と呼ぶ、英語でも「Space Ship」といい、やはり「Ship」で船である。その船がたどり着く先を「しま」と呼ぶのは適切ではないか。昨今のコンピュータグラフィックスは精巧で、あたかも自分も一緒になって飛んでいるように見えるが、何もない空間に、始めは点として存在し、近づくにつれて次第に大きくなり、画面いっぱいに広がった星を見ていると、海上と行く船が島を認め、近づく光景と、うり二つではないか。宇宙という広大な空間に浮かぶ星は、海洋に浮かぶ島と実によく似てはいないか。今日のような科学知識を持たない彼らは、見たままを素直に言葉にした。そして、もっとも身近な言葉を選んだ。それが「しま」である。だから星を島といっても、なんの差し障りもないばかりでなく実に適切な表現だと思う。
それに星は星間物質が集合して、つまり「閉まって」できる。閉まる→「しま」る→島。実にシンプルな言葉だけれど本質もついているではないか。
|
小惑星帯 小惑星帯は惑星がこわれてできたのか? 最大の小惑星でも1000キロ程度の大きさしかなく、多くはいびつな形をしている。太陽系が形成されたころ、微惑星が衝突、合体して惑星ができたといわれている。小惑星帯は当時の微惑星がそのまま残っているものなのだろうか。あるいは惑星が形成する途中で、はげしい衝突のために惑星が破壊された結果できたものなのだろうか。結論はまだでていない。 小惑星帯には、一つの惑星がこわれて形成されたと考えられる小惑星のグループ(族)が数多く存在することがわかっている。惑星がこわれてできた小惑星が多いことはたしかであろう。しかし、なぜ小惑星帯でだけ惑星が破壊したのかという理由はまだわからない。 |
けっこう、現代の科学が突き止めた真実と符合してきた。そうすると、男の神様イザナギノミコトから声をかけて、左回りに回転運動をおこなったら、大八島ができたということは、太陽系の惑星ができたと考えても良さそうではないか。しかし、ここで困ったことが起こる。なぜなら、太陽系の惑星は9個で、8個(八島)ではない。やっぱりダメか、と思ったのだが、太陽系の最外周を回る冥王星の記述を見ると、
|
冥王星は、海王星最大の衛星であるトリトンに、大きさや密度、薄い大気をもつ点がよく似ている。したがって、冥王星とトリトンの起源については、同じような過程を経て形成された天体が、一方は海王星にとらえられて海王星をまわる衛星となり、もう一方は太陽を公転する衛星となったともいわれる。カロン(冥王星の衛星)の起源もなぞである。』 トリトンは、ユニークな特徴をもつ天体である。トリトンは海王星から35万キロの円軌道を、海王星の自転方向とは逆回りに公転する逆行衛生である。そのためトリトンは、どこかほかの場所で誕生したあとから海王星の重力にとらえられたという説がある。レネイドもトリトンと同様に捕獲天体の可能性がある。 |
冥王星は、水星〜海王星の8個の惑星とは違う起源をもつようなのである。そうすると、太陽系ができた当初は、惑星はやはり8個ということになり、大八島の八と一致してくる。こんなことから、大八島は水星〜海王星の8個の惑星と言って良いではなかろうか。
六島は衛星のことか
大八島を生んだ後で、「吉備の児島より天の両屋の島まで并はせて六島」を生んだとある。先の大八島が惑星ならば、これは、おそらく、月などの衛星のことではないのかと推測してみた。すると、水星〜海王星までの8個の惑星で、衛星を持つものは6個である。表にすると、以下の通りで、それに、古事記の六つ島名前とその別名を合わせてみた。
|
惑星名 |
衛星数 |
古事記の島名前とその別名 |
|
水星(地球の38%) |
0 |
|
|
金星(地球の95%) |
0 |
|
|
地球 |
1 |
女島(ひめじま)、天一根(あめひとつね) |
|
火星(地球の約半分) |
2 |
両児(ふたご)の島、天の両屋(ふたや) |
|
木星(地球の11倍) |
16 |
大島(おほしま)、大多麻流別(おほたまるわけ) |
|
土星(地球の9.4倍) |
18 |
小豆島(あづきしま)、大野手比賣(おほのでひめ) |
|
天王星(地球の4倍) |
15 |
吉備(きび)の児島(こじま)、建日方別(たけひがたわけ) |
|
海王星(地球の3.9倍) |
8 |
知詞(ちか)の島、天の忍男(おしを) |
驚くべきは、古事記の名前と、各惑星が持つ、衛星の特徴の一致である。例えば、天一根(あめひとつね)を取り上げると、「1つ」の衛星というのは、地球はしかない。地球は言わずと知れたように、月という一つの衛星をもつ。その月は、太陽を男性原理として象徴すると、月は女性原理として象徴されるから、「女島(ひめじま)」と言う言葉によく似合う。
火星の衛星の特徴は
|
火星にはフォボスとダイモスという二つのいびつな形をした小さな衛星がある。内側の衛星フォボスは、27×21×19キロのラグビーボールのような形で、火星から6000キロはなれた軌道を8時間で公転する。外側の衛星ダイモスは、15×12×11キロのだ円体で、火星から2万キロはなれた軌道を30時間で公転する。 |
天の両屋(ふたや)は「2つ」と解し、「両児(ふたご)の島」というのも、上記の記述から納得できるものがある。
木星の衛星の特徴は
|
木星は衛星を16個したがえている。そのうち内側に近いところには、とくに大きな四つの衛星がある。これらは1610年にガリレオにより発見されたために、ガリレオ衛星と呼ばれる。四つの衛星は木星に近い方から、イオ、エウロパ、ガミメデ、カリストと名づけられている。 |
とあるから、「大島」と呼ばれてもおかしくはないだろう。さらに、木星のリングについては、
|
木星のリングの発見は、ボイジャー探査機の重要な成果の一つである。リングは木星の半径の約1.8倍のところにあり、たいへんに薄い。そこから木星の表面まで、さらに薄いリングが広がっている。 |
とあるから、「おおたまるわけ」とは、「おおきな」な「た(もう一つの)」の「まる」が「わかれる」とも読めて、ボイジャーの観測と一致しないだろうか。そうすると、地球からの望遠鏡の観測ではわからなかったリングを、探査衛星など絶対に持つことができない、遙か昔から知っていたと言うことになる。
次に、土星の衛星の特徴は、
|
美しいリングを持つ土星は、地球から肉眼でみることのできる最も外側の惑星である。土星を望遠鏡で観測したガリレオは、土星の両側に奇矯なこぶがあることを発見した。此がリングだったのである。 土星の最大の特徴は、雄大なリングである。太陽系で最多の衛星をもつ平たい惑星で、衛星の数は18個もあり、太陽系で最も多い。土星の衛星はタイタンを除くといずれも半径数百キロ以下で、ほとんど氷からできている。 |
とある。数は多いが、多くは「半径数百キロ以下」と言われているから、「小豆島(あづきしま)」、つまり小豆のようなという表現は適切であろう。
また、「大野手比賣(おほのでひめ)」というのは、観測衛星など飛ばさなくても、簡単な望遠鏡で地球から土星を見ると、丸い星が手を突きだしているように見えるのだが、こんなことから「大きな手」が「ひいでて」「めだつ、めでる」と解することもできそうである。土星の輪の特徴をよく表現しているではないか。
次に、天王星の衛星の特徴だが、
|
天王星の衛星は全部で15個存在する。このうち五つは比較的大きく、地球からでも観測できる。残りの衛星は、ボイジャ探査機の接近によってはじめてみつかった、半径20〜80キロ程度の小さな衛星である。 |
といわれ、「半径20〜80キロ程度」なら、「小豆」よりも小さい、「吉備(キビ)」という表現はピッタリである。さらに「児島(こじま)」と言うのだから、まさに「小さな衛星」ではないか。
「建日方別(たけひがたわけ」)というのは、
|
これらの衛星の中でとくに話題を集めたのは、五大衛星のうち最も内側をまわるミランダである。半径わずか250キロ程度のこの小さな衛星の表面に、まるで何かでひっかいたような巨大な地形や、深さ20キロに達する溝がみつかった。このような地形は、過去にミランダが破壊されたあと再度集積するという過程を、何度かくりかえした跡だという説もあるが、まだその原因はわかっていない。 また、・・・直径が1610キロと天王星の衛星中最大のチタニアの表面にはクレーターが比較的少なく、地質学的には比較的最近何かの活動があったのではないかと考えられる。それを裏づけるかのように、東西に走る長さ1500キロ以上の断崖谷が発見された。・・・ |
とある。1610キロの直径に1500キロの断崖谷とは、ほとんど真っ二ということだろう。ミランダの溝と合わせて、「猛々しく」「わけられた」というので。「建日方別(たけひがたわけ)」といってもまったくおかしくない。
8個の惑星とすると、の最外周になる、海王星の衛星の特徴は
|
最大の衛星トリトンは、ユニークな特徴をもつ天体である。トリトンは海王星から35万キロの円軌道を、海王星の自転方向とは逆回りに公転する逆行衛星である。 |
とあるから、逆回りすれば、大変なエネルギーの浪費となるだろうから、「天の忍男(おしを)」は、忍んで回っていると解すれば、実に適切な表現ではないか。
大八島とは太陽系の惑星のこと
以上のように、「吉備の児島より天の両屋の島まで并はせて六島」はニュートンの記述とぴたりと一致してしまった。この対比の一致に勇気を得て、「大八島」の名前も検討してみた。最初の数字は太陽から数えた時の順、()の数字は古事記に現れた順番である。
1 水星(5) 伊岐の島、別名、天比登都柱(あめひとつはしら)
|
水星のコアの謎:水星の半径の3分の2から4分の3からなる非常に大きな金属のコアが存在する。・・ |
柱とはコアのことではないのか。ちょっと苦しいが、伊岐(いき)の「い」というのは、いちばんの「一」というのは、どうだろう。
2 金星(6) 津鳥(つしま)、別名、天の狭手依比賣(さてよりひめ)
金星は、「明けの明星、宵の明星」言われる。地平のはて最初に現れる星である。だから。一番星といわれる。そして、夜空に現れる星の中では最も明るく目立つ。「さてより」は「はて」「よって」あらわれ、目立つことから、「ひいでて」「めだつ」で「ひめ」というのではないか。「津鳥(つしま)」の「つ」は次の島という意味の「つ」としたら、意味は通らないか。
3 地球(8) 大倭豊秋津島(おおやまととよあきつしま)別名、天つ御虚空豊秋津根別(あまつみそらとよあきつねわけ)
ニュートンでは『生命にあふれた水惑星』というタイトルで次のように書かれている。
|
地球の最大の特徴は、太陽系で唯一、液体の水が表面に存在している点である。表面の70%は海洋におおわれている。地球には生命が満ちあふれている。液体の水があるからこそ、生命が存在できるのである。地球は私たちのふるさとである。そのため、地球のような環境が当然のように考える人も多い。しかし太陽系のほかの惑星や衛星を見渡せば、地球がいかに特異な惑星であるかがすぐわかるだろう。今のところ地球だけが生命を宿す唯一の惑星である。 太陽系の惑星は、地球のように主に岩石や金属からなる「地球型惑星」と、ガスを主成分とする、「木星型惑星」の2種類に分けることができる。太陽に近い水星、金星、地球、火星が地球型惑星である。・・・地球の大きさ−地球の赤道半径は6378キロである。これは太陽の0.9%、木星の8.9%ほでであり、地球型惑星の中では最大である。 |
「おおやまととよあきつしま」「みそらとよあきつねわけ」、言葉の雰囲気から、生命にあふれた豊かさを感じられないだろうか。「みそら」は「大気」で「とよ」とは豊かで「あき」は「酸素」のことなどと考えてしまうのである。いずれにしても、古事記の表現の中ではダントツに生命の存在を感じる表現である。これを、地形に置き換えて本州にしてしまうと、どの島だって、生命にあふれるのだから、この言葉の意味は通じなくなってしまう。
4 火星(7) 佐渡(さど)の島。
火星は『砂嵐の吹き荒れる荒涼とした赤い大地』とあるから、「さど」は「砂」の「土地」か。
5 木星(2) 伊予の二名の島。身一つ面四つ 末尾の(#)は古事記に現れた順。
木星は別名を『木星は太陽になりきれなかった惑星』と言われる。まさに二つの名前がある。
また、「身一つ面四つ」というのは、四つの特徴と考えてみることもできる。「身一つ面四つ」という表現は、この太陽系で最大のガス惑星の木星と、2番目に大きい、土星に相当すると思われる「筑紫の島」にも使われていることから、伊予の島と筑紫の島をそれぞれを九州と四国の土地として当てはめるより、二大ガス惑星の特徴として相当させた方が、結びつき方も自然である。
●土左の国を建依別(たけよりわけ)4)
|
−−あざやかな縞模様−−ボイジャ探査機やハッブル望遠鏡が撮影した木星の写真をみると、赤や茶色、白などの縞模様が美しい。・・・ |
土星に相当すると思われる「筑紫(つくし)の島の熊曾(くまそ)の国の建日別(たけびわけ)」と言い方が似ている。ちがいは「より」と「び」だけである。「より」の方が「び」より目立つ表現になるだろう。そうすると、ニュートンでは土星の縞模様は『土星にもみられる縞模様』で、木星は『あざやかな縞模様』と表現されている。ゴロがうまく合いすぎて怖いみたいだ。
●粟の国を、大宜都比賣(おおげつひめ)3)
|
ガニメデは半径2600キロ(*直径では約5200キロ、地球の月は直径3500キロ)という大きさを持つ、太陽系最大の衛星である。ガニメデの表面は、明るい部分と暗い部分にわかれている。明るい部分は筋のようにみえる谷が密集している。暗い部分はクレーターにおおわれており、40億年前にできた地形であると考えられている。 |
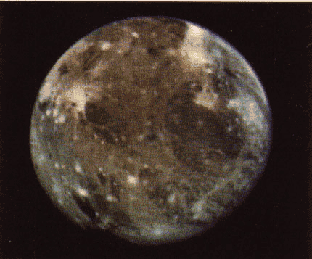
ガニメデ ニュートン1995.April Vol.15 No5より
太陽系で最大の月(衛星)だから、おおきな、つき、ひめ?。
●讃岐(さぬき)の国を飯依比古(いひよりひこ)2)
すでに、木星の衛星の特徴で書いたが、その後の文章を続けると、
|
−−ボイジャの発見した薄いリング−−木星のリングの発見は、ボイジャー探査機の重要な成果の一つである。リングは木星の半径の約1.8倍のところにあり、たいへんに薄い。そこから木星の表面まで、さらに薄いリングが広がっている。この二つのリングを囲むような形で、ぼんやりとした物質の取り巻きが、はるか遠くまで広がっていることがわかっている。 地上からのスペクトル観測の結果では、リングを構成している物質は岩石(ケイ酸塩など)と思われているが、まだ確定はできていない。リングの粒子はマイクロメートルサイズのきわめて細かい物質である。このような細かい粒子は、木星の磁気圏との相互作用などにより10万年程度で木星の本体へ落下してしまうが、リングを維持するためには粒子がどこからか供給させなければならない。この役目をはたしているのはリングのすぐ外側をまわる小惑星、アドラステアではないかと考えられている。イオの噴煙も供給源の一つとなっているのだろう。 |
しかし、これでは、「いよりひこ」の感じは伝わってこない。「糸がよりそう」とイメージされるので、インターネットでもうすこし探ってみた。すると、次のような記事が見つかった。
|
氷の塊でできた土星のリングとは異なり、繊細な木星のリングは惑星間塵が木星の小惑星に衝突する際にまい上がる微粒子で作られています。1998年9月15日、探査機ガリレオから送られてきたデータを分析した科学者によってかつて謎とされていたかすかな木星のリングが発見され、またその誕生の理由も解明されたとの発表がなされました。・・・ 約20年前、ボイジャーが初めて木星リングの構造を撮った画像を送ってくれました。それによると、ぺちゃんこなメインリングもハローと呼ばれる内側の雲に似たリングも、小さな暗い粒子でできていることが分かりました。探査機ボイジャーが撮った一枚の画像に、かすかな外側のリングが写っているように見えました。ガリレオが送ってきた新しい画像には、透明なことからゴッサマーリングと呼ばれる三番目のリングは、実際は二本のリングでできていることが分かりました。つまり、一本のリングが別のリングの中に納まっていたのです。 二本のリングは、衛星のアマルテアとテーベから放出される微粒子でできています。「初めて、ゴッサマーリングにより留め置かれたこれ等二つの衛星から放出される塵を見ることができ、そして現在ではメイン・リングは、衛星のアドラステアとメーティスの塵でできているらしいと考えられるようになりました」と、コーネル大学の科学者ジョセフ・バーンズ氏は語っています。これに付加えて、NOAOのマイケル・ベルトン氏は、「ゴッサマーリングの構造は、全く予測していないものだった」と、言っています。・・・ http://www.planetary.or.jp/Report/R9811-12_a.html
|
私が参考にしたニュートンの記事は1970年代も終わりに近い頃の探査機ボイジャーのデータである。その後、1998年に探査機ガリレオのデータを元にした記事が上記のものである。まさに「糸のように細いものがよりそう」→「いよりひこ」という連想が生まれくるではないか。
●伊予の国を愛比賣(えひめ)1)
|
−−赤い渦巻きのなぞ−−木星の表面で最も特徴的なものといえば、南半球にみられる大赤斑(だいせきはん)である。地球の直径の3倍をこえるこの巨大なだ円形の渦は、現在まで300年も消えず観測されつづけている。・・・大きさは東西24,000キロ、南北13,000キロ 大赤斑の成因については、昔からいろいろ考えられている。・・・(いろいろな)説などが上げられているがはっきりしたことはわかっていない。大赤斑のあざやかな赤い色はたいへん印象的だが、これは赤リンによるものらしい。 |
「身一つ面四つ」と記されている、4つの特徴を、古事記に現れてくる順に関係なく、一致させ易いものから順に並べてきたが、「愛比賣(えひめ)」が、一番最後に残ってしまった。ニュートンでは大赤斑が真っ先にあげられた、木星の最大の特徴なのだが、他の特徴は容易に結びついたのに、この愛比賣(えひめ)と大赤斑が結びつかない。「赤」に結びつく言葉がないのだ。だから、残った木星の特徴と対比させたのだが、全体の雰囲気から、何となく、それっぽいのだが、どうにも結びつかなかいので少々困った。
そこで、「ひ」と言う言葉に注目して、「真理・第四巻青年編・谷口雅春著・日本教文社」に掲載されている言霊のカタログを参考にしてみた。すると、『「ヒ」といふのは「火」の意味であります。この火から色々転じているのでありまして、「光」といふのは、「火(ヒ)輝(カ)り」であります。「ル」とか「リ」はその螺旋回転の意味から動的な感じを与えているのであります。赤い色に「緋」色と云ふのがあります。・・・』とあった。この「緋」に注目すると、意味は「火のような、濃く明るい紅(べに)色」である。そうすると、赤リンのあざやかな赤い色の大赤班を意味することにもなる。というわけでこれも結びついてしまった。
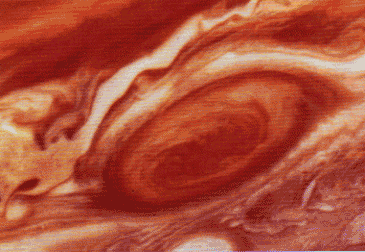
大赤斑は南半球にみられる巨大な渦巻きである。大きさは大きさは
東西24,000キロ、南北13,000キロにもなり、300年以上も観測されつづけている。
ニュートン1995.April Vol.15 No5より
6 土星(4) 筑紫(つくし)の島。身一つ面四つ
土星は、太陽系で二番目に大きいガス惑星である。『赤道半径にくらべ極半径が6300キロも短い、平たい惑星』と呼ばれている。南極と北極が「くっついた」ということから、「つくし」なのか。その4つの特徴は
●筑紫の国を白日別(しらびわけ)1)
|
土星にも大気中にときおり渦(うず)巻き状の斑点模様ができる。この点も木星に似ているが、木星とことなり、この斑点模様は白いので「大白斑(だいはくはん)」とよばれる。 |
●豊(とよ)の国(くに)を豊日別(とよひわけ)2)
|
細かい粒子からなるリング−− 土星最大の特徴は、雄大なリングである。・・リングにはところどころにすき間が開いている。・・比較的大きなすき間には「カッシーニ間隙(かんげき)や「エンケ間隙」などといった名前がつけられている。 リングの成因−−ボイジャー探査機の観測により、一枚の板のように見えたリングが、実際には1000以上もの細かいリングの集まりからなっていることがわかった。これだけ細かいリングをつくるためには、衛星の作用だけでは説明しきれない。 ・・リングの中には奇妙にねじれた形をしたものや、まるで自転車のスポークのような模様をもつものがある。このような、これまでのリングの概念をくつがえすような形状の原因については、まだ確実な結論はでていない。 |

BリングとCリング ニュートン1995.April Vol.15 No5より
『1000以上もの細かいリングの集まり』だから、ゆたかに(とよ)、秀でて(ひ)、わけられる(わけ)。或いは「輪」。
●肥の国を建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)3)
|
土星の最大の衛星であるタイタンは、半径が約2600キロ(ガニメデも半径2600キロ)で太陽系の衛星の中でも最大級にである。・・・タイタンは、地球の1.5倍の濃い大気(1.5気圧)をもつ珍しい衛星である。地球の半分のサイズにも満たない衛星でこれだけ濃密な大気を維持できる理由は、タイタンが非常に冷たい環境にあるからである。マイナス180度cという寒さである。このような環境では大気を構成するガスの分子の運動が鈍くなり、タイタンの重力でもガスを引き止めておくことができるのである。 タイタンの大気の主成分は窒素で、メタンが数%まじっている。またシアン化水素なども見つかっており、アセチレンやエチレンなどの有機物も検出されている。このことから、タイタンの表面にはかなり複雑な有機物が存在する可能性もあるとみられている。タイタンには生命が誕生している可能性もあるという人もいる。あそらくタイタンには広大なメタンの海が広がり、濃密な大気の中ではメタンの雨が注いでいることだろう。 タイタンは、原始地球の環境に似ているといわれる。生命誕生のなぞをとくかぎをにぎっているかもしれない。 |
肥の国というのが、濃密な大気を連想させる。建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)という名前も、地球の「天つ御虚空豊秋津根別(あまつみそらとよあきつねわけ)」の表現の雰囲気がにていて、ともに、豊かな大気を思わせるし、「原始地球の環境に似ている。生命誕生のなぞをとくかぎ」などの表現を連想させるものがある。
●熊曾(くまそ)の国を建日別(たけびわけ) 4)
既に説明したが、『土左の国を建依別(たけよりわけ)』と言葉が似ているから、『土星にもみられる縞模様』のことであろう。
|
−−土星にもみられる縞模様−− 土星にも木星と同様、赤道に並列な縞模様がみられる。このことからも大気の運動が木星とよく似ていることがわかる。 |
7 天王星(1) 淡道(あはじ)の穂(ほ)の狭別(さわけ)の島
|
−−11本の細いリング−−・・・ボイジャー探査機の観測などにより、天王星のは全部で11本のリングがあることがわかった。いずれも幅は数十キロと細く、土星のように幅が広くない点が大きな特徴である。天王星のリングは、ほとんどがメートルサイズより小さな物質からできているらしい。具体的な成分は不明であるが、たいへん暗い物質でできていることはわかっている。 |
これが「あわい」「穂(ほ)」先のような、ということで「淡道(あはじ)の穂(ほ)」。
狭別(さわけ)の意味は、
|
異常な特徴は過去におきた大衝突の結果か おだやかな外見とは反対に、天王星は太陽系の中でもかなり異常といえる特徴を持っている。自転軸の傾きをみると、天王星は98度もある。つまり天王星は横倒しになった状態で太陽のまわりをまわっている。しかも、天王星の衛星もすべて、自転軸の傾きに合わせて横倒しになった赤道面上を公転している。 自転ばかりではない。天王星の磁軸は中心から30%もはなれたところを通っている。過去に経験した大衝突の結果、このような特徴をもってしまったのかもしれない。 なぞに満ちた衛星 天王星の衛星は全部で15個存在する。このうち五つは比較的大きく、・・・これらの衛星の中でとくに話題を集めたのは、5大衛星のうち最も内側をまわるミランダである。半径わずか250キロ程度のこの小さな衛星の表面に、まるで何かでひっかいたような巨大な地形や、深さ20キロに達する溝がみつかった。このような地形は、過去にミランダが破壊されたあと再度集積するという過程を、何度かくりかえした跡だという説もあるが、まだその原因はわかっていない。 ・・・直径が1610キロと天王星の衛星中最大のチタニアの表面にはクレーターが比較的少なく、地質学的には比較的最近何かの活動があったのではないかと考えられる。それを裏づけるかのように、東西に走る長さ1500キロ以上の断崖谷が発見された。・・・ |
「狭別(さわけ)」の、「さ」には「性質、状態のへだたり」という意味もある。先に天王星の衛星の特徴は「建日方別(たけひがたわけ)」ではないかといったが、異常な力によって分けられた星と言えるではないか。
8 海王星(3) 隠岐(おき)の三子(みつご)の島、別名、天の忍許呂別(おしころわけ)
海王星は、冥王星を外せば一番外側になる。したがって、太陽系ができた当初は、いちばん遠いところを回っていた。「おき」は「沖」のことだろう。
|
海王星の衛星 ボイジャーによって6個の新衛星が発見され、海王星の衛星はトリトン、レネイドと併せて8個が知られるようになった。 ・・・最大の衛星トリトンは、ユニークな特徴をもつ天体である。トリトンは海王星から35万キロの円軌道を、海王星の自転方向とは逆回りに公転する逆行衛生である。そのためトリトンは、どこかほかの場所で誕生したあとから海王星の重力にとらえられたという説がある。レネイドもトリトンと同様に捕獲天体の可能性がある。 |
|
冥王星は、海王星最大の衛星であるトリトンに、大きさや密度、薄い大気をもつ点がよく似ている。したがってトリトンの起源については同じような過程を経て形成された天体が、一方は海王星にとらえられて海王星をまわる衛星となり、もう一方は太陽を公転する惑星になったともいわれる。カロンの起源もなぞである。 |
「三子(みつご)の島」は、上記から、レネイド、トリトン、冥王星は同じ性質の三つの星ではないか。まさに、三子の島である。
ラテン語の数字は、1はモノ(mono)、2はジ(di)、3はトリ(tri)、4はテトラ(tetra)、5はペンタ(penta)・・・と続く。3は「トリ(tri)」である。そういえば、サンスクリット語でもヴァータ、ピッタ、カファはトリ・ドーシャと呼ばれている。やはり3は「トリ」と呼ばれる。だから、トリトンの「トリ」はこのことかも知れないと思ったが、トリトンという名前は、ギリシャ神話のほら貝の名人で下半身は魚で上半身は人間の、人魚のような神様である。だから、数字との関連はない。
さらに、考えてみると、ニュートンの記述では、三つの星は別の場所でできて、捕獲されたと考えられているようだが、別の考え方として、太陽系ができた初期の頃は、まだ冥王星はなかった。太陽系の最外周の軌道を回る惑星は海王星だったが、その衛星には特徴のある三つの月があった。トリトン、レネイド、冥王星である。それが、何かの理由で、冥王星のみ、海王星の軌道から外れ、さらに外周の太陽系の軌道を回るようになったというのはどうであろう。こんなことは、ニュートンには書かれてないが、したがって、こうした説は未だ学界には存在しないのだろうが、古事記の記述はそのようにもとれる。今より1300年前に書かれたものが、それを知っていたとしたら、実に面白いことになると思う。
天(あめ)の忍許呂別(おしころわけ)の意味は、
|
反時計回りの渦、海王星の巨大に大暗斑 木星型惑星の中で。海王星は太陽系の最も外側にある。現在は太陽から30天文単位の軌道にある。・・・海王星表面の南緯22度には、木星の大赤斑や土星の大白斑(だいはくはん)と同様の卵形の渦があり、約16日の周期で反時計回りに回転している。この渦は「大暗斑」と呼ばれている。 |
最初は、反時計回りと言うことで、これを「おしころわけ」に結びつけようとしたが、そうすると大赤班だって反時計回りである。反時計回りは、太陽系の「順行」である。決して「逆行」しているわけではないから、これでは、結びつかない。
しかし、トリトンは『海王星の自転方向とは逆回りに公転する逆行衛星』だから、忍んでころがる、という意味で「忍許呂別(おしころわけ)」はピッタリだ。ただ、こうすると、既に、海王星の衛星の特徴を「天の忍男(おしを)」ということで、一度取り上げている。ここでも取り上げられたとすれば、古事記は同じものに二度、名前をつけたことになってしまう。
やはり、無理があるのか。それに、ここまでの説明では、いくら名前に似たものがあったとしても、「そう言うことは言えるかも知れないが・・」ということになって、古事記の島の生成が、太陽系に結びつくという、根拠には今ひとつ乏しいものがある。ダメか!と思ったのだが、同じことを二度説明しているのは、ここだけではなかったことを思い出して、表にしてみた。二度にわたり出てくる星や、その特徴と結びつく名前は下の表のようになる。そうすると、古事記の中では脈絡なく記述されていたものが、整合性をもって、並んでしまった。
|
惑星名 |
特徴 |
六島(衛星の特徴) |
八島(惑星の特徴) |
|
木星 |
リング |
大多麻流別(おおたまるわけ) |
飯依比古(いひよりひこ) |
|
土星 |
リング |
大野手比賣(おほのでひめ) |
豊日別(とよひわけ) |
|
天王星 |
大衝突 |
建日方別(たけひがたわけ) |
狭別(さわけ)の島 |
|
海王星 |
トリトン |
天の忍男(おしを) |
天(あめ)の忍許呂別(おしころわけ) |
例えば、木星のリングの特徴は、薄い二重のリングだから「おおたまるわけ」。そのさらなる特徴はゴッサマーリングの「いひよりひこ」となる。土星もしかりで、天王星は大衝突の結果、天王星に「さわけ」の力がはたらき、衛星も、猛々しく分けられた(たけひがたわけ)となる。こうしたことは、古事記の六島と八島は記述上からでは関係は伺い知ることはできない。にもかかわらず、惑星とその衛星に当てはめてみると、共通した概念で結びあってしまうのである。
このような整合性は、木星と土星の特徴の関係にも見られる。次は、「身一つ面四つ」として、生み出された島々を、古事記に出てくる順にしたがって書き出し、表にしたものである。そして、それに相当するニュートンの記述を重ねると、きれいに下の表のように、1は惑星表面の渦に、2はリングに、2は衛星に、4は惑星の外観、というようにそれぞれの特徴が分類できてしまった。
|
|
|
|
1 |
伊予の国を愛比賣(えひめ) |
大赤斑 |
筑紫の国を白日別(しらびわけ) |
大白斑 |
|
2 |
讃岐の国を飯依比古(いひよりひこ) |
薄いリング |
豊(とよ)の国を豊日別(とよひわけ) |
雄大なリング、概念をくつくつがえす様々な形状 |
|
3 |
粟の国を大宜都比賣(おおげつひめ) |
太陽系最大の衛星ガニメデ |
肥の国を建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ) |
地球の1.5倍の濃い大気タイタン |
|
4 |
土左の国を建依別(たけよりわけ) |
あざやかな縞模様 |
熊曾の国を建日別(たけびわけ) |
土星にもみられる縞模様 |
ニュートンに書かれている、現代科学が発見した太陽系の特徴と、1300年前に書かれた、古事記の島の名前から連想するイメージを重ねあわせてゆくと、苦労することなく、自然に呼び合うように一致してしまう。これほどの一致は、島の名前を本州や九州、四国などの地名にそって当てはめたのでは、絶対に得られない。例えば、「肥の国」は、武田祐吉訳注によると、『誤記があるのだろう。肥の国(肥前肥後)の外に、日向の別名があげられているのだろうというが、日向をいれると五国になって、面四つありいうのが合わない。』とか、「知詞(ちか)の島、天の忍男(おしを)」の『所在は不明』となって、どうにも合わないところが出てくるのである。
古事記の言葉を太陽系の星々に結びつけなければ、このような特徴と概念の一貫性は絶対に生まれてはこないのである。神代の巻の島の生成は、過去の誰がおこなった解釈よりも、太陽系の特徴と対比させた方が最もよく似合う。最先端の科学がとらえた真実と、わが国最古の文章の内容は一致するということは、古事記はおとぎ話や作り話ではなく、真実を物語っていたと言えるではないか。
余談になるが、古事記の「島の生成」の項の後は、「神々の生成」となり、大事忍男(おおことおしお)の神から始まり、数々の神々が生まれてくる。たぶん、この部分は地球の46億年の歴史に相当する部分ではないかと思う。闇戸(くらと)の神は、地球に大隕石がぶつかって、その後、舞い上がった塵によって起こった太陽光の遮断、大戸或子(おおとまどひこ)は、生物の大量絶滅と再生、などというイメージが想起される。また、以上のような太陽系、地球規模の話とは関係はないが、言語学上の問題として、「ひめ→姫」、「ひこ→彦」という言葉にも注目して良いと思う。この言葉は、フランス語やスペイン語などの、男性名詞、女性名詞と、関係がありそうな気がする。「ひめ」、「ひこ」がつかない名刺は中性名詞になるのではないだろうか。いずれにせよ、古語の言葉の「ふり」を突き詰めてゆけば、新たな発見がありそうである。
本居宣長は
|
凡て神代の伝説(ツタエゴト)は、みな実事(マコトノコト)にて、その然有(シカア)る理は、さらに人の智(サトリ)のよく知ルべきかぎりに非れば、然(サ)るさかしら心を以て思うべきに非ず。 |
と言った。このように見ると、この言葉の底知れぬ、重みをひしひしと感ずる。どうして、このような確信が生まれるのか。「もののあはれ」を知る本居宣長の「こころ」が、その「しな」にしたがい、古事記の「言葉のふり」、「言霊(ことだま)」についての徹底的な考証をおこなった。そして、そこに、驚くべき古代の人々の英知を発見したのだ。
サンスクリット語にナーマ・ルーパという言葉がある。「ナーマ」は「名とか音」であり、nemeの語源でもある。「ルーパ」とは「形とか質」だといわれている。この宇宙のすべては、現れるための条件として、名と形(ナーマとルーパ)の両方を持つ、というのである。わが国の古代の人々も、このことを、しっかりと認識していた。思惟は、ことば(言葉)となり、言葉は、こと(事)の、は(発)となる。こうして物事は生まれる。「言」と「事」同じなのだ。したがって、言葉の響きの中にすべては存在している。このことを、古代インドの人々も、われわれ日本の祖先も確かに知っていた。
言霊の確かさと、不思議。事と言とは一体、神々の名(ことば)は働き。心を澄ませばそれが見えてくるのだ。心の中にきざして来る思いがある。それに耳を傾ける。直観的思考とは、そうした心に投影して物事を考え把握しようとする方法といえるが、それを極めれば神々の姿が見えてくるのだ。かって、わが国は言霊のさきわう国とよばれていた。近頃の日本人はそのことをすっかり忘れてしまったようである。なぜ、この真実が失われてしまったのか。本居宣長はその原因は「漢心」にあると見た。
|
彼は、上代人の言語経験が、上代文化の本質を成し、その最も豊かな産物が「古事記」であると見ていた。 ・・・明らかな事は、無きことを、有りげにいひなす理と、有る事の上に、顕(*あら)はに見えた理と、言はば空理と、実理とを、宣長ははつきりと区別して、考へている事だ。次に、この実理を掴んで、考へを深めて行けば、当然、理はいくらでも精しくなる。古伝説に現実的な意味合いを読み取る事も出来るやうになる。「 古事記伝」の言ひ方で言へば、「尋常(ヨノツネ)の理」に精しくなれば、「其ノ外に測リがたき妙理(クシキコトワリ)のあることを知る」やうになる。さういふ考へだ。宣長は、さう考へるとともに、空理を捨てて実理を取るといふ、当り前な事が、何故、かうもむつかしいのか、何故、世の識者達は、皆争つて空理に走るのか、といふ疑問に出合ふ。この疑問は、「古事記伝」を書く動機と堅く結ばれている。わが国で一番古い、又今日まで一番重んじられて来た史書「(*日本)書記」を開けば、一目瞭然の事だが、「天地の初発(ハジメ)のありさまが」が、もう陰陽の空理によつて説かれている始末である。古伝説の正実(マコト)を捨てて以来、千余年、識者達の「漢意(カラゴコロ)の痼疾(フカキヤマヒ)」は治らない。「漢籍説(カラブミゴト)に迷った病者には、陰陽の理と言はれれば、天地自然の理として、すべての物も事も、この理を離れては考へられぬ。病は其処まで来ている。 ・・・「この陰陽の理といふことは、いと昔より、人の心の底に深く染着(シミツキ)たることにて、誰も誰も、天地の自然(オノズカラ)の理にして、あらゆる物も、此の理をはなるることなしとぞ思ふめる、そはなほ漢籍説(カラブミゴト)に惑へる心なり、漢籍心(カラブミゴコロ)を清く洗ひ去りて、よく思へば、天地はただ天地、男女(メヲ)はただ男女(メヲ)、水火(ヒミヅ)はただ水火(ヒミヅ)にて、おのおのその性質情状(アルカタチ)はあれども、そはみな神の御所為(ミシワザ)にして、然るゆえのことわりは、いともいとも奇霊(クスシ)く微妙(タヘ)なる物にしあれば、さらに人のよく測知(ハカリシル)べきはにあらず(古事記伝、書紀の諭ひ)。理といふものは、今日ではもう、空理の形で、人の心に深く染付き、学問の上でも、すべての物事が、これを通してしか見られない、これが妨げとなって、物事を直かに見ない、さういふ慣わしが固まつて了つた。白分の願ふところは、ただ学問の、このやうな病んだ異常な状態を、健康で、尋常な状態に返すにある。学問の上で、面倒な説など成さうとする考へは、自分には少しもないのであり、心の汚れを、清く洗ひ去れ、別の言葉で言へば、学者は、物事に封する学問的態度と思ひ込んでいるものを捨て、一般の人々の極く普通な生活態度に還れ、といふだけなのだ。 ・・・空理など頼まず、物を、その有るがままに、「男女(メヲ)はただ男女(メヲ)、水火(ヒミヅ)はただ水火(ヒミヅ)」と受取れば、それで充分ではないか。誰もが行つている、物との、この一番直かで、素朴な附き合ひのうちに、宣長の言ひ方で言へば、物には「おのおのその性質情状(アルカタチ)が有る、と疑ひやうのない基本的な智恵を、誰もが、おのづから得ているとする。これは宣長が、どんな場合にも、決して動かさなかつた確固たる考へなのであつて、彼は、学問は、そこから出直さなければならない、と言ふのである。この基盤を踏み外さずに、考へを進めて行く限り、理の働きは、いよいよ精しくなるのは当り前で、さういう顕はに見える理の働きを、否む理由は全くない。自分の歩いた道も、言つてみれば。「尋常(ヨノツネ)の理」を超えて、「妙理(クスシキコトワリ)」に至る、この一と筋であった。「古事記」といふ「物」に添うて、考へ詰めたところに、「古ヘの伝説(ツタエゴト)」の趣は、今日の世にも新しい意味合いを帯びて生きているのを見た。彼は、そこまで、「古事記」を読み熟(コナ)した。 ・・・「古事記」の「神代一之巻(カミヨノハジメノマキ)」は神の名しか伝へていない。「古事記」の著者が、それで充分としたのは、神の名は、神代の人々の命名といふ行為を現している点で、間違ひのない神代の事跡だからだ。さういう事に、人々が全く鈍感になつて了つたのは、後世発達した、「さかしだちて物を説く」傾向による、と宣長は考へた。「さかしだちて物を説く」人は、「物のことわりあるべきすべ」を説くので、実は、決して物をとかない。物を避け、ひたすら物と物との関係を目指す。個々の物は、目に見えぬ論理の糸によつて、互いに結ばれ、全体的秩序のうちに、組み込まれるから、先ず物は、物たる事を止めて、推論の為の支点と化する必要がある。なるほど物の名はあるが、実名ではない。或る物と自余の物との混同を避ける為に付された記号、さういう段階に下落した仮の名に過ぎない。 ・・・言ふまでもなく、「物を説く」人には、そういふ事は一向に気にならない事なのだが、諸概念の識別標として、言葉を利用し、その成功に慣れて了ふといふ、避け難い傾向は、どうしても、心の柔らかさを失はせ、生きた言葉を感受する力を衰弱させる。さうしているうちに、言葉とは、理解力の言ふなりに、これに随伴して来る、本来そういふ出来のものである、といふ考へを育てて了ふのである。しかし、物を説く為の、物についての勝手な処理といふ知性の巧が行はれる、ずつと以前から、物に直に行き道を、誰も歩いているのは疑ひやうのないところだ。その第一歩として、物に名を付けるといふ行為がある。物を理解するといふ知的行為が、掩ひ隠して了つた行為があるのだ。神々の名を注釈しつつ、宣長が痛感したのはその事だったのである。 ・・・宣長の言ひ分は、確かに感知される物が、あらゆる知識の根本をなすといふか考へに帰する、といふだけの話なら、一応は、簡単な話と言へよう。だが、前にも言つたやうに、宣長は議論などしているのではなかった。物のたしかな感知といふ事で、自分に一番痛切な経験をさせたのは、「古事記」といふ書物であつた、と端的に語つているのだ。更に言へば、この「古ヘの伝説(ツタエゴト)」に関する、「古語物(コトドヒモノ)」が提供している、言葉で作られた「物」の感知が、自分にはどんな豊かな経験であつたか、これを明らめようとすると、学問の道は、もうその外には無い、といふ一と筋に、おのづから繋がつて了つた。それが皆んなに解つて欲しかつたのである。 ・・・彼は、「物のあはれを知る心」は、「物のかしこきを知る心」と離れる事が出来ない、と言っているのである。我邦の歴史は、物のかしこきに触れて、直ちに嘆く、その人々の嘆きに始まつた、と古伝の言ふところを、宣長は、そのままそつくり信じた。 ・・・ところで、「古事記伝」の「総論」の結びに、「年月を経(ヘ)るまにまに、いよいよ益々からぶみごころの穢汚(キタナ)きことさとり、上ツ代の清らかなる正実(マコト)をなむ、熟(ウマ)らに見得(ミエ)てしあれば、此記を以て、あるが中の最上(カミ)たる史典(フミ)と定めて」とある、・・・宣長には、「世の識者(モノシリビト)」と言はれるような、特殊な人々の意識的な工夫や考案を遙かに越えた、その民族的発想を疑ふわけには参らなかつたし、その「正実(マコト)」とは、其処に表現され、直に感受出来る国民の心、更に言へば、これを領していた思想、信念の「正実(マコト)」に他ならなかつたのである。 ・・・この意識が天武天皇の修史の着想の中核をなすものであった。当時の知識人の先端を行くと言つてもいい、この先鋭な国語意識が、世上に行はれ、俗耳にも親しい、古くからの言伝へと出会ひ、これと共鳴するといふ事がなかつたなたならば、「古事記」の撰録は行なはれはしなかつた。そして、このやうな事件は、其の後、もう二度と起こりはしなかつたのである。 |
私は、自分の治療の世界から、この世界を見る見方に二つの方法がある、ということに、おぼろげながら気づき、その正体を手探りながら、ここに発表してきた。本居宣長を読んだのは、この正体を探るためだった。そして、ここで、やっとその正体がつかめた気がする。上記を読んでもらえば、中国的なものの見方の二原則的な思考というものが、どういうもので、どういう作用をするのかが、わかるであろう。そして、三原則的なものの見方は、古事記の世界を見ればわかる。古事記こそ究極の直観的思考の姿なのだ。だから。小林秀雄も、次のように、言うのである。
|
宣長が、「古事記」の研究を、「これぞ大御国の学問(モノマナビ)の本なりける」と書いているのを読んで、彼の激しい喜びが感じられないやうでは、仕方がないであらう。・・・ |
神の名
長くなったので、そろそろ、終わりにしたいのだが、まだ、二つほど、お伝えしたいことが残っている。その、一つは、「本居宣長」を読んで啓発された、神の概念についてである。驚くことに、この「神」ついての概念が、古代の人々と今日の私たちとは全く違うのである。
|
・・・さて、神といふ「言(コトバ)」の「意(ココロ)」といふ問題に直に入らう。古伝による神の古意については、「古事記伝、三之巻」に詳しい。大事な文であるから、引用は省けない。 「凡て迦微(カミ)とは、古御典等(イニシエノミフミドモ)に見えたる天地の諸(モロモロ)之神たちを始めて、其(ソ)を祀(マツ)れる社に坐ス御霊(ミタマ)をも申し、又人はさらにも云ハず、鳥獣(トリケモノ)木草のたぐひ海山など、其余何(ソノホカナニ)にまれ、尋常(ヨノツネ)ならずすぐれたる徳(コト)のありて、可畏(カシコ)き物を迦微(カミ)とは云うなり、(すぐれたるとは、尊(タフト)きこと善(ヨ)きこと、功(イサヲ)しきことなどの、優(スグ)れたるのみを云に非ず、悪(アシ)しきもの奇(アヤ)しきものなども、よにすぐれて、可畏(カシコ)きをば、神と云なり、さて人の中の神は、先ヅかけまくもかしこき天皇は、御世々々みな神に坐スこと、申すもさらなり、其(ソ)は遠(トホ)つ神と申して、凡人(タダビト)とは遙(ハルカ)に遠く、尊く可畏(カシコ)く坐シますが故なり、かくて次々ににも神なる人、古ヘも今もあることなり、又天ノ下にうけばりてこそあらね、一国一里一家の内につきても、ほどほどに神なる人あるぞかし、さて神代の神たちも、多くは其代の人にして、其代の人は皆神なりし故に、神代とは云なり、又人ならぬ物には、雷は常にも鳴ル神神鳴リなど云へば、さらにもいはず、龍樹霊(タツコダマ)狐などのたぐひも、すぐれてあやしき物にて、可畏(カシコ)ければ神なり、(中略)又虎をも狼をも神と云ること、書記万葉などに見え、又桃子(モモ)に意富加牟都美(オホカムツミノ)命と云名を賜ひ、御頚玉(ミクビタマ)を御倉板挙(ミクラタナノ)神と申せしたぐひ、又磐根木株艸葉(イワネコノタチカヤノカキバ)のよく言語(モノイヒ)したぐひなども、皆神なり、さて又海山などを神と云ることも多し、そは其ノ御霊(ミタマ)の神を云に非ずて、直(タダ)に其ノ海をも山をもさして云り、此(コレ)らもいとかしこき物なるがゆえなり、)抑迦微(カミ)は如此(カクノゴト)く種々(クサグサ)にて、貴(タフト)きもあり賤(イヤシ)きもあり、強(ツヨ)きもあり弱(ヨワ)きもあり、善(ヨ)きもあり悪(アシ)きもありて、心も行(シワザ)もそのさまざまに随(シタガ)ひて、とりどりにしあれば、(貴(タフト)き賤(イヤシ)きにも、段々(キザミキザミ)多くして、最賤(モトモイヤシ)き神の中には、徳(イキホヒ)すくなくて、凡人にも負(マク)るさへあり、かの狐など、怪(アヤシ)きわざをなすことは、いかにかしこく巧(タクミ)なる人も、かけて及ぶべきに非ず、まことに神なれども、常に狗(イヌ)などにすら制せらるばかりの、微(イヤシ)き獣なるをや、されど然(サ)るたぐひの、いと賤き神のうへをのみ見て、いかなる神といへども、理を以て向かふには、可畏(カシコ)きこと無(ナ)しと思ふは、高きいやしき威力(チカラ)の、いたく差(タガ)ひがあることを、わきまへざるひがことなり、)大かた一(ヒト)むきに定めては論(イ)ひがたき物になむありける」 |
わが国の天皇が終戦後、人間宣言を行って、神ではないことを宣言したが、本居宣長の説に従えば、あれは間違っていたことになる。神を西洋のGod(キリスト教の天地創造の神)と解し、西洋の概念の神をわが国「神」の概念に当てはめたところに問題がある。この問題は日本国憲法の問題にとどまらず、明治憲法においても、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるが、ここでの神とは、いかなる神か。おそらく、西洋の「王権神授説」の要素もあると思われるが、そうすると、明治憲法も「神」の解釈において間違っている。
天皇が神であるならば、われわれも「ほどほどに神なる人」である。いや、人間だけではない、犬も狐も山も川も神で、「おおまがつみのかみ」などという神の名前もあるから、悪いやつも神である。となると、みんな神なのだから、神と人とは同次元で一体なのだ。西洋の神のように、十戒を破れば、罰する、恐ろしげな、人の上に傲然と君臨する神ではないのである。これこそ、完全なる平等思想ではないか。これから見ると、絶対の神を認める、西洋の民主主義など、真の民主主義ではないといえる。神代の時代の方が、今日よりはるかに民主的だったとはいえないか。しかし、これは脱線である。神の概念についの話に戻す。
|
「天地初発之時(アメツチノハジメノトキ)、於高天原成神名(タカマノハラニナリマセルカミノミナ)・・・高御産巣日神(タカミムスビノカミ)と神産巣日神(カミムスビノカミ)・・・宣長は、神名の詮索にいろいろ心を配つているが、これは何故かといふと、・・・凡そ事物は、名付けられる事なく、人生に組入れられる事は、決してないと考へられていたからだ。彼の言ひ方を借りれば、−−「凡そ御国の古言は、ただに其ノ物其ノ事のあるかたちのままに、やすく云初名(イヒソメナ)づけ初(ソメ)たることにして、さらに深き理など思ひて言(イヘ)る物」ではないから、その「こころばへ」で産巣日神(ムスビノカミ)という神名を釈くなら、「産巣(ムス)」は「生(ムス)」であり、「日(ビ)」は霊異(クシビ)の意の「比(ヒ)」であり、「凡て物を生成(ナ)すことの霊異(クシビ)なる御霊(ミタマ)」といふことになる。従って、「あらゆる神たちを、皆此神の御児(ミコ)」と見て差支えないわけで、多くの神々の「有ルが中にも仰ぎ奉るべき、崇(イツ)き奉るべき」神と解された。 ・・・「古事記」の「神代之巻」で語られていることは、これはすべて、神と呼ばれた人々の「事跡(コトノアト)」である。「神々の事態(シワザ)である。・・・まさしくさういふ神々の端的な直知といふ事(ワザ)が語られているのであつて、そこには、どんな形の教理も纏(まと)はる余地はない。万物の説明原理だとか、万物に君臨する全能の神とかいふ「寓言(コトヨセゴト)」とは、何の関係もない話なのである。 ・・・古言は、この御霊について、天地の初めの時に、高天原に、成りましたと言ふ他、何も余計な事を言つていない。古伝は、ただこの万物生成の、言はば原動力が、先づ自ら形態(カタチ)を生成した事を、有るがままに語れば、足りるとしたに違ひないのである。 ・・・その神々の姿との出会ひ、その印象なり感触なりを、意識化して、確かめるといふ事は、誰にとつても、八百万の神々に命名するといふ事に他ならなかつたであらう。「迦微と云は体言なれば」と宣長が言ふ時、彼が考へていたのは、実は、そのことであつた。彼らは、何故迦微を体言にしか使わなかつたか。体言であれば、事は足りたからである。「直(タダ)に神其ノ物を指シて」産巣日神と呼べば、其ノ物に宿つている「生(ム)す」といふ活(ハタラ)きは、おのづから眼に映じて来たし、例えば、伊邪那岐神、伊邪那美神と名付ければ、その「誘(イザナ)ふ」といふ徳が、又、天照大御神と名付ければ、その「照らす」徳が露はになるといふ事で、「言意並ニ朴」なる「迦微」と共にあれば、それで何が不足だつたろう。 迦微をどう名付けるかが即ち迦微をどう発想するかであつた。そういふ場所に生きていた彼等に、迦微といふ出来上つた詞の外に在つて、これを眺めて、その体言用語の別を言ふやうな分別が、浮びやうもなかつた。言つてみれば、やがて体言用語に分流する源流の中にいる感情が、彼等の心ばへを領していた。神々の名こそ、上古の人々には、一番大事な、親しい、生きた思想だつたといふ確信なくして、あの「古事記伝」に見られる、神名についての、「誦声の上がり下がり」に及ぶ綿密な吟味が行われた筈はないのである。 |
泣澤女神
二つ目は、こうした神々の御名を心にとどめ、「本居宣長」の最後のページを読んでいて、出会った感動のことである。
|
多くの島々と神々の誕生の物語は、伊邪那美神の死で幕になる。−−「伊邪那美神者(イザナミノカミハ)。因生火神(ヒノカミヲウミマセルニヨリテ)。遂神避坐也(ツヒニカムサリマシヌ)」−−だが、大團圓とでも言ふべきものは、伊邪那岐神の嘆きうちに現れる。・・・ 火の神を生み、神避り坐した伊邪那美神に向ひ、−−「伊邪那岐命詔之(イザナギノミコトノリタマハク)。愛我那邇妹命乎(ウツクシキアガナニモノミコトヤ)。謂易子之一木乎(コノヒトツケニカヘツルカモトノリタマヒテ)。乃葡匐御枕方(ミマクラベニハラバヒ)。葡匐御足方而哭時(ミアトベニハラバヒテナキタマフトキ)。於御涙所成神(ミナミダニナリマセルカミハ)。坐香山之畝尾木本(カグヤマノウネオノコノモトニマス)、名泣澤女神(ミナハナキサハメノカミ)」と。 |
この文の美しさに打たれた。そして、感動のあまり、本を胸に抱いてしまった。古事記の、このくだりは何度も読んでいたから、特に目新しいものではなかった。にもかかわらず、この時ほど、漢字とカタカナで書かれた、文章がこれほど美しく感じられたことはなかった。
ただ、伊邪那岐命の状態を記述しただけの、簡潔な文章なのに、万葉の秀歌以上の美しさを感じた。なるほど、これならば、歌聖、柿ノ本人麻呂の歌もおよばないように思えた。読みにくい旧字体をこつこつ読んできて、古文に慣れたからなのか。文字のない時代に、稗田の阿禮の、大和の古言よりなる古からの語り伝えを、漢字の音訓を拾い対応させながら、かくも見事な伝承の歴史を編集した、安萬侶の苦労を感じたからなのか。
本居宣長が古事記を、「これぞ大御国の学問(モノマナビ)の本なりける」と言ったというのならば、小林秀雄の「本居宣長」は、私に取って、「これぞ学問(モノマナビ)の本」である。しかし、おおかたの読者には、私のこの感動は伝わらないであろう。「一人で舞い上がっている」としか思えまい。そこで、これ以上の解説は野暮に成ることを、承知の上で、皆さんのイメージを広げて、いくらかでも、私の感じたことを伝えてみたいと思う。
先に、太陽系には9個の惑星のうちの冥王星を除く8個までは、古事記の島に当てはめることが出来る、と説いた。では、冥王星は何処にいったのか。私は冥王星は、伊邪那岐命の嘆きによって出来た星だと思うのである。
冥王星とはどういう星か
太陽系の惑星は、個体の表面をもつ「地球型惑星」と、ガスの表面を「木星型惑星」とに分けられる。冥王星は木星型惑星のガス惑星の領域にあるが、個体の表面をもつ、といわれる特殊な惑星なのである、ガス惑星であると同時に、固体表面をもつとは、どういうことかというと、メタンが超低温のため凍った、ために、両者の性質があるのだと言われている。
|
|
|
|
水星 |
木星(地球の11倍) |
|
金星 |
土星(地球の9.4倍) |
|
地球 |
天王星(地球の4倍) |
|
火星 |
海王星(地球の3.9倍) |
|
|
|
冥王星 直径約2300km 月の約3分の2(月の直径は3500km) |
太陽も回る軌道も特殊である。
|
冥王星の奇妙な軌道----太陽系のほかの惑星の公転軌道がほぽ円なのに対し、冥王星の軌道はやや細長いだ円である。だ円の形が、どれくらい円とちがっているかをあらわす数値を「離心率」という。離心率が大きいほど細長いだ円をあらわす。地球の公転軌道の離心率がO.02なのに対し、冥王星の値はO.25である。
この値は水星をしのいで惑星の中では最大である。したがって太陽に最も近づくときには、太陽からの距離はおよそ30天文単位となり、海王星より約1億キロ内側になる。一方、太陽から最も遠ざかるときには50天文単位の距離になる。ほかの惑星の軌道面はほぽ黄道面上にある。最大の水星でも7度であるのに対して、冥王星の軌道面は17度も傾いている。冥王星の公転周期は248年である。1979年に海王星より内側の軌道に入った。海王星軌道の外に出るのは1999年であり、それまでの間、太陽から最も遠い惑星は海王星ということになる。 |
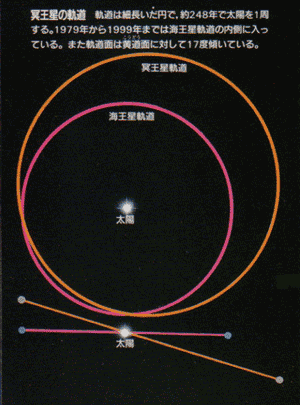
ニュートン1995.April Vol.15 No5より
連星でもある。
|
冥王星と衛星カロン----カロンは1978年に発見された。カロンの軌道を測定することにより、冥王星とカロンの距離がたいへん近いことがわかった。最近の報告では、その距離は1万9500キロ前後とされている。地球の月が、地球半径の約60倍(約38万キロ)の軌道を公転しているのにくらべて、カロンは冥王星半径の約17倍という非常に近い軌道を公転している。・・・冥王星の赤道直径は2300キロ、カロンの直径は冥王星の半分の1200キロである。冥王星は地球の月の3分の2、最大の小惑星であるセレスの2.5倍の大きさしかない。また冥王星に対するカロンの大きさは、衛星としては非常に大きい。冥王星とカロンは惑星と衛星というより連星系といえる。 |
古事記の伊邪那岐の命の嘆きを、書き下すと以下のようになる。
|
かれここに伊邪那岐の命の詔(の)りたまわく。愛(うつく)しき我(あ)が汝妹(なにも)の命を、子(こ)の一木(ひとつけ)に易(か)へつるかも。とのりたまひて、御枕方(みまくだべ)に葡匐(はらば)ひ御足方(みあとべ)に葡匐(はらば)ひて、哭(な)きたまふ時に、御涙に成りませる神は、香山(かぐやま)の畝尾(うねお)の木のもとにます、名は泣澤女(なきさはめ)の神。 |
この、香山(かぐやま)というのは、「か」と「ぐ」の特性、すなわち「かすかな」と「具」の特性のことではないか。ガス惑星と個体型惑星という意味と合う。また、その軌道は、まさに「うねって」いる。これが「畝尾(うねお)」の意味ではないのか。したがって、冥王星は香具山となる。
山という言葉にも意味がありそうである。山は島の中にできる。山は単体では存在できないではないか。島という言葉は惑星にも使われて、地球の月のような単体の衛星にも使われてはいるが、複数の衛星や、もっと多数の衛星群をも島と呼んでいるから、おそらく「香具山」そうした衛星群の中の一つとして存在していたのだろう。だから、「山」という言葉で区別したのである。そして、それはおそらく海王星の衛星だったはずである。
「御枕方(みまくだべ)に葡匐(はらば)ひ御足方(みあとべ)に葡匐(はらば)ひて」とは、太陽系の端から端までという意味で、したがって、その嘆き、「哭(な)きたまふ時に」とは、太陽系を全体を激震させる「なげき」でなのであろう。その時、海王星の衛星が、その軌道より離れ、外惑星となって、冥王星=香具山が生まれたのではないか。「御涙に成りませる」という泣澤女の神は、おそらく冥王星の衛星のカロンであろう。
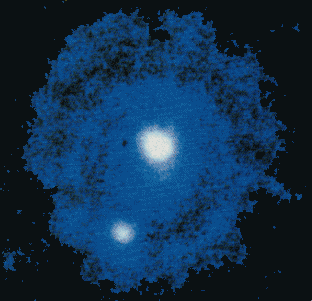
1991年には、ハッブル宇宙望遠鏡で冥王星とカロンの画像が撮られた。 カロンの他には衛星は見つかっていない。
ニュートン1995.April Vol.15 No5より
ジェームズ・ラブロックがとなえた、ガイア仮説というものがある。それは、「地球自身、何らかの意思を持った、れっきとした1個の生命体ではないだろうか」という、考え方である。松井孝典氏も次のように述べている。
|
地球が海をつくり、大陸をつくり、二酸化炭素を減らすような方向へ進化しているという事実は何を意味しているのだろう。互いに関連し合い進化の方向を決めるという意味で、一つの意志が働いているかのようにはみえないだろうか。その意志とは、地球の環境を現在のように安定した環境に何十億年も維持しつづけるということである。 地球の進化とは、たんに熱的に冷えるということだけではない。あたかも地球自身が明確な意志を持っているかのように進化しているのである。その意志とは、いうまでもなく生命の誕生、それも高等生命が生まれ、繁殖し得るような安定した環境をつくり出す方向である。 地球46億年の孤独・松井孝典(新領域創成科学研究科教授)・徳間文庫
|
ガイア仮説の出現は、ようやく、科学も超自然的な意志の存在を、その視野に内に入れはじめてきた、ということだろう。そうした、地球の意志が考えられるのならば、地球を生み出した太陽系の意志をも考えられるだろう。太陽系の意志とは、伊耶那岐(イザナギ)、伊耶那美(イザナミ)の神様の意志ではないか。ここにおいて科学と神話が一致する可能性が出てきたといえる。だが、科学と神話の決定的な差もある。科学は、神の意志を認めつつあるが、その、「嘆き」を伝えてはくれない。
伊耶那岐(イザナギ)の涙で生まれた、泣澤女の神は、奈良県の香具山の麓の、畝尾都多本神社・泣澤女の神の社、に祭られている。では、なぜ、冥王星の衛星カロンに伊耶那岐(イザナギ)の涙を見た、古代人は、香具山の麓に社をもうけたのか。ここにも、わが御親達の、驚くべき英知と、優しさを感じられずにはいられない。なぜならば、この世の事象はすべて、自己相似性をもっている、とカオス理論(拙論、科学的方法論の盲点を参照)は述べているではないか。これが真実ならば、冥王星も地球のあちこちに自己相似の姿をとって現れているはずである。従って、その相似の姿が、奈良県の香具山であり、その麓に、泣澤女の神の社であっても、おかしなことではないはずである。
言ってみれば、これは、音楽での主題のようなものである。作品の中で、主題は、少しずつ形を変えながら、何度でもくり返し演奏される。おなじように、太陽系を作り出した、「意志」は、その姿をすこしずつ変えながら、時空のなかに何度でも繰り返し現れてくるのだ。神の名前とは、言い換えれば、そうした主題につけられたの名前なのだ。神社とは、空間的に表された主題と言うことが出来ると思う。「泣澤女の神」は、そうした空間的主題の一つとして、奈良県の香具山の麓に祀られたのである。わが祖先達は、神々の意志の、細やかな感情の動きをもけっして見逃すことはしなかったのである。
古事記の神々は、全知全能の神ではない。われわれと同じように、成功もし、失敗もし、喜び、嘆き、そして、悪い神にもなり、遂には死ぬ。神の社を造り、祭る行為とは、その神々と共に、定めなきこの世を歩もうとした、わが祖先達の「やさしい」行為である。わが国の古代の人々の姿はかくも「うるわしい」のである。
『「故事(フルコト)」は、みな「実事(マコトノコト)であつて、決して「寓言(コトヨセゴト)ではない』。「もののあはれ」知れば、それが見えてくる。