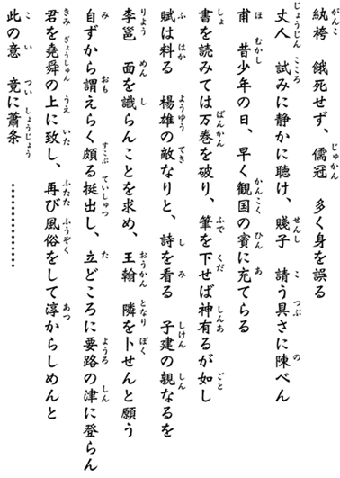直観的思考の点描3
島崎藤村の「夜明け前」
「本居宣長」に継いで、島崎藤村の「夜明け前」を読んだ。「本居宣長」によって発見された、「国学」の思想、神ながらのいにしえの代に帰れという復古の教え、すなわち私の言葉を使わしてもらえば直観的思考法が、あるいは三原則原理の思考法と言ってもよいが、本居宣長の発見以降、どのように変遷していったかを見たかったからである。
|
木曾路《きそじ》はすべて山の中である。あるところは岨《そば》づたいに行く崖《がけ》の道であり、あるところは数十間の深さに臨む木曾川の岸であり、あるところは山の尾をめぐる谷の入り口である。一筋の街道《かいどう》はこの深い森林地帯を貫いていた。・・・
|
20代に、この冒頭の文章の美しさに引かれて、読みはじめて見たものの、木曽谷の庄屋の視点で描かれた、江戸末期の風俗の単調な描写が延々と続くので、変化の乏しい物語の展開に辟易して、数十ページを読んだだけで投げ出してしまった。そんなことを2、3回繰り返しただろうか。あまり文学小説は読まないのだけれども、島崎藤村の作品には心惹かれるところがあって、破壊、桜の木の熟するとき、春、新生・・・等、代表的な作品を、私としては、けっこう読んだ方である。それで、最後の藤村の大作に挑んでみたのだが、1・2巻、それぞれ上下があるので4冊、この分量を読むには、内容が単調すぎて、ついては行けなかった。
しかし、年を取ると言うことは、ありがたい面もある。50歳を過ぎて読んでみると、今度はすこぶる面白い。江戸幕府の断末魔の姿が、木曽谷の庶民の目を通して伺える。明治維新の小説は数々あるが、それらは、坂本龍馬や西郷隆盛など維新の英傑が主人公で、多くは武士の視点からのものである。それらは、戦があったりして、ダイナミックで面白いのだけれど、このような一庶民の視点からのものはほとんどない。
また、国学を信奉する人々の動向を伝えたものもあるにはあるが、その、ほとんどは水戸学派のもので、それらは、やはり武士の立場に立って書かれている。そのような中で、本居−平田派の国学は、どちらかというと、町人や農民、商人に信奉者が多かったことから、これらの人々の視点から明治維新が、かいま見られて面白い。いわば「静」の面白さと言って良い。文章も美しい。文に酔いながら読むという楽しみも味わえた。これらがわかるのには、やはり年を重ねるほかはないようである。
文学の世界には縁がなく、文学作品としての「夜明け前」が、どのような評価をされているのか、よくわからない。しかし、藤村の父、島村正樹がモデルの主人公、青山半蔵の目を通して描かれる「国学」の変遷に注目しなければ、「夜明け前」の真の面白さは語れないと思うのである。また、明治維新の本質にも迫れないはずなのだ。しかし、この視点に立っての論評はあまりない。これは不思議である。なぜ、「国学」というものについて、言葉を変えれば、日本的精神というものについて、論じようとしないのか。意識的、あるいは無意識的に、日本人全体が、それに触れることをためらっているようだ。しかし、ここに踏み込まなければ、日本の明日は開かれない気がする。
|
和助に聞くと、親しい学校友だちの一人が通って来る三十間堀《さんじっけんぼり》もそこからそう遠くない。その足で彼はそちらの方へも和助に案内させて行って見た。春先の日のあたった三十間堀に面して、こぢんまりとした家がある。亡き夫の忘れ形見に当たる少年を相手に、寂しい日を送るという一人の未亡人がそこに住む。
おりから和助の学校友だちは家に見えなかったが、半蔵親子のものが訪ね寄った時はその未亡人をよろこばせた。彼は和助の見ている前で、手土産がわりに町で買い求めた九年母《くねんぼ》を取り出し、未亡人から盆を借りうけて、いきなりツカツカと座をたちながら、そこに見える仏壇の前へ訪問のしるしを供えたというものだ。
その時の彼の振る舞いほど和助の顔を紅《あか》らめさせたこともなかった。父のすることはこの子には、率直というよりも奇異に、飄逸《ひょういつ》というよりもとっぴに、いかにも変わった人だという感じを抱《いだ》かせたらしい。彼にして見ればかつて飛騨の宮司《ぐうじ》をもつとめたことのある身で、このくらいの敬意を不幸な家族に表するのは当然で、それに顔を紅らめる和助の子供らしさがむしろ不思議なくらいだった。
彼は都会に遊学する和助の身のたよりなさを思って、東京在住の彼が知人の家々をも子に教えて置きたいと考える。そこで、ある日また、両国方面へと和助を誘い出した。・・・
その時も和助は父のそばにいて、ただただありがた迷惑なような顔ばかり。
・・・父と共にある時の和助が窮屈にのみ思うらしい様子は、これらの訪問で半蔵にも感じられて来るようになった。この上京には、どんなにか和助もよろこぶであろうと思いながら出て来た半蔵ではあるが、さて、足掛け四年ばかりもそばに置かない子と一緒になって見ると、和助はあまり話しもしない。父子の間にはほとほと言葉もない。ただただ父は尊敬すべきもの、畏《おそ》るべきもの、そして頑固《がんこ》なものとしか子の目には映らないかのよう。
この少年には、父のような人を都会に置いて考えることすら何か耐えがたい不調和ででもあるかのようで、やはり父は木曾の山の中の方に置いて考えたいもの――あのふるさとの家の囲炉裏ばたに、祖母や、母や、あるいは下男の佐吉なぞを相手にして静かな日を送っていてほしいとは、それがこの子の注文らしい。
どうやら和助は、半蔵が求めるような子でもなく、彼の首ッ玉にかじりついて来るような子でもなく、追っても追っても遠くなるばかりのような子であった。これには彼は嘆息してしまった。どれほどの頼みをかけて、彼もこの子を見に都の空まではるばると尋ねて来たことか。
|
このくだりは、「夜明け前」2巻、下の、三分の二のあたり、ほぼ終わりに近いところの文章である。この和助というのは、藤村自身である。幼き日の自分と父との交流を子が父の視点で描いている。この不思議な対比の中に、親子の機微というものが感じられ、私の好きなところの一つなのだが、幼き日に父を奇異、突飛と感じ、疎んじた藤村が、もっともよき父の理解者となったのである。
これを見ていると、親子の対話が必要などというのは絵空事ではないかと思ってしまう。教育とは、子供に、くだくだとあれこれ伝えるのではなく、子供にどう反発されようとも親は黙っておのれの生きざまを示せば、それで良いのではないか。その時は理解できなくても、それが因となり、時間がたてば果を結ぶことになる。伝承とは、このようにして親から子に伝わるということの、好例のような気がする。しかし、これが本題ではない。
7人兄弟(四男三女)の末っ子で、9歳の頃東京へ出され、もっとも父との縁の薄かった藤村が、もっとも父を良く理解した。そして、父のその果たし得ぬ志を明らかにした。「夜明け前」に描き出された、この主題、日本人が、置き去り、次に捨て去り、ついにはそのことさえも忘れ去ろうとしている問題、それに藤村は、日本人の中で、ただ一人、いち早く気づいていた。
|
「でも、香蔵さん、吾家《うち》の阿爺《おやじ》が俳諧《はいかい》を楽しむのと、わたしが和歌を詠んで見たいと思うのとでは、だいぶその心持ちに相違があるんです。わたしはやはり、本居先生の歌にもとづいて、いくらかでも古《むかし》の人の素直《すなお》な心に帰って行くために、詩を詠むと考えたいんです。それほど今の時世に生まれたものは、自然なものを失っていると思うんですが、どうでしょう。」
半蔵らはすべてこの調子で踏み出して行こうとした。・・・
国学者としての大きな先輩、本居宣長ののこした仕事はこの半蔵らに一層光って見えるようになって来た。なんと言っても言葉の鍵(かぎ)を握ったことはあの大人(うし)の強味で、それが三十五年にわたる古事記の研究ともなり、健全な国民性を古代に発見する端緒ともなった。儒教という形であらわれて来ている北方シナの道徳、禅宗や道教の形であらわれて来ている南方シナの宗教――それらの異国の借り物をかなぐり捨て、一切の「漢(から)ごころをかなぐり捨て、言挙(ことあ)げということもさらになかった神ながらのいにしえの代に帰れと教えたのが大人(うし)だ。
大人から見ると、何の道かの道ということは異国の沙汰(さた)で、いわゆる仁義礼譲孝悌(てい)忠信などというやかましい名をくさぐさ作り設けて、きびしく人間を縛りつけてしまった人たちのことを、もろこし方では聖人と呼んでいる。それを笑うために出て来た人があの大人だ。大人が古代の探求から見つけて来たものは、「直毘(なおび)の霊(みたま)」の精神で、その言うところを約(つづ)めて見ると、「自然(おのずから)に帰れ」と教えたことになる。より明るい世界への啓示も、古代復帰の夢想も、中世の否定も、人間の解放も、または大人のあの恋愛観も、物のあわれの説も、すべてそこから出発している。
伊勢の国、飯高郡(いいだかごおり)の民として、天明(てんり)の民として、天明(てんめい)寛政(かんせい)の年代にこんな人が生きていたということすら、半蔵らの心には一つの驚きである。早く夜明けを告げに生まれて来たような大人は、暗いこの世をあとから歩いて来るものの探るに任せて置いて、新しい世紀のやがてめぐって来る享和(きょうわ)元年の秋ごろにはすでに過去の人であった。半蔵らに言わせると、あの鈴の屋の翁(おきな)こそ、「近(ちか)つ代(よ)」の人の父とも呼ばるべき人であった。
|
無益な言葉を連ねることはあるまい。これが「夜明け前」を貫く主題なのである。先の小林秀雄の本居宣長でも教えられることは多かったが、ここでもハッとさせられることが多い。次の箇所などは、現代においても、そのまま当てはまるばかりではなく、民主主義というものの虚盲・偽善・欺瞞を鋭く指摘していないだろうか。
|
宣長の言葉にいわく、
「古(いにしえ)の大御世(おおみよ)には、道といふ言挙(ことあ)げもさらになかりき。」
また、いわく、
「物のことわりあるべきすべ、万(よろず)の教(おしえ)ごとをしも、何の道くれの道といふことは、異国(あだしくに)の沙汰(さた)なり。異国は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の御国にあらざるが故(ゆえ)に、定まれる主(きみ)なくして、狭蝿(さばえ)なす神ところを得て、あらぶるによりて、人心(ひとごころ)あしく、ならはしみだりがはしくして、国をし取りつれば、賤(いや)しき奴(やっこ)も忽(たちま)ちに君ともなれば、上(かみ)とある人は下(しも)なる人に奪はれまじと構へ、下なるは上のひまを窺(うかが)ひて奪はむと謀(はか)りて、かたみに仇(あだ)みつゝ、古(いにしえ)より国治まりがたくなも有りける。そが中に、威力(いきおい)あり智(さと)り深くて、人をなつけ、人の国を奪ひ取りて、又人に奪はるまじき事量(ことはかり)をよくして、しばし国をよく治て、後の法(のり)ともなしたる人を唐土(もろこし)には聖人とぞ言ふなる。そもそも人の国を奪ひ取らむと謀るには、よろづに心を砕き、身を苦しめつゝ、善(よ)きことの限りをして、諸人(もろびと)をなつけたる故に、聖人はまことに善き人めきて聞(きこ)え、又そのつくり置きたる道のさまもうるはしくよろずに足(た)らひて、めでたくは見ゆれども、まづ己(おのれ)からその道に背(そむ)きて、君をほろぼし、国を奪へるものにしあれば、みな虚偽(いつわり)にて、まことはよき人にあらず、いともいとも悪(あ)しき人なりけり。もとよりしか穢悪(きたな)き心もて作りて、人を欺く道なるけにや、後の人の表(うわ)べこそ尊み従ひがほにもてなすめれど、まことには一人も守りつとむる人なければ、国の助けとなることもなく、その名のみひろごりて、遂(つい)に世に行(おこな)はるることなくて、聖人の道はたゞいたづらに、人をそしる世々の儒者(ずさ)どもの、さへづりぐさとぞなれりける。」
多くの覇業(はぎょう)の虚偽、国家の争奪、権謀と術数と巧知、制度と道徳の仮面なぞが、この『直毘(なおび)の霊(みたま)』に笑ってある。北条、足利をはじめ、織田、豊臣、徳川なぞの武門のことはあからさまに書かれてないまでも、すこし注意してこれを読むほどの人で、この国の過去に想(おも)いいたらないものはなかろう。『直毘の霊』の中にはまた、中世以来の政治、天(あめ)の下の御制度が漢意(からごころ)の移ったもので、この国の青人草(あおひとぐさ)の心までもその意(こころ)に移ったと嘆き悲しんである。
「天皇尊(すめらみこと)の大御心(おおみこころ)を心とせずして、己々(おのおの)がさかしらごゝろを心とする」のは、すなわち、異国(あだしくに)から学んだものだと言ってある。武家時代以前へ――もっとくわしく言えば、楠(くすのき)氏と足利氏との対立さえなかった武家以前への暗示がここに与えててある。御世(みよ)御世の天皇の御政(おんまつりごと)はやがて神の御政であった、そこにはおのずからな神の道があったと教えてある。神の道とは、道という言挙(ことあ)げさえもさらになかった自然(おのずから)だ、とも教えてある。
この自然に帰れ、というふうに、あとから歩いて行くものに全く新しい方向をさし示したのが本居大人の『直毘の霊』だ。このよろこびを知れ、というふうに言葉の探求からはいった古代の発見をくわしく報告したものが、翁の三十余年を費やした『古事記伝』だ。直毘(なおび)(直び)とはおのずからな働きを示した古い言葉で、その力はよく直くし、よく健やかにし、よく破り、よく改めるをいう。国学者の身震いはそこから生まれて来ている。翁の言う復古は更生であり、革新である。天明寛政の年代に、早く夜明けを告げに生まれて来たような翁のさし示して見せたものこそ、まことの革命への道である。
|
『聖人はまことに善き人めきて聞え、又そのつくり置きたる道のさまもうるはしくよろずに足らひて、めでたくは見ゆれども、まづ己からその道に背きて、君をほろぼし、国を奪へるものにしあれば、みな虚偽にて、まことはよき人にあらず。』とは、どうも、アメリカのブッシュ大統領がオーバーラップするのだが、そんな風に感じるのは私だけだろうか。いやアメリカのみならず国家の本質というべきものがここにある。要するに汚いのである。いかに言葉でかざろうとも、略奪に変わりない。
「自然(おのずから)に帰れば、その力はよく直くし、よく健やかにし、よく破り、よく改める」のだとあるが、この理想と精神が明治維新の原動力に成った。しかし、「夜明け前」を読み進んでゆくと、この理想が無惨にも打ち壊されてゆく。そのようなところに注意をすると、退屈どころかすこぶる面白いのである。
木曾街道は、東山道といわれ、東海道とともに、交通輸送の一大動脈とも言うべきものであった。その、木曾街道にまで、時代の「影響は日に日に深刻に浸潤して来ていた。」と書かれている。
馬籠の一庄屋の玄関先を、参勤交代の大名行列が通り過ぎてゆく、黒船のうわさが届く、井伊大老暗殺の桜田門外の変、政略結婚といわれた将軍に嫁ぐ皇妹和宮の通行、伏見寺田屋の変、一橋慶喜の台頭。参覲交代の廃止、それにともない女中方、奥方など武家屋敷のなかにこもり暮らしていた婦人や子供達の郷里に帰る行列、生麦での英人の殺傷、足利将軍の木像の首を晒(さら)しものにした三条河原事件、将軍家茂の京都上洛の一向の通過、悪性の痲疹大流行とおびただしい数の死人、新撰組の台頭、長州征伐の一行の行列、天誅組の大和挙兵、蛤御門(禁門)の変、馬関海峡での長州と英米仏蘭四国連合艦隊の衝突、薩英戦争、水戸天狗党の乱に破れた水戸浪士の通行。参覲交代制度の復活の報、それに応じない諸大名達、第2次長州征伐と幕府方の敗北、王政復古の大号令、大政奉還、ええじゃないかの騒動、戊辰戦争の勃発と東征軍進発などなど、1853年(嘉永6年)から1868年(明治元年)の15年間、激動の歴史が通り過ぎて行くのである。それは、移動のできないタイムマシンに乗って、その窓から、時の流れとともに激しく移り変わってゆく世界を見ているようである。
そして、ついに半蔵らの待ち望んだ維新はやって来た。しかし、それはつかの間の喜びであった。『「王政の古(いにしえ)に復することは、建武中興の昔に帰ることであってはならない。神武の創業にまで帰って行くことであらねばならない。」多くの国学者が夢みる古代復帰の夢』、その理想は文明開化という、真反対な、性急な近代化、西洋化の大波に呑み込まれて、無惨にも風化してゆくのである。
|
どうして半蔵がこんなに先輩の正香を待ったかというに、過ぐる版籍奉還のころを一期とし、また廃藩置県のころを一期とする地方の空気のあわただしさに妨げられて、心ならずも同門の人たちとの往来から遠ざかっていたからで。そればかりではない。復古の道、平田一門の前途――彼にはかずかずの心にかかることがあるからであった。
|
この暮田正香は実在の人物ではないだろう。青山半蔵を静の主人公とするならば、動の主人公というのが暮田正香ではないかと思う。半蔵は木曾の山の中にあって自由に諸国を巡り歩くことができない。そこで、ややもすれば静的な物語の展開になるところを、討幕運動の中心となった京都に自由に行き来し、国事に奔走のできる人物を設定し、物語の展開を静的な単調さから解放しようとしたのではないのだろうか。いわば青山半蔵の分身が暮田正香である。正香がいることにより物語に躍動感が出てくる。
その暮田正香は1863年(文久3年)2月に起きた、足利尊氏・義詮・義満の足利三代将軍の木像の首を引き抜き三条大橋に鳩首した事件のメンバーの一人として設定されている。足利幕府に借りて現幕府を非難したのであるが、幕府に対する反旗が上げられた最初の事件といってもよいだろう。
この文久3年という年は、この鳩首事件の後、長州藩が下関で外国船を砲撃し、薩摩藩は英国艦隊と交戦し、天誅組は倒幕の挙兵を大和で起こし、長州藩は禁門(蛤御門)の変を起こした。いわば、幕府に対し公然と敵対行動が示された年でもあるが、その口火を切ったのが足利三代将軍鳩首事件事件であった。
今日的にいえば、フセイン大統領が衰えたりとはいえ、まだ健在な時に、その銅像を打ち壊すようなものだといったら理解しやすいだろう。それ以前の政治運動は、ここまであからさまに、江戸幕府にたてつくものではなかったのである。
もう一つ注目すべきことは、この事件には、武士だけでなく、平田派の町人や商人も関わっていたことである。彼等は生身の人間を相手の血なまぐさい闘争をせず、木像という象徴を利用した。武士の運動を違った面がみられて面白いと思う。
その暮田正香が幕府の追っ手を逃れ、半蔵のもとに逃げてきた。そのくだりは次のように書かれている。
|
「青山君、やりましたよ。」
二人ぎりになった時、正香はそんなことを言い出した。その調子が半蔵には、実に無造作にも、短気にも、とっぴにも、また思い詰めたようにも聞こえた。
同志九人、その多くは平田門人あるいは準門人であるが、等持院に安置してある足利尊氏以下、二将軍の木像の首を抜き取って、二十三日の夜にそれを三条河原に晒《さら》しものにしたという。それには、今の世になってこの足利らが罪状の右に出るものがある、もし旧悪を悔いて忠節を抽《ぬき》んでることがないなら、天下の有志はこぞってその罪を糺《ただ》すであろうとの意味を記《しる》し添えたという。
ところがこの事を企てた仲間のうちから、会津方(京都守護の任にある)の一人の探偵があらわれて、同志の中には縛に就《つ》いたものもある。正香は二昼夜兼行でその難をのがれて来たことを半蔵の前に白状したのであった。
正香に言わせると、将軍|上洛《じょうらく》の日も近い。三条河原の光景は、それに対する一つの示威である、尊王の意志の表示である、死んだ武将の木像の首を晒《さら》しものにするようなことは子供らしい戯れとも聞こえるが、しかしその道徳的な効果は大きい、自分らはそれをねらったのであると。
この先輩の大胆さには、半蔵も驚かされた。「物学びするともがら」の実行を思う心は、そこまで突き詰めて行ったかと考えさせられた。同時に、平田|大人《うし》没後の門人と一口には言っても、この先輩に水戸風な学者の影響の多分に残っていることは争えないとも考えさせられた。・・・・・
翌日の昼過ぎに、半蔵はこっそり正香を見に行った。御膳何人前、皿何人前と箱書きのしてある器物の並んだ土蔵の棚を背後《うしろ》にして、蓙《ござ》を敷いた座蒲団の上に正香がさびしそうにすわっていた。前の晩に見た先輩の近づきがたい様子とも違って、多感で正直な感じのする一人の国学者をそこに見つけた。
その時、半蔵は腰につけて持って行った瓢箪《ふくべ》を取り出した。木盃《もくはい》を正香の前に置いた。くたぶれて来た旅人をもてなすようにして、酒を勧めた。
「ほ。」と正香は目をまるくして、「君はめずらしいものをごちそうしてくれますね。」
「これは馬籠の酒です。伏見屋と桝田屋《ますだや》と、二軒で今造っています。一つ山家の酒を味わって見てください。」
「どうも瓢箪のように口の小さいものから出る酒は、音からして違いますね。コッ、コッ、コッ、コッ――か。長道中でもして来た時には、これが何よりですよ。」
まるで子供のようなよろこび方だ。この先輩が瓢箪から出る酒の音を口まねまでしてよろこぶところは、前の晩に拳を握り固め、五本の指を屈《かが》め、後ろから髻《たぶさ》でもつかむようにして、木像の首を引き抜く手まねをして見せながら等持院での現場の話を半蔵に聞かせたその同じ豪傑とも見えなかった。
|
この後、暮田正香は捕縛されるが、明治維新の成就と共に罷免され、こんどは維新の功労者として、明治4年頃まで、中央政府で活躍することになる。しかし、その後、中央政府の政策転換と共に左遷されてしまう。その正香が、左遷される任地におもむく途中に馬籠の半蔵を訪ねてきた。
|
正香は一人の供を連れて、その日の夕方に馬で着いた。明荷葛籠《あきにつづら》の蒲団《ふとん》の上なぞよりも、馬の尻の軽い方を選び、小付《こづけ》荷物と共に馬からおりて、檜笠の紐を解いたところは、いかにもこの人の旅姿にふさわしい。
「やあ。」
正香と半蔵とが久々の顔を合わせた時は、どっちが先とも言えないようなその「やあ」が二人《ふたり》の口をついて出た。・・・
やがて半蔵の前に来てくつろいだ先輩は、明治二年に皇学所監察に進み、同じく三年には学制取調御用掛り、同じく四年にはさらに大学出仕を仰せ付けられたほどの閲歴をもつ人であるが、あまりに昇進の早いのを嫉む同輩のために讒《ざん》せられて、山口藩和歌山藩等にお預けの身となったような境涯をも踏んで来ている。今度、賀茂《かも》神社の少宮司《しょうぐうじ》に任ぜられて、これから西の方へ下る旅の途中にあるという。・・・
その時、半蔵は先輩に酒をすすめながら、旧庄屋の職を失うまでの自分の苦い経験を、山林事件のあらましを語り出した。
彼に言わせると、もしこの木曾谷が今しばらく尾州藩の手を離れずにあって、年来の情実にも明るい人が名古屋県出張所の官吏として在職していてくれたら、もっと良い解決も望めたであろう。今のうちに官民一致して前途百年の方針を打ち建てて置きたいという村民総代一同の訴えもきかれたであろう。この谷が山間の一|僻地《へきち》で、舟楫《しゅうしゅう》運輸の便があるでもなく、田野耕作の得があるでもなく、村々の大部分が高い米や塩を他の地方に仰ぎながらも、今日までに人口の繁殖するに至ったというのは山林あるがためであったのに、この山地を官有にして人民一切入るべからずとしたら、どうして多くのものが生きられる地方でないぐらいのことは、あの尾州藩の人たちには認められたであろう。
いかんせん、筑摩県の派出官は土地の事情に暗い。廃藩置県以来、諸国の多額な藩債も政府においてそれを肩がわりする以上、旧藩諸財産の没取は当然であるとの考えにでも支配されたものか、木曾谷山地従来の慣例いかんなぞは、てんで福島支庁官吏が問うところでない。言うところは、官有林規則のお請けをせよとの一点張りである。その過酷を嘆いて、ひたすら寛大な処分を嘆願しようとすれば、半蔵ごときは戸長を免職せられ、それにも屈しないで進み出る他の総代のものがあっても、さらに御採用がない。しいて懇願すれば官吏の怒りに触れ、鞭で打たるるに至ったものがあり、それでも服従しないようなものは本県聴訟課へ引き渡しきっと吟味に及ぶであろうとの厳重な口達をうけて引き下がって来る。その権威に恐怖するあまり、人民一同前後を熟考するいとまもなく、いったんは心ならずも官有林のお請けをしたのであった。
「一の山林事件は、百の山林事件さ。」
と正香は半蔵の語ることを聞いたあとで、嘆息するように言った。・・・・
「見たまえ。」という正香の目はかがやいて来た。「われわれはお互いに十年の後を期した。こんなに早く国学者の認められる時が来ようとも思わなかった。そりゃ、この大政の復古が建武中興の昔に帰るようなことであっちゃならない、神武《じんむ》の創業にまで帰って行くことでなくちゃならない――ああいうことを唱え出したのも、あの玉松あたりさ。復古はお互いの信条だからね。しかし君、復古が復古であるというのは、それの達成せられないところにあるのさ。そう無造作にできるものが、復古じゃない。
ところが世間の人はそうは思いませんね。あの明治三年あたりまでの勢いと来たら、本居平田の学説も知らないものは人間じゃないようなことまで言い出した。それこそ、猫も、杓子もですよ。
篤胤先生の著述なぞはずいぶん広く行なわれましたね。ところが君、その結果は、というと、何が『古事記伝』や『古史伝』を著わした人たちの真意かもよくわからないうちに、みんな素通りだ。いくら、昨日の新は今日の旧だというような、こんな潮流の急な時勢でも、これじゃ――まったく、ひどい。」
「暮田さん、」と半蔵はほんのりいい色になって来た正香の顔をながめながら、さらに話しつづけた。「わたしなぞは、これからだと思っていますよ。」
「それさ。」
「われわれはまだ、踏み出したばかりじゃありませんかね。」
「君の言うとおりさ。今になってよく考えて見ると、何十年かかったらこの御一新がほんとうに成就されるものか、ちょいと見当がつかない。
あれで鉄胤先生なぞの意志も、政治を高めるというところにあったろうし、同門には越前の中根雪江のような人もあって、ずいぶん先生を助けもしたろうがね、いかな先生も年には勝てない。この御一新の序幕の中で、先生も老いて行かれたようなものさね。まだそれでも、明治四年あたりまではよかった。版籍を奉還した諸侯が知事でいて、その下に立つ旧藩の人たちが民政をやった時分には、すくなくも御一新の成就するまではと言ったものだし、また実際それを心がけた藩もあった。
いよいよ廃藩の実行となると、こいつがやかましい。江戸大城の明け渡しには異議なしでも、自分らの城まで明け渡せとなると、中には考えてしまった藩もあるからね。一方には郡県の政治が始まる。官吏の就職運動が激しくなる。成り上がり者の官吏の中にはむやみといばりたがるような乱暴なやつが出て来る。さっきも君の話のように、なかなか地方の官吏にはその人も得られないのさ。国家の事業は窮屈な官業に混同されてしまって、この調子で行ったらますます官僚万能の世の中さ。
まあ、青山君、君だって、こんなはずじゃなかったと思うでしょう。見たまえ、この際、力をかつぎ出そうとする連中なぞが士族仲間から頭を持ち上げて来ましたぜ。征韓、征韓――あの声はどうです。もとより膺懲《ようちょう》のことは忘れてはならない。たとい外国と和親を結んでも、曲直は明らかにせねばならない。国内の不正もまたたださねばならない。それはもう当然なことです。しかし全国人民の後ろ楯なしに、そんな力がかつぎ出せるものか、どうか。
なるほど、不平のやりどころのない士族はそれで納まるかもしれないが、百姓や町人はどうなろう。御一新の成就もまだおぼつかないところへ持って来て、また中世を造るようなことがあっちゃならない。早く中世をのがれよというのが、あの本居先生なぞの教えたことじゃなかったですか……」
酒の酔いが回るにつれて、正香は日ごろ愛誦する杜詩《とし》でも読んで見たいと言い出し、半蔵がそこへ取り出して来た幾冊かの和本の集注を手に取って見た。正香はそれを半蔵に聞かせようとして、何か自身に気に入ったものをというふうに、浣花渓《かんかけい》の草堂の詩を読もうか、秋興八首を読もうかと言いながら、しきりにあれかこれかと繰りひろげていた。
「ある。ある。」
その時、正香は行燈《あんどん》の方へすこし身を寄せ、一語一句にもゆっくりと心をこめて、杜詩の一つを静かに声を出して読んだ。

|
底本は上記の通りだったが、漢文はまったく分からないので調べた。書き下すと次の通りになる。
「杜詩」というのは「杜甫の詩」。有名な「国破れて山河あり」はこの人に詩であることも分かった。杜詩講義3(全4巻)著者:森槐南・東洋文庫によれば、大意は次のようにである。(※はJIS漢字コードにないので、上記の画像の文書を参照してください。)
※(がん)袴という、白絹の袴(はかま)をはく、富貴の家の子弟は、飢えて死んだという例は聞かない。
儒冠(儒者のかぶる冠)を頭に戴いて学問を研究している連中は、多くは身を誤つて遂に餓死するまでに落ちぶれることが多い。(憤激のあまりに発した言葉)
丈人(長老、老人等、尊敬の意をもってよぶ)よ、かく言わなければならない理由を静かに御聴きください。
是より私が細かに其不公平なる所以を具陳(詳しく述べることに)致します。
甫は昔し少年の頃に、試験に応じ、選ばれて(観国の賓となり)、都に出て参りました
書は万巻を読み破り、我が作る文章には神の助けがあるかと思われます。
我が作る賦(詩)は、恐らく漢の揚雄に匹敵するであらうと思われます。
その詩に注目すると、彼の建安七子の頭たる曹子建の親類位にはなろうと思われます。
李※(よう)は、一遍逢つて置きたい者であると言つて、逢ひに来られた。
王翰は、隣人になりたいと申込んで参つた。決して私が独りで自慢を言うわけでは無い。
それ故、数限りなく才人文人はいる事であるが、その中において頗る挺出し(抜きんでて)優れている者と自ら思っている。
(だから)立どころに要路の津に登つて、ふさわしい地位を得る様になるであらう思った。
その地位を得たならば、兼ねてから懐いている抱負、即ち我君を補佐し奉つて古への堯舜の時代(中国古代の聖王達が治めた理想の時代)の昔に復し、そうして、澆季(ぎょうき:人情が薄く、世の乱れた時代)の風俗を、古の淳厚(じゅんこう:あつくゆたか)風俗に復すだけの大経綸(けいりん:国家を治めととのえること)を、必ず行つて見せるという積りであった。
ところが、この志は遂に得られず、希望は空想であった。蕭条(しょうじょう)と物さびしいばかりである。
李※は、唐代の名士で、李北海といい、開元天宝時代の名士。
王翰は、葡萄美酒夜光杯、欲飲琵琶馬上催という詩をつくった王翰で、当代で是も有名な才人。
|
そこまで読みかけると、正香はその先を読めなかった。「この意《こころ》、竟《つい》に蕭条《しょうじょう》」というくだりを繰り返し半蔵に読み聞かせるうちに、熱い涙がその男らしい頬《ほお》を伝って止め度もなく流れ落ちた。
|
こうして、暮田正香は去っていくのだが、それとともに、古代の人々の素直な心を求めよとする、古代復帰の夢は潰えていった。この後、青山半蔵も傷心を酒にのがれ、精神を病み、自分の家の座敷牢で、糞にまみれて死んでゆくのである。
文学には門外漢なので、島崎藤村が文学史の中でどのように評価されているにかをよく知らないが、この結末をもって、明治維新の虚妄性を描いた作品だという評価もあるようである。なかには反体制の作家のとしての評価もあるようで、昔のことになるが、プロレタリアートの作家として位置づけられた評論も読んだ気がする。たしかに「破壊」のテーマにも見られるように、賤民の地位向上を訴えた作品もあるので、そのようにとらえられているのかも知れない。
しかし、それらはまったく見当違いというほかにない。島崎藤村が「夜明け前で」描きたかったものは、そういったことではないと思う。明治維新を「日本の夜明け」であると考えている人は多いと思うが、少なくとも島崎藤村はそのように思ってはいなかった。日本はまだ「夜明けを迎えてはいない」と考えていたのだと思う。「夜明け前で」という表題が示しているとおり、我々は明治維新以後も、今日までも、いまだに夜明けを迎えてはいない、ということを言いたかったのではなかろうか。
|
維新と言い、日進月歩の時と言って、国学にとどまる平田門人ごときはあだかも旧習を脱せざるもののように見なさるるのもやむを得なかった。ただ半蔵としては、たといこの過渡時代がどれほど長く続くとも、これまで大和言葉(やまとことば)のために戦って来た国学諸先輩の骨折りがこのまま水泡に帰するとは彼には考えられもしなかった。いつか先の方には再び国学の役に立つ時が来ると信じないかぎり、彼なぞの立つ瀬はなかったのであった。
|
「夜明け前」のほぼ最後に当たる文章は次のように記されている。
|
その時になって見ると、旧庄屋として、また旧本陣問屋としての半蔵が生涯もすべて後方(うしろ)になった。すべて、すべて後方になった。ひとり彼の生涯が終わりを告げたばかりでなく、維新以来の明治の舞台もその十九年あたりまでを一つの過渡期として大きく回りかけていた。人々は進歩をはらんだ昨日の保守に疲れ、保守をはらんだ昨日の進歩にも疲れた。新しい日本を求める心はようやく多くの若者の胸にきざして来たが、しかし封建時代を葬ることばかりを知って、まだまことの維新の成就する日を望むこともできないような不幸な薄暗さがあたりを支配していた。・・・・
|
1935年(昭和10年)10月、藤村が63歳のとき、「夜朋け前」は完結したが、藤村は、続編となる「東方の門」で、再びこのテーマを追求する。それは、「新しい日本」を求め、「まことの維新」の成就とは如何なるものかを求めた小説になるはずであったと思われる。主人公は青山半蔵が放火しようとした万福寺の住職、松雲。物語はその松雲が青山半蔵の行動の真意を探らんとする思索小説の形で進んで行く。その、冒頭の文章は次の通りである。
|
東方の門 序の章
古い伝説によると、かつて日の光は天の岩戸に隠れてしまつたことがあつた。この世は全く長い夜の連続であつた。そこへ思慮の深い神が来た。この神はやがて日の出の遠くないことを感づいて、夜明けを告げるために沢山な鶏を集めた。常世(とこよ)の長鳴鳥(ながなきどり)といふものの声が闇の空を破つて遠くにも近くにも起こつたが、そこいらはまだ暗かつた。そこへ今度は逞しい力の神が来た。いかな力の神でも、堅く閉じた岩戸をこじあけることは叶はない。そこには、鍛冶に造らせた真鐵(まがね)の鏡を持ち寄つて暗黒を照らそうとした神もある。玉造りに造らせた曇りなき玉のひかりを持寄つた神もある。枝葉の茂つた常磐木(ときわぎ)をそこへ運んで来て、一切の穢汚(きたな)いもの、あさましいものを払いきよめるために、青い布や白にい布をその枝にかけた神もある。あるひは樺の皮を用ゐて占ト(うらなひ)に余念もなかつた神まである。これだけの神が集まつても、天の岩戸に隠れた太陽神をどうすることも出来なかつた。最後に、そこへ面白い恰好をした女神が来た。この女神は日蔭(ひかげ)の葛(かづら)を襷(たすき)にかけ、正木(まさき)葛(かづら)の鉢巻をして、笹の葉を手に持ち、足拍子をかしく踊り出すといふ滑稽さであつた。のみならず、神が人間に乗り移つた時のやうな姿をして、恥づかしい乳をあらはして見せ、腰から下には裳の紐をぶらさげた、それ見てどつと笑はない神々はなかつた。さすがの堅い岩戸が細目に開けたのはその時であつた。力の神はここぞしとばかり、太陽神が岩戸からやや御姿をあらはしかけた時に、その手を執つて引き出しまいらせることが出来たといふ。そこから日の光もあらはれ、大地も微笑み、神も人と交はつた。
この古い伝説は長く人の口に語り継がれ、神楽の舞ともなり囃子ともなつてしばしば民衆の面前に演ぜられて来た。おそらくこの国土に生を亨けたほどのもので、互いの大きな母であり希望の拠つて立つ大地でもあるところに永久に日の光の輝き満ちることを願はないものはなかろう。しかし歴史の推移(おしうつり)が語る激しさは、ややもすれば多くのものの希望をうち砕くやうにした。この古い伝説が教えるやうに、光は顕はれもし、また隠れもしたからであつた。堅く閉じた岩戸の前に立つ神々のやうにして、世の行く末を思ひわづらふ人達もいろいろとこの国に生まれた来た。あるものは深い思慮を持ち寄り、あるものは逞しい力を持ち寄り、あるものは鏡のごとき眞(まこと)の明るさを、あるものは珠のごとき徳を、あるものは浄化を、あるものは予言をといふ風に。浅い滑稽から出発しながら、それを言葉にやはらげもし、深めもするため、一生心を労しつづけたやうなものもある。
そこにはまた、日の出の遠くないことに感づいて、それを告げにこの世に生まれて来たやうなものもある。そういう先達のなかには、遠く海を渡って来て、異邦人としては眞にこの国民を知り愛しまた導きもしたといふべき希な人すら見出さるる。・・・
|
文学者が描いた古事記の天の岩戸開きの一節はかくのごとく美しい文章で綴られている。こうして1943年(昭和18年)1月「東方の門」は「中央公論」で連載が始まったが、第三章で絶筆となった。その年の8月22日、藤村は71歳で脳梗塞のため永眠する。その時から今日まで、およそ60年間、明治維新から数えると136年間、日の光は未だに失われたままである。そして、闇はますます深くなっていくばかりのようだ。われわれは夜明けの光を再び見ることができるのだろうか。
2003.5.6
戻る トップ 次へ