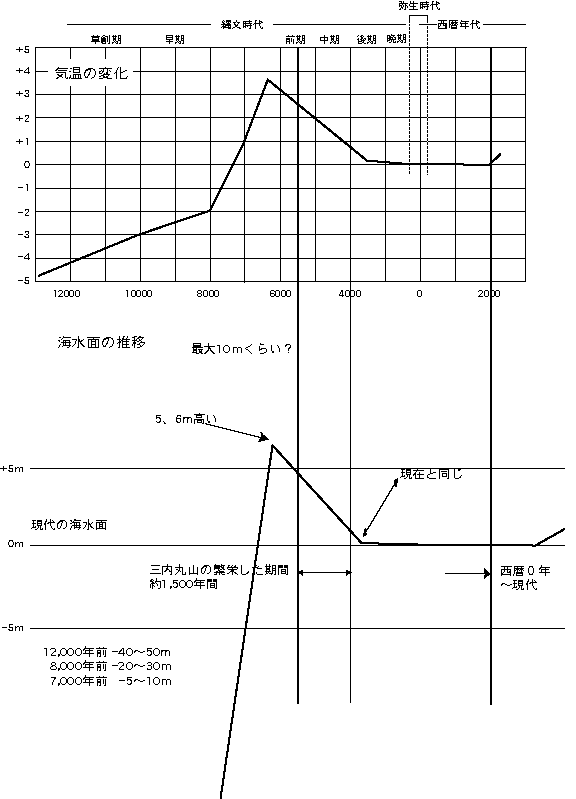
SF的東洋医学起源論
アーユルヴェーダや漢方の起源について考えていると、不思議に思うことがあります。それは最初から完全な形でわれわれの前へ現れてくることです。
漢方の世界で古典派と言われる人達がいます。古いものほど完全で真実に近いと考える人達です。例えば、漢方で治療する場合、最新の医学的成果より、過去の文献を大事にして、廣帝(漢方の祖)はこうした症状の時は、どう考えたか、どう治療したのか、ということに思いをはせて、古い時代の治療の姿をもとめて、現代の治療に応用しようとしています。
これは、今日の、われわれの常識から考えると不思議です。常識では、古いものほど不完全で、新しいものほど完全に近くなるはずだからです。進化論がそれを証明しているし、進化とはそういうことでしょう。したがって5,000年前のアーユルヴェーダや3,000年前の漢方は、古い時代ほど不完全で、時代をへるにしたがって完成され、理想に近くなっていかなければならないのに、実情はその逆で、時代を経るにしたがって、完全な姿が失われ、理想の姿から遠ざかっているようにみえるのです。しかし、この逆行現象はアーユルヴェーダや漢方に限ったことではありません。
大河のほとりに、4大文明といわれる、メソポタミア文明・エジプト文明・インダス文明・黄河文明が栄えました。これらの古代の4つの巨大都市文明は5,000年前(紀元前3,000年)に、ほぼ同時に出現したのですが、おかしな事に、この文明には、前期(プレ)と呼ばれるものがないのです。我々が、貧弱な家を建てるときにでも、3度くらい建て変えて満足するものが出来ると言われるのに、あれだけの規模の都市を造るのですから、何度か作り替え、試行錯誤をくりかえした跡があっても良さそうなのに、4大文明には、そうした造りかえ、改良した跡がみられずに、時の流れの中に、突如として、完全な形で出現してくるのです。
例えば、エジプト文明は5,000年前ごろ、宗教体系・絵文字・医学・哲学・天文学・文学などの体系を完成した姿で出現してくるのですが、完成前の発展してきた過程の遺跡や遺物が見つかっていないのです。こんなおかしなことがあるでしょうか。2億4千年前〜6,500万年前に生息した恐竜の「うんち」の化石まで見つけている時代に、わずか5,000年前の遺跡や遺物が見つからないはずはないでしょう。
また、前のコメントでものべましたが、古事記の島が、私の言うように太陽系の惑星や衛星であったならば、望遠鏡や観測衛星など持てるはずもない古代人が、なぜ、惑星の衛星の位置や数や特徴を知ることが出来たのかでしょうか。こんなことを考えていると「一体、俺達の歴史はどうなっているのだ」と思ってしまうのです。このような進化論に逆行する現象をわれわれはどうとらえれば良いのでしょうか。
グラハム・ハンコックは『神々の指紋』の中で、今から1万年前くらいに、近代文明よりも高度な科学・技術をもっていた未知の文明が存在した、と言っています。これは面白い指摘です。私たちは、現代文明が人類の文明の最高峰だと思い込み、古代人を未開人と思い込んでいますが、そうした考え方に一石を投じた考え方として、高く評価していいように思います。
ただ、難点は、彼も同書で書いていますが、高度な文明が存在していたのなら、何十万人もの文明化された人々がいたはずで、その遺跡が数多く発見されていなければならないのに、それが、物質的痕跡もほとんど残さず消え失せ、さらには住んでいた土地自体も消え失せたということになると、そのようなことはどう考えても考えられない、ということです。この理由のためにハンコックの助手は彼のもとを去ってしまいました。
私も、まったくそのとおりだと思います。現代より高度な科学・技術文明があったのならば、必ずその痕跡は見つかるはずです。例えば、我々の文明が、何らかの理由である日、突如として滅んでしまっても、1万年後に、ジャンボジェットや、原子力潜水艦、核爆弾や、高層ビルの残骸、車や、洗濯機や冷蔵庫、パソコンなど、我々が存在し生活していた残骸はいくらでも発見できるはずでしょう。なのに、彼のいう1万年前に存在したと考えられる高度な科学・技術文明の遺物は皆無というほど発見されてはいないのです。
現代の技術でも加工が難しいといわれる水晶のどくろや、氷のない南極大陸の正確な地図(ピリ・レイス地図)などの、オーパーツ(OUT OF PLACE ARTIFACTS≒本来そこにあるはずのない場違いな出土品)があるではないか、というかもしれません。でも、そんな物が、数点、見つかったからといって、高度な文明が存在したという証明にはならないでしょう。
ピリ・レイス地図を例にとれば、南極大陸の海岸線を描くことができるということは、南極が氷に覆われていなかったことになります。その場合、南極と北極の氷が全部溶けている必要がありますが、氷が全部溶けたとなると、海水面は100メートルほど上昇するそうです。そうすると、現在の地形から推測される南極のすがたより、その海岸線はもっと内陸に入りこんでいなければなりません。大陸の面積ももっと小さくなっているはずです。形もだいぶ違っていることでしょう。ハンコックは、南極に氷がなかった時、すなわち、海面が今より100メートル上昇していた時に描かれたと思われるピリ・レイス地図と現在の南極大陸の形が同じ、というのですから矛盾が出てきてしまいます。
それで、ハンコックは南極大陸は、ポールシフト(極移動)によって、3,200キロ移動した、という仮説を述べています。だから、古代の高度な科学技術の遺跡や遺物は、現代の南極大陸の、厚さ3キロの氷の下にある。そこを探れば発見できるというのです。なるほどと、頭から否定はしませんが、ちょっと無理な感じもしないではありません。
では、ハンコックの言うように高度に発達した文明は存在しなかったのでしょうか。いや、彼のいうような、高度な科学・技術文明はありませんでしたが、別の意味で、高度な文明は存在していたと思います。さて、これから核心の部分に入ってゆきますが、そこで登場するのが「ドラえもん、のび太の魔界大冒険」です。ここに、古代に高度な文明が存在していたと考えられる、カギがあるのです。
毎日、勉強ができずに怒られてばかりののび太は、この世界がいやになり、ドラエもんに泣きつきます。そこで、ドラエもんは、例によって「もしもボックス」をポケットから取り出します。それは、一見すると公衆電話ボックスのようですが、そこで「もしも、・・・・だったら」と話すと、その言ったことが実現してしまうのです。のび太は、「もしも、この世界が科学に支配された世界ではなく、魔法に支配された世界だったら」と話します。しかし、外に何も変わった様子はみられません。ガッカリして寝てしまいますが、朝起きて、窓の外を見てビックリ。お父さん達はマイカーや電車で通勤しているのではなく、みんな、空飛ぶ絨毯にのって出勤していたのです。空は、お父さんの乗る空飛ぶ絨毯のラッシュアワー・・・。
この物語のおもしろさは「魔法」と「科学」の対立を、パラダイム(ものを考える枠組み)の違いとしてとらえたところにあります。現代は、パラダイムとして「科学」の方を採用しましたが、それだけが唯一の世界ではありません。魔法も決して迷信ではなく、立派な考え方として通用し、パラダイムを変えれば「魔法」に基づく世界も考えられる、といっているところがおもしろいのです。ですから、たかが漫画とあなどってはいけません。「科学世界」対「魔法世界」という「パラレルワールド」の概念を巧みに取り入れた本格的SF張りの物語になっているのです。どらえもん長編シリーズの中でも最高傑作といわれる所以です。
この「もしも、・・・・だったら」という考え方はすこぶる面白いのですが、「マンガじゃなー」という方の為に、アーサー・C・クラークのSF小説「銀河帝国の崩壊」と「都市と星」ではどうでしょうか。
・銀河帝国の崩壊(Against the Fall of Night
) 井上勇訳 ・ 創元推理文庫。
・都市と星 (The city and the
stars) 山高昭訳 ・ ハヤカワ文庫SF
アーサー・C・クラークを知らない方には、不朽の名作といわれる映画「2001年宇宙の旅」の原作、脚本、科学アドバイザーといったら、少しわかっていただけるでしょうか。この作品はクラークの『卓越して科学的な目と、天才的な想像力がなければ完成されなかった(NHK夢伝説より)』といわれています。
アーサー・C・クラークは作家だけでなく、優れた科学者でもあります。現在、通信衛星はクラークが考案した軌道で地球の周りをっていますが(クラーク軌道)、それは、1945年、通信衛星を電波の中継点にする構想を発表した、クラークの論文が元になっています。クラークは、この通信衛星が情報化社会の主役になるとも予言しています。たしかに、これにより世界は大きく様変わりしました。
「国連、NASAが絶大な信頼をよせる、人類の未来に思いをはせる現代の予言者」ともいわれ、およそ60年も前に、通信衛星の構想、人工知能、テレビ電話、電子メール、スペースシャトル、生物のクローン化、パソコンの出現を予言しているのですから驚きです。『全てのSFは予言の性格を持ちますが、クラークのは当たる確率が高い、といわれていて、『宇宙飛行士や科学者はクラークが言うから、これは本当になる』と考えているそうです。
BIS=British Interplanetary
Society (イギリス惑星間飛行協会)の会長を二期務め
RAS=Royal Astronomical Society (王立天文学協会)の会員です。
その、クラークが「銀河帝国の崩壊」と「都市と星」を書きました。注目すべきことは、この2作品の主人公とテーマが同なのです。一人の作家が、同じテーマで、二つの作品を書くのは、異例中の異例と言えますが、クラークは、このテーマによほど執着をもっていたといえるでしょう。
1937年『銀河帝国の崩壌』執筆開始。
1946年『銀河帝国の崩壌』脱稿。
1953年『銀河帝国の崩壌』出版。
1955年『都市と星』脱稿。
上記ように、10年近い年月をかけて『銀河帝国の崩壊』を完成させたのに、脱稿から9年後には全面改稿されて『都市と星』ができています。長篇の全面改稿もさることながら、最終的な完成が想を得てから20年あまりという点に、クラークのこの作品に対する執着ぶりがうかがえます。『20年間、頭を離れなかったテーマというのは、20歳から40歳近くまで、人生の最も充実した期間を占めた、文字通りライフワークであることが明確になる(堀晃)』
改稿された理由は何かというと、『この物語を思いついて以来20年間におこった科学の進歩のため、当初の考えの多くは幼稚なものとなり、この本が初めに計画された頃には思いもよらたかった展望と可能性が開げてきた。』とクラークはのべていますが、科学技術の進歩がすさまじいため、その進歩に合わせて、物語に現実感を与えるために書き直したのでしょう。しかし、クラークがこの二つの作品を通して述べたかった根本のテーマはただ一つなのです。
舞台は10億年後の未来の地球(SF小説の中でも最長の遠未来です)。海は干上がり、山は風化され摩滅し、砂漠だけが広がる世界。その、荒涼たる世界の中に、
|
その都市は、輝く宝石のように砂漠の懐に抱かれていた。かつては、そこにも変化や移り変りがあったが、今ではそこは時の流れと無関係だった。夜や昼が砂漠の上を通りすぎていったが、ダイアスパーの通りにはいつも午後の日射しがあり、夜の帳りがおりることはなかった。長い冬の夜、砂漢では、地球の希薄な大気にわずかに残った湿気が凝結して、挨のように霜をおくこともあった。だが、この都市には暑さも寒さもなかった。そこは外界と何の接触もなく、それ自身が一つの宇宙だったのである。 人類はそれ以前にも数多の都市を建設したが、この都市のようなものは前例がなかった。都市の中のあるものは数世紀、あるものは数千年も続いたが、いずれは時のうつろいと共に、その名さえ忘れられていった。ここダイアスパーだけが永劫の時に抗して、都市やその中の一切のものが、歳月とともに徐々に摩耗し、朽ち果て、錆におかされることから守ってきた。 この都市が建設されて以来、地球の海は消減し、全世界を砂漢が取りまくようになった。山々は一つ残らず風雨にすりへらされて塵と化し、衰え果てた地球にはそれらを新たに生みだす力はなかった。この都市には、それも関係のないことだった。たとえ地球そのものが崩れさろうとも、ダイアスパーは、その建設者たちの子孫や財宝を、時の流れの中で無事に守りぬくことことだろう。 ・・・・こういう黄金時代を夢みたものは多かったが、それを達成しえたのは彼らだけだったのである。10億年をこえる歳月が過ぎてゆく間、彼らは同じ都市に住み、奇蹟のように変わることのない同じ通りを歩いてきたのだった。(都市と星より) |
このように、物語は砂漠の中の不減の都市ダイアスバーの描写からはじまりますが、この都市の中では、人類は、コンピュータとリンクし、生老病死を克服し、物質を意志の力一つで自由自在に、まるで魔法使いのように、取り出し、消減させ、再び再生させています。人間とともに、物質も摩滅することなく永遠の存在となっています。いかに地球の環境が激変しようとも、そこには『永遠の午後の日射しがふりそそいでいる』というように、人類が夢に見、理想とした生活が営まれているのです。
|
その部屋は真暗で、一方の壁だけが光っており、アルヴィンがしきりに空想をこらすのにつれて、その上にはさまざまな色彩が潮のように現われては消えていった。その模様の一部は彼の気に入った。海から抜け出て聳え立つ山々の線に、彼は夢中になった。・・・ 「全部抹消」と、彼は機械に命じた。海の青が消えていった。山々は霞のように消え、あとには白い壁だけが残った。まるで、初めから何もなかったようだった。まるで、それらは、アルヴィンの生まれるよりずっと昔に地球の海や山が忘却の彼方へ消えていったように、見えなくなっていった。部屋には再び光があふれ、アルヴィンが今まで夢想を投影していた明るい四角形は、その周囲と区別がつかなくなり、まわりの壁と一つになった。しかし、いったいこれは壁なのだろうか?。 こんな場所を今まで見たことのないものには、これは全く妙な部屋だった。そこは完全にのっぺりしていて、家具は一切なかったから、アルヴィンはまるで球の中心に立っているように見えた。壁と床や天井との間には、両者を分ける線は何も見えなかった。眼を据えることのできるようなものは何もなく、視覚から判断するかぎりでは、アルヴィンを囲む空間は、さしわたし十フィートかもしれないし、十マイルかもしれなかった。 手をさしのべて進んでゆき、このとんでもない場所の物理的な境を突きとめようとする誘惑は禁じがたいことだろう。けれども、歴史の大部分を通して、こういう部屋が人類の多くにとっての〈住み家〉だったのである。アルヴィンが単に適当な思念をこらしさえすれば、壁は都市の好きな場所に向かって開く窓になった。別の願望をこらすと、彼が見たこともない何かの機械が働いて、彼に必要などんな家具でも、この部屋に投影してくるのだった。それが〃実在〃するのか、そうでないのかなどということを気にするものは、この10億年というもの、ほとんどいなかった。いわゆる確かな物体というのが、やはり別の見せかけにすぎないのにくらべれば、これらがわずかでも実在しないとはいえないのである。 また、用がなくなれば、これらは都市の〈記憶バソク〉という幻の世界に返してしまえるのだ。ダイヤスパーのあらゆるものがそうであるように、これらも絶対に摩耗せず、記憶されているそのパターンを人為的に消してしまわないかぎりは、決して変わることもないだろう。 |
次のダイアスパーの交通網の描写です。
|
彼女は、高速自動走路が二人を混雑する都市の中心から運び去ってゆく間、・・・彼らはいっしょに走路の中央の高速帯の方へ移動していったが、足もとの奇跳には眼もくれようとしなかった。古代杜会の技術者ならば、一見したところ固体の走路が両側が固定しているのに、どうして中央にゆくに従って次第に速度が増すのかを理解しようとして、だんだん頭がおかしくなることだろう。しかし、アルヴインやアリストラにとっては、一方向には固体であり、他方向には液体であるような性質を持った物質があるということは、全く当然のことのように思えたのである。 |
ダイアスパーこそ、人類が科学技術の粋を集めて完成させた不滅の都市なのです。この永遠の都市に、人並みはずれた好奇心の強い性格を持たされて、アルヴィンという、一人の若者が、遺伝子バンクの中から誕生します。彼は、ダイアスパーの外には何があるのか、かっては銀河の中心にまで進出した人類が、なぜこの都市だけに住み、満足しているのか、といったダイアスパーの住人なら誰も感心を払わないことに疑問をいだきます。そこで、都市に仕掛けられた様々なナゾを解き明かし、かっては人類が、様々な都市をつなぎ、星々に進出した交通網の拠点となった場所を発見します。すると、そこには、まだ一つだけ、ダイアスパー以外にも、この地球で、10億年の歳月を生き抜いてきた都市があることを発見するのです。その都市の名はリス。その都市は、ダイアスパーが科学技術の力を極限まで発達させて生き残った方法とは全く違った方法により、永遠に等しい歳月を生き抜いて来たのです。
|
その洞穴からの出口を探しながら、アルヴィンは、自分のいまいる文明が、彼自身のものとは違ったものかもしれないことを示す最初の徴しを発見した。地上への道は、明らかに洞穴の一端にある低い広々としたトンネルの中を通っているのだが、そのトンネルを抜けて、上に向かっているのは、一すじの階段だった。こういうものは、ダイアスパーではきわめてまれだった。・・・その階段はごく短くて、つきあたりには扉があった・・・。 初め彼は、自分がその存在を当然としダイアスパーの全生活の基礎をなしている動力や機械のことを、リスの人々が忘れてしまったのか、それとも初めから持ったことがなかったのかしらと考えた。ほどなく、そうではないということがわかった。道具や知識はあるのだが、必要不可欠の時しか使わないのだった。その最もいちじるしい例は、輸送機関だった−−これを、そんなたいそうな呼び方をしていいのならだが。−−皆は、近くへ行く時は歩き、しかもそれを楽しんでいるようだった。急ぎの時や、ちょっとした荷物を運ばねばならない時には、明らかにこの目的のために改良された動物がつかわれた。 |
というように、交通輸送は全く対照的なのです。さらに、学習の方法にも、テレパシーのようなものが使われます。
|
「あなたが質間したいことは、わかっています」と彼女はいった。「・・・それを言葉でいうのはたいへんな仕事になるでしょう。もし私に心を開いてくださるなら、あなたが知りたがっていることを、お話しましょう。心配しなくてもいいのよ。断わりなしに、あなたの心から何も盗みはしませんから」。 「どうすればいいんですか?」アルヴィンは、用心深くいった。「私の助けを受けいれるようにしてください。私の眼を見て、それから、何もかも忘れなさい」と、セラニスは命じた それからおこったことは、アウビィンにはよくわからなかた。彼はあらゆる感覚をすっかり失っていた。何かを受けとった覚えは全くたかったのだが、自分の心の中を覗きこんでみると、知識はもうそこに入っていたのだった。彼は過去をふりかえっていた。それは、はっきりとではなくて、どこかの高い山にのぼって霞んだ平野を見渡したような感じだった。 人類は初めから都市に住んでいたのではないこと、また機械によって労働から解放されて以来、二つの型の文明が絶えず対抗しあっていたことを、彼は知ったのだった。・・・ |
ここで、アルヴィンは「科学の力」ではなく、もう一つの力があることを思い知らされます。「精神の力」です。
|
リスは、初めの頃から、他の何百とあった共同体とは少し違っていたのであるが、長い年代の間に、次第に独自の文化を発展させ、それは人類に知られた最高の文化の一つになった。それは、精神の力を直接利用することに主たる基礎をおいた文化であり、このために、ますます機械に依存するようになった他の人類杜会と区別されていた。長い長い年代の間、彼らが違った道を進んでいるうちに、リスと都市との間の溝は拡がっていった。 |
長々と引用してきましたが(いつものことですが)、『都市と星』はクラークの80余の作品中、『幼年期の終わり』とともに、最高傑作といわれていますが、ここで彼は、文明には二つのタイプがあることを予言しているのです。つまり「科学の力」を発展させることにより繁栄した文明と「精神の力」を発展させることにより繁栄することのできる文明です。
NHKの番組、夢伝説「アーサー・C・クラーク」の中で、アルビン・トフラーは『SFはわれわれ人間に様々な選択肢が存在することを教えてくれます。そこには、現在の生活様式だけが唯一可能な生き方ではないという、重要なメッセージがあるのです』といっています。その言葉を借りれば、「科学の力」にもとづく生活様式が、唯一可能な生き方ではなく、「精神の力」による生活様式も、また一つ生き方として充分に考えられる、ということが言えるでしょう。
これで、私が何を言いたいのかお解りでしょう。ハンコックの言うような、現代より高度な科学・技術文明は存在しなかったと思いますが、別の意味で、高度な文明、そうです「精神の力」を発達させた文明が、今から1万年くらい前に存在していたのではないか、ということが言いたいのです。「科学」ではなく、「精神」を発達させた文明です。
「精神」を発達させた文明。それは、どんな文明になるでしょうか。どんな特徴をもつのでしょうか。それには精神の力とは何かがわからなければなりません。そこで、ヨーガの教典、パタンジャリのヨーガ・スートラに書かれている、精神の力を開花させた時に生じる力をリストアップしてみました。
・あらゆる生き物の叫びの声の意味がわかる (解説:ヨーガ・スートラ 佐保田鶴治 平河出版社より)
・前世がわかる
・他人の心を知ることができる
・体を誰にも見えなくさせることができる
・死期を知ることができる
・慈などの情操に綜制(サンリャマ)を向けることによって、種々の力を発揮することができる。
・象などの力に綜制(サンリャマ)を向けると、それらの力に等しい力があらわれる
・微細なもの、隠されているもの、はるか遠くにあるものでも知ることができる
・宇宙を知る力があらわれる
・星の配置を知ることができる
・星の運行を知ることができる
・体内の組織を知ることができる
・飢えと乾きを消すことができる
・堅忍(しんぼう強く、がまんする)性が得られる
・神霊をみることができる
・すべてを知ることができる
・心を意識することができる
・身我の智を現ずることができる
・超自然的な聴覚、触覚、視覚、味覚、嗅覚が生ずる
・心は他人の身体のなかへ入りこむことができる
・水、泥、刺(トゲ)などにわずらわされず、また容易にそこから脱出できる
・身体から火焔を発することができる
・神霊の声、微細な声、ささやき声、遠方の声でも、一度に聴くことができる
・空を歩くことができる
・魂を身体から遊離させることができる
・五つの物質元素(地水火風空)を克服することができる
・五つの物質元素の克服により、身体の縮小などの自在力があらわれ、肉体が完全になり、なにものにも破壊されなくなる。
・肉体の完全さとは、端麗、優雅、強力、金剛不壊の強靱さをいう
・世界の根元を支配する力があらわれる
・分析から生ずる知があらわれる
・同一に見える二つのものも、的確に見分けられる
・一度に一切を知ることができる
・覚のサットヴァと真我の清浄さが等しくなった時、真我独存の境地があらわれる
・このような秀れた霊能に対してさえも喜びの心を抱かなくなった時に、すべての悪の根が絶たれて、真我独存が顕現する
すごいですね。このようなことは、現代の文明では荒唐無稽とされて、省みられませんが、われわれは脳の機能の5%くらいしか使っておらず、残り95%は使っていないといわれているのですから、脳の機能を100%開花させた時には、上記のような力を持つことができるのではないでしょうか。私はヨーガ・スートラが全くのでたらめを書いているのは思えないのです。すくなくとも、頭から疑ってかからず、その可能性について、もっと積極的に研究する必要があるでしょう。
そして、上記のような力を持った人達が多くいる社会とは、どんな社会になるでしょうか。少なくとも、我々のように、これが欲しい、あれがなければダメだ、などと物欲に凝り固まってはいなかったことでしょう。
清貧を旨とするヨガの行者が、キンキラキンの宝石を身につけるでしょうか。「起きて半畳、寝て一畳」と満足している、悟りを開いたお坊さんが豪邸を欲しがるでしょうか。かすみを食べている仙人が豪華なごちそうを食べたがるでしょうか。というような、冗談はさておき、精神を発達させた人々の、物に対する欲望は、われわれより、かなり希薄であったと思われます。そこで、そのようなベースを持った文化は、現代の文化と比べ、ずいぶんに違ったものになっていることは容易に推測できるでしょう。
いずれにせよ「精神の文明」という観点から、過去の歴史を洗い直して見る必要があるでしょう。このような観点から見ると、石器時代といえども、なかなかどうして、かなり満ち足りた豊かな生活をおくっていて、ことによると現代人よりも幸せに暮らしていたのではないか、ということをうかがい知ることができるのです。
1992年(平成4年) 青森市の南西3キロの県営野球場建設地から、驚くべき巨大遺跡が発見されました。三内丸山遺跡とよばれていますが、それは縄文時代の常識、すなわち、定住もせずに、狩りをし、貝や木の実を採集して、原始的な生活を送っていた、という認識を次々とくつがえし、世界中に大きな衝撃を与えました。その、三内丸山遺跡には3つの大きな特徴があります。
●大きい
その、第1は「大きい」こと。遺跡の規模は、約35ヘクタール(約10万坪)の丘陵にひろがっていて、中心地の6ヘクタール(約1万8千坪、平均直径6〜700m)の巨大な円形状の土地には、中央を貫通する幅12mの道路や、幅7mの道路などがあり、約100棟の掘立柱建物、約480棟の竪穴住居が、整然と配置されていました。最大の大型掘立建物は、6本の柱をもち、正確に南北、東西に配置され、柱穴の間隔もぴったり4.2mか2.8mと1.4の倍数(35センチ単位の縄文尺)、内転び角度約2度(高くそびえても安定度抜群)。 一本の柱の直径は、80cm、吉野ケ里遺跡(佐賀県・弥生時代)の物見やぐらを超える高さ20m、重さは約15トン(日本最古の灯台との説もある)。ゴミ捨て場などが計画的に配置され、その計画性と巨大性から「縄文都市」と言われます。このようなことから大規模な土木工事を可能にした優れた知恵があったといわれています。
●長い
第2の特徴は「長い」こと。(遺跡の継続期間:約5500年前から1500年間)。縄文人はこの地に1,500年もの間、定住し、優れた土木造成技術で計画的な都市を形成し、縄文文明を維持していました。各地方をつなぐ、交流センターとしての役割があったようで、三内丸山には、新潟県糸魚川のヒスイ(勾玉などに加工)、北海道十勝地方の黒曜石(矢じりなどに加工)、秋田産のアスファルト(石鏃などの接着、接合に使われる)、遠くシベリアの大地からは朱泥(ウルシ器や柱などを赤く塗るため)などなど、多くのものが運び込まれ、加工され、土器などとともに他地域へ送り出されていました。海上交通による遠距離からの、広範囲にわたる流通が行われていたようです。
●多い
第3の特徴は、「多い」ことです。おびただしい数の遺物が発掘され、その総数は、過去、日本中の遺跡から発掘された遺物の総数を上回ります。その分類、整理に100年はかかるといわれています。その遺物から、縄文人の衣食住などの暮らしぶりはかなり豊かであったことがうかがい知れます。
・海の幸と山の幸
主食はクリ。クリの花粉量が自然分布状態に比較して多すぎることや、同一のDNAを持つことから、管理栽培をされていたことが明らかになりました。さらに、驚くべきことに、栽培しなければあるはずのない、ヒョウタンやマメ、エゴマ、ゴボウ、野生のヒエなどの種子なども見つかっているのです。稲作はまだないとしても、農業技術があったことがわかってきました。日本最古級の農耕ということになります。また、クルミ、ヤマクワ、サルナシ、ニワトコ、ヤマブドウ、キイチゴ出土していますが、特にニワトコ、ヤマブドウ、キイチゴなどは食料の他に酒などを造るためにも使われていたようです。
すぐそばの海からとれたと思われる、タイやヒラメ、アジ、イワシ・・など、50種類以上の魚介類をまんべんなく食してしたようです。われわれでも、なかなか50種は食べられないのですから、現代に住むわれわれ以上に海の幸の恩恵にあずかっていたと思われます。鯨の骨製の刀、エイのとげ製の縫い針なども見つかり、海に依存した生活をしていたとみられます。このようなことからかなり豊かな食生活を享受していたようです。
・ロクロとウルシの技術
ウルシ塗りの直径約25cm木製鉢は、ロクロを使って約5mmの厚さに真円に精巧に加工されていて、表面の朱色にはシベリヤ産の朱泥がつかわれ、それをウルシで塗っています。今までは、ロクロは弥生時代に確立された技術、ウルシは中国が原産地とされていましたから、そうした技術のルーツや起源にも見直しが迫られています。(残念ながら、北海道南茅部町大船の町埋蔵文化財調査団事務所が原因不明の火災で貴重な遺物数万点が一瞬にして灰になり、その中に世界最古とみられる約九千年前の漆製品も焼失してしまいました)
この三つ特徴の他に、平和で階級のない平等社会、共生と循環の社会であったことも、大きな特徴です。
●平和な平等社会■
集落のそばに平然と配列されたこれらの墓地は、全く大小の区別なく、巨大な建物や王や貴族の家などの区別もなく、副葬品もみな同様だったことから、王や奴隷などの階級差のない、平等な社会であったと見なされています。さらに、出土する人骨に、弥生時代のような、刀やヤリなどで殺された後が無いことから、縄文時代は戦争のない平和な社会だったようです。
●循環を壊さない生き方
貝塚は、ゴミ捨て場として認識されていましたが、三内丸山では、食用にされた、貝は丁寧に並べられて、盛り土をされていました。土器も同じように、盛り土されていました。このようなことから、単なるゴミ捨て場ではなく、霊を弔うお墓ではなかったのか、といわれています。『貝がふたたび豊かな身をつけて、この世に戻ってくるようにとの願いを込めて、貝の霊を丁重にあの世に送る場所だったようです。(国柄探訪:共生と循環の縄文文化:http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h12/jog134.html)』
ただ、これは三内丸山遺跡だけの特質ではなく、縄文の文化全体に渡る特質のようです。能登半島の真脇地方では、縄文人がイルカを常食としていました。真脇遺跡(約6,000年前)からは、大量のイルカの骨がみつかり、そのことから「イルカ漁を主な生業としていたムラではなかったかとも考えられています」。今日の常識から見れば、あんな頭の良い、かわいい動物を食べるなんて、と動物愛護協会は自然保護団体から、大目玉をむかれそうなことを、平気でやっていたようです。
でも、これは極めて自然なことなのだと私は思うのです。われわれはこの地上で生きてゆくためには、他の生物を命を殺め、それを食べなければ生けては生けません。この不条理がこの世に生きてゆくわれわれの宿命のようです。イルカも他の小魚を食べていかなければ生きてゆけないのですから、この世に生きる物すべては、この不条理な食物の連鎖から逃れるすべはないのです。
しかし、真脇遺跡からはもう一つ、不可解な出土品があります。それはインディアンのトーテムポールの様な彫刻を施した柱で、イルカの供養に使われたのであろうと推測されています。おそらく、彼等は命の糧としてイルカを食べながらも、死んで行くイルカに限りない感謝をこめていたに違いありません。そして、おそらく生きて行くのに必要なだけ、捕獲していたのではないでしょうか。
これこの、みたま、いただきます。
これこの、みたま、ごちそうさま。
この言葉は、近くの古八幡神社(大沢)に、初詣(2004年)に行って頂いた新しいお箸の袋に書かれていました。いつの頃からか、私たちの祖先は、食事の時、箸をすすめるたびに、一箸ごとに、「みたま」=魂を頂く、と思って食事をしていたようです。そして、犠牲になった動植物の魂に感謝をささげていたようです。何というやさしさ。お正月早々、感動しました。
すでに、書きましたが、「めぐみ」という言葉は「めぐる」という言葉から来ています。めぐ「る」から、めぐ「み」→「実」が与えられるのです。「恵み」「巡る」と漢字で書いたのでは、別の意味にとらえられてしまいますが、古代の日本語はこの関係を確かに知っていたのです。
この言葉が生まれたのは縄文の時代。最も古い神道の思想の中に言霊として残っていました。彼等は最も本質的なことを確かに知っていたのです。「めぐる」ことが、壊れないように、私たちも生きてゆかなければならいはずです。循環可能な社会とはそういうことでしょう。『縄文人の精神の根底には、すべてのものに生命が宿り、それがあの世とこの世を循環しているという世界観があった。(国柄探訪:共生と循環の縄文文化)』
三内丸山遺跡には、栽培農業、都市計画、物流システム、人の往来による情報網、現代よりも平和で平等な社会、循環に基調をおいたシステム等など、驚くべき高度な文化が存在していました。世界に4大文明が栄えていた頃、日本列島にも縄文文明と言っても良い高度な文明が栄えていたのです。4大文明は「石」を基調としていましたが、縄文の文明は「木を」基調にしていました。木は腐りやすいので、発見が遅れたと思われますが、発見されてみると、未開などとは、とても言うことのできない、むしろ現代のわれわれの生活に近い暮らしぶりだったのです。もしかすると、古代のうっそうとした豊かな森の中で、われわれ以上に豊かな生活を満喫していたのかも知れないのです。
さて、話を元に戻し、われわれは、土器や石器などの、粗末な道具しか持っていなかった文化を、縄文時代とか石器時代とよび、そうした文化を持つ社会を未開社会とよんでいますが、科学文明を発展させて、自らの首をしめて絶滅していこうとしている、われわれと比べ、どちらが文化的で、どちらが未開なのでしょうか。
地球村(http://www.chikyumura.org/)の代表、高木善之さんは、自らの臨死体験を通して、現代人は「モア&モア(もっともっと)」という教義の、「科学」という宗教と、「経済」という宗教にマインドコントロールされているといっています。
本当にそのとおりだと思います。毎日、毎日、これを買え、あれを買えと、洪水のように流されるマスメディアの広告は、洗脳とどう違うのでしょうか。その結果、われわれは「物がなければ、幸せに生きてはいけない」と思いこんで、せっせと物を買い続けます。これを、学者は大量消費社会などと呼んでいますが、これって資源を浪費し、強いては枯渇させてしまうような、罰当たりな社会ではないですか。
また、物にあふれる生活を文化生活と呼んでいますが、本当にこれが文化生活ですか。こんな生活をしていて幸せですか。お金お金と夜遅くまで、馬車馬のように働き、テレビやパソコンにより家族の団らんは無くなり、人と人の絆は希薄になり、大量消費を実現するために、資源を乱獲し、環境を汚染し、他の生物を絶滅に追いやり、そのために自らの絶滅を目前に控えているわれわれは、はたして幸せなのでしょうか。
ハンコックは古代に高度な科学技術をもつ文明を求めましたが、高度な文明とは科学技術に裏打ちされなくても存在し得ると思います。クラークのいうように『精神の力を直接利用することに主たる基礎をおいた文化』とは縄文時代(世界的規模では新石器時代)の文化ではないでしょうか。精神を発達させた人々にとって、石器や土器しかなく、今日の我々からみると、考えられないような粗末な道具でも、効率や生産性を重要視しない文化ならば、さほど不便を感ずることなく、充分に満ち足りた生活をしていたのではないでしょうか。あるいは、クラークの小説のリスの住人のように、粗末な道具を使う、その不便さを楽しんでいたのかもしれません。ことによると、道具を進化させることの危険性を、精神を発達させた結果得られる予知能力により、あらかじめわかっていたから、科学技術を発達させる道を選ばなかったのかもしれません。
石器や土器が主体となっている文化でも、『精神の力を直接利用することに主たる基礎をおいた文化』ならば、そのような文明からは、科学技術の痕跡が出てこないのは当然のことです。科学技術など、初めから無かったのですから。そして、石器や土器が出土しても、未開なもとして、無視してしまいますから、高度な文明の痕跡はすでに出てきているのに「ナイ、ナイ」と見当違いな方向を探し続けていいることになるのです。これでは、いつまでたっても見つかるはずはないのです。しかし、視点さえかえれば、それは、われわれのまわりにゴロゴロ転がっているのです。
例えば、3万年前の、スペインのアルタミーラやフランスのラスコーの洞窟壁画は、世界最古の壁画として有名ですが、その鍾乳洞の中で、一切の明かりを消して、真の闇を実現したとき、自分と他の物との接点が曖昧になり、瞑想状態に容易に入ることができるのではないでしょうか。現代で行われている感覚を遮断するタンクに入って変成意識状態になることと同じことです。
文字がないから野蛮で未開?。ことによると精神を発達させ、脳の機能を100%開花させた古代人は、脳をハードディスク代わりにして、モニター不要で、眼前に情報を読み出すことができる、完全なペーパレス社会を実現していたから必要なかったのではないでしょうか。空海は「虚空蔵菩薩求聞持法」により、一度見た教典を諳(そら)んずることができたといわれますし、現代でも、試験前にザッと教科書に目を通すだけで、教科書の文字が目の前に現れて来るので、難なく試験をパスをしたという人がいます。
ついでに、テレパシー能力があれば、現在われわれがインターネットを通してやっているようなこともできたのではないでしょうか。クラークの「都市と星」でも、道に迷った時に、主人公たちが、そうした能力を使って切り抜ける場面があります。
|
「思い出した」彼はやや弁解するようにいった。「・・・方角はあまり確かじゃないけれど、あれはシャルミレインに違いないよ」 「シャルミレインは、あの方角だ」彼は自信ありげにいった。アルヴィンは、彼がどうして知ったのかを訊ねはしなかった。彼は、ヒルヴァーの心が何マイルも彼方の友人と短時間の接触を行い、必要な情報が声もなく送ってよこされたのだと察した。 都市と星より |
おそらく、このような文明のもとから、アーユルベーダーや漢方が生まれたのだとおもいます(やっと本題)。ヨーガスートラの「体内の組織を知る」能力を使えば造作ないことだったでしょうから。古事記の島が太陽系の惑星や衛星であることも、「星の配置や運行を知り、宇宙を知る力」があれば、できないことではないでしょう。
これ私と同じ瞑想のTMシディーを実習している仲間に聞いた話ですが、探査衛星のボイジャが1979年、木星に近づき、1日後にその映像がおくられてくることが話題になっていた時に、彼は、瞑想の終了後に「木星はどんな姿をしているのだろう」と思いました。そうすると、脳裏に、輪のある星の姿が見えたそうです。てっきり彼は土星を見てしまったと思ったそうです。当時は、木星に輪が存在することなど知られていませんでしたから。「木星と思ったのに、なぜ土星になったのか」と不思議に思ったそうですが、後日、ボイジャーから送られた映像を見てびっくり。そこには、それまで知られていなかった輪が存在し、彼が見た映像と同じだったのです。これは、偶然、見えて、しまったのですが、精神が発達すれば、このようなことは日常的なことになっていたのでではないでしょうか。
現代の技術でも加工が難しといわれる水晶のどくろも、「五つの物質元素(地水火風空)を克服することができるの」ですから、動作なくできることでしょう。氷のない南極大陸の正確な地図もつくることも、「同一に見える二つのものも、的確に見分けられる」のですから、できないはずはありません。どうですか、このように考えると、新石器時代、あるいは縄文時代というのも高度な文明が発達した時代と言って良いのではないでしょうか。
|
悪しき見識の、千有餘年心の底に染著て、其他を思はざる世の人なれば、今かやうに申しても、誰も早速にはえ信ずまじき事なれども、惣じて異國風のこざかしき料簡は、よくおもへば、返て愚なることぞ、今一段高き所を考へて、まことの理は、思慮の及びがたきことにして、人の思ひ測るところとは、大に相違せる事のあるものぞといふことを、よくさとるべきなり (本居宣長) |
では、この高度な精神の文明は、なぜ継承されず滅び、変わりに科学・技術の文明が台頭してきたのでしょうか。その鍵は、時間です。そして、それには気温と稲作が関係してきます。
12,000〜10,000年前は、気温は今より2〜3°低く、海水面も現代の水位より40〜50mくらい低いといわれています(20,000年前は−100m)。7,000年前で−5〜10m。6,300年前には最温暖期を迎えたといわれています。三内丸山遺跡の栄えた頃の6,000〜5,000年前は、気温は今より2〜3度高く、海水面も5メートルくらい高かったようです。この後気温は下がりはじめ、弥生時代を迎えるころになると、ほぼ現在の気温と同じになったようです。これをグラフにすると次のようになります。
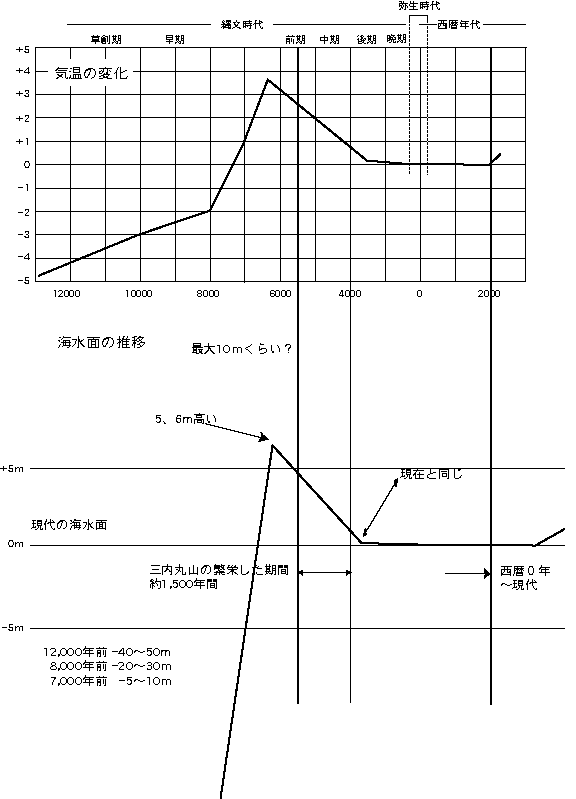
これは、かなりラフなグラフです。実際の海水面の変化などは、小海退や小海進がくり返されるので、このような直線のはずはなく、ゆらぎのある曲線になるはずなのですが、これでも傾向はわかってもらえるでしょう(詳しい資料がないのです)。海水面の変化は8,000年前より、急激に立ち上がるようになっていますが、これは、目盛りを5メートルにすると、1万年前は40メートルというのですから、その8倍になり、この範囲には収まりきれなかったからです。変動が大きいので対数のグラフにした方が良かったかも知れませんが、そうすると、急激な変化がとらえにくくなります。この方が海が急速な勢いでせり上がって来るのが良くわかると思います。
グラフが示すとおり、恐ろしいほどの変化ですが、しかし、4,000年以前の氷河期の寒冷化した気温の中で生活していた古代人の食生活に限っていえば、それは比較的、豊で安定的に供給されていたのではないでしょうか。その時期はマンモスなどの大型動物が食用になったでしょうし、天然の冷蔵庫があるのですから、貯蔵も容易だったでしょう。また、今より2、3度高くなったといわれている7,000〜4,000年の間は、暖かかったのですから南国に暮らす人と同じで、食料の確保に精を出す必要もなかったでしょう。人工の増加も今のように年率2%などという、暴力的なものでなく、20分の1の0.1%くらいでしたから、楽園のような状態だったのではないでしょうか。
しかし、その楽園を追い出される日がやってきました。4,000年前、気温が現在と同じになった時、三内丸山遺跡はうち捨てられました。私は物好きにも三内丸山遺跡の縁まで歩いてゆき、当時、そこから先は海であった、というところまで行ってみました。そこは、5、6メートルの高さの崖の上でした。2メートルくらい下には家々の屋根がみえていました。電信柱の上端はほぼ、目線の高さです。人々が三内丸山を捨てるとき、みえていた光景が想像されました。
4,000年よりすこし前から、三内丸山に間近に迫っていた海は、年を追おうごとに後退してゆき、ついには3キロも離れてしまったのです。変わりに現れたのは、それまで海底だった土地です。おそらく、葦の原が延々と続いていたことでしょう。これでは、海を利用した交易も廃れ、手づかみでとれていた海の幸も食卓に並ばなくなったことでしょう。2、3度下がってしまった気温では、それまで常食としていたクリは育ちませんから、この葦の生い茂る原っぱで、どのように生きてゆけば良いのか当時の人々は、途方に暮れたことでしょう。楽園に住み、豊かに暮らしていた人々に飢えがおそってきたのです。
そのような時に、水田稲作(稲作は6,000年前に発見)の技術が大陸からもたらされます。この稲作により人々は飢えから解放され、弥生時代がこの時から始まりますが、このことが縄文の高い精神文化を維持していた「時間」を人々から奪っていたのです。
クリはほおって置いても実りますが、稲作は、田に畦をつくり、水を導き、籾を蒔き、田植えをし、水の管理をしっかりと行い、雑草をとり、実った稲を収穫し、脱穀し、貯蔵し、と様々な手間ひまがかかります。労働の大半がその維持管理の為に費やされることになります。
さらに、加えて、稲作は広い耕地を必要とします。より良い条件を求めて、争いも生じたことでしょう。また、収穫した米の奪い合いも起きるようになったと思われます。このような争いに勝つためには、争いの技術に長けた人々の養成も必要になりました。兵隊がうまれ、兵隊には統率者が必要となり、指導者が生まれます。職業の分化はこの時より始まったと思われますが、それは年を経る事に複雑化して階級制度へと発展していったのではないでしょうか。
このような組織では、効率が尊ばれ、技術が発展しますが、それらは、物に対する効率で、精神に対する効率ではありませんでした。高い精神性を維持するには「時間」が必要だといいましたが、その時間とは、そのような労働に対する効率的な時間ではなく、反対に労働から解放された、非生産的な時間、ゆったりとした時間を必要とするのです。スローライフが必要なのです。
お釈迦さんが造った、祇園精舎などの僧院では、乞食が行われていました。乞食とは、僧が家の前に立ち、鉢をささげ、食物をこい歩く、托鉢(たくはつ)のことですが、これは、お釈迦さんが修行する僧に労働を禁ずるシステムとして行われたものです。なぜ、労働を禁止したのか。
心という物は、常に外界の変化に反応するようにできています。ですから、心を澄ませて集中しようと思っても、心の特性が外に向かって反応するようにできているのですから、なかなか集中することができないのです。「こころ」というのは「ころころ」「ころがる」のが特性で、TMでは、それを蝶々のようだと説明します。蝶々は花から花へ、甘い蜜を求めて飛び回りますが、一所にジッと止まりません。
われわれの意識も同じような振るまいをします。例えば、図書館や本屋の書棚の前で、興味ある題名に引かれ本を読み出しますが、まもなく、飽きてしまい、ふと別の本に目移りしてしまいます。それが興味を引くものであれば、次にその本を取って読んでしまいます。
心のこのような特性は、外界の変化に瞬時に反応し適応するために、肉体の機能としては必要なのですが、深く、自分の意識の奥を探ろうとすると、この特性が邪魔になります。精神の世界に深く穿ちいろうとした時、心が蝶々のように、他の対照へと移動してしまうのでは、自己の内側へ深く入り込めません。したがって、外界の変化をできるだけ少なく単調なものにする必要があります。
日常の生活をしていると、どうしても外界の変化が多いために、なかなかこれができないので、そこで、米を炊いたり、おかずを作ったり、という調理のための労働さえも遠ざけて(ましてや稲作の労働などもってのほかです)、体を維持する最低限の活動だけをおこなうようにしたのが、乞食という托鉢の行なのです。
私の行っているTMの合宿でも同じようなことをしています。1984年5月、水上温泉の水上館で2週間の合宿をしましたが、合宿といっても、禅の修行のようにきびしいものではなく、水垢離や滝行などの荒行があるわけでもありません。朝、適当な時間に起きて(8時ごろ)、温泉で一つ風呂浴びてから(入らなくてもかまいませんが)、定められた瞑想をしますが、その瞑想といっても、姿勢が厳しく問われるものでなく、上半身を起こしていれば良いので、私などは壁に寄りかかって行っていました。すべてを終えると2〜3時間くらいかかりますが、それが終わると食事。これは菜食です。カツオのダシさえ使えませんが、けっこううまい。肉があまり好きではない、私にはまったく問題ありません。
食事が終わると、消化のための散歩(30分くらい)。それが終わる3時ころまで自由時間。この時間がもったいないと思う人にはミーティングの時間があり、瞑想の知識についての情報提供が用意されていますが、出なくてもかまいませんし、出ても、寝転がって聞いていても怒られません。その後、3時頃より午後の瞑想、終われば夕食、散歩、自由時間(又はミーティング)、10時ごろ就寝(私は温泉で一風呂浴びてから寝てました)、とこんな具合。実に快適な二週間です。
こんなことしていて、何の効果があるのか、いぶかしく思う方もいるでしょうが、3,4日すると、体の代謝率がかなり落ちてきます。例えば大広間があったので、昔取った杵柄と、飛び込み前転をしたとたん、頭が痛くなり、一瞬動けなくなりました。階段を少し上がるだけで息が切れてしまいます(普段なら何でもないことなのですが)。というわけで、激しい運動や動作は禁止されています。
そうすると、体の代謝率が落ちているためか、このころから、瞑想の体験も普段の瞑想ではおきないようなことが次々と起こってきます。私は、おどろおどろしい白昼夢のようなものを数多く見ていました。一例を挙げると、瞑想中、気がつくと、井戸の前に立っています。そこに、得体の知れない婆さんがいて、井戸の水をかき回しています。すると、水の底から、骸骨やら、女性やら、甲冑を着た武将の遺体が次々と浮かんできました。いったい、何だったのかわかりませんが、潜在意識の底にある、何かの思いが、浮かんでは消えていったのだと解釈しています。
そんなことを、繰り返していた、ある時、ふと、真っ黒い『色』に出会いました。その黒さの綺麗なこと。黒という色が、こんなにも高貴で、つややかで、みずみずしく、深く・・・、いったい言葉というものは何なのだ。実体を言いあらわすのにこんなに不完全なものはない、という思いとともに、完璧な『黒』という存在の前に打ちのめされるように、ただ、ただ呆然としている私がいました。しかし、不思議なことに、その『黒』の『色』が見えないのです。
「俺はたしかに黒い色を見ている、なのに、なぜ見えないのだ」と自問自答している自分がいました。圧倒的存在として確かに『ある』のに、なぜか『ない』のです。こんな体験をしたのですが、それが数秒なのか、数分なのか、わからないまま、再び意識は遠のいていきました。瞑想から覚醒した時は、体験したことはすっかり忘れていました。圧倒的といえるほどの体験なのに、淡い淡い微かな体験でもあったようです。
それを思い出したのは、ミーティングの時で、今でも仲の良い、Kさんが「形が見えないことはありますか」という質問をしたのです。その言葉がキーワードとなり、さっきの体験がよみがえってきました。そこで、思わずアドミニストレーターに体験したことを話しました。なぜなら、なぜ白とか光とかではなく黒だったのか。もしかしたら「悪魔に魅入られる」ような不吉な体験ではなかったのかという思いがあったからです。
普段、多くの体験を「それはストレス解消ですから気にしないで」というアドミニストレーターは、その時はとても喜んでくれて、5本の指を広げ、体験というものは、5感(聴覚、触覚、視覚、味覚、嗅覚)を通じて認識されること。その五感の大本は一つで、5感を超越して体験すると、そのような体験になるのだと説明してくれました。
その時は、意味は良くわからなかったのですが、般若心経に書かれている「空」というものの体験をしたのではないかと今では思っています。色即是空、空即是色。色はそのままで空。空はそのままで色。一切の物質的現象(色)は無(空)である。無(空)はすべての物質的現象(色)である。無眼耳鼻舌身意、無色声香味触法。眼も鼻も耳も舌も体も意識も無く、形も声も香も味も触れことも法則さえも無い。すべては「空」。「空」が一切のものの根元。
どうも、その体験をしたようです。これが、合宿6、7日目なのですから、こういうことを、何年も繰り返していたら、とんでもない高次元の体験ができるのではないでしょうか。それには、何もしない「時間」が必要なのです。精神を進化させ、高い精神文化を維持し続ける為には、是が非でも、この「時間」を創り出す必要があるのです。
縄文時代や新石器時代の人々の実労働時間は2時間ぐらいと想像できるので、彼らは、その余暇時間を利用して、自己の内側を深く探求していき「精神の力を直接利用することに主たる基礎をおいた文化」を築いていったのでしょう。
しかし、寒冷化した気候と、それに伴い、生き延びてゆくために、必然的に発達した稲作の技術は、前述したように手間暇のかかることから、精神を進化させるために必要な「時間」を人々から奪っていきました。その結果、しだいに高い精神性が維持できなくなり、精神の文明は徐々に滅んでいったのだと思います。
取って代わった台頭してきたのが、いかにして稲の収穫量を上げるか、といった生産性を上げ効率を求めるパラダイムでした。ここに至って、ついに『精神』の文明は『物』の文明へとにシフトしていったのだと思います。
私の言葉で言わしてもらえば、パラダイムは、3原則の文化から2原則へ、直観的思考から分析的思考へシフトしていったのです。科学・技術の発達はこの延長線上に必然的に発達してきたものものと言って良いと思いますが、その発達とともに、ヨーガスートラで語られているような、心が創り出す様々な超能力は、人々のリアルな体験とはならなくなり、精神の深みは伝承の中にしか存在しなくなりました(ベーダ文献や古事記)。ついには、高い精神の文明があったと言うことさえも忘れてしまいました。
しかし、忘れてはならないことは、かっては存在した高い精神の文明が、アーユルベーダをそして漢方を、4大文明を、古事記に記された太陽系の正確な記述を成し遂げたのであるということです。そして、物の効率を求め科学文明を生みだしたパラダイムは、その最終局面で、地球環境を破壊し、われわれ自身を滅ぼしかねないところまで来てしまっているということです。
ただ、これは科学が悪いのではないと思います。科学は、寒冷化し、その中で増加する人類に、より豊かな生活を与えるために発展したはずです。言わば、過酷な労働から人々を解放し、再び、人々に豊かな「時間」与えるために発展してきたはずなのです。それが、どこで間違えたのか、奪い合い、競争し合う為に使用されています。人々は、他社よりも高機能な製品をと、競争に負けないために寝る時間を惜しんで、その開発のに費やしますが、精神の深化に費やすべき貴重な時間が浪費されてしまっています。また、わずか1円(開発途上国では数十倍になります)のお金がないために餓死する人がいるかと思うと、1秒間に何十億円という金額を稼ぎ出す人もいます。この不均衡、矛盾の原因を突き止め、正せば、科学・技術が生み出してくれた「時間」を使って、人類の新たな黄金時代を築くことができると思うのですが、どうでしょう。
当節は「時は金なり」と勤勉が尊ばれるご時世ですが、しかし、そんなに忙しくしていると「忙」という字がいみじくも語っているごとく「心」が「亡」びます。「時は心(精神)なり」なのですから。このパラダイムが人々の中で当たり前になったときに、私たちの「夜明け」は訪れることでしょう。
2004.10.11
参考文献
・銀河帝国の崩壊(Against the Fall of Night
) 井上勇訳 ・ 創元推理文庫。
・都市と星 (The city and the
stars) 山高昭訳 ・ ハヤカワ文庫SF
・神々の指紋 グラハム・ハンコック著 大地舜訳 翔泳社
・解説:ヨーガ・スートラ 佐保田鶴治著 平河出版社
参考HP
・国柄探訪:共生と循環の縄文文化
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h12/jog134.html