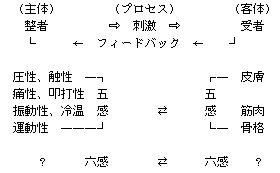
一般的に「科学的ではない」「客観性に欠ける」といわれと、それは信頼のおけない、いかがわしいものといった印象があるが、それでは科学的で客観的でない手技はいかがわしい存在なのか。しかし、世の中には科学的でも客観的でもないが、価値のあるものが存在する。それは科学の対局にある芸術である。
芸術において客観性は重要なことでない。ピカソの絵を見て、明度や彩度があるいは三角や丸の構成比率が何パーセントだから名作だと言うだろうか。また、私の手元にブルノーワルターの指揮するモーツァルトの交響曲第40番のアナログレコードがある。ワルターはこの第一楽章を6分35秒、第二を8分45秒、第三を5扮5秒、第四を4分55秒で指揮する。しかし、リチャード・エドリンガーは第一を6分36秒、第二を12分06秒、第三を3分42秒、第四を6分47秒で指揮する。同じモーツァルトの交響曲第40番でも指揮者により大きな違いがある。客観性が大切だからということで40番を何分で引かなければ芸術ではないと言うだろうか。
絵画や音楽などに限らずおよそ芸術といわれるものは、客観性に頼らず、芸術家の感性にしたがい心のおもむくままに絵筆をはしらせ、指揮するからこそ、われわれを感動させるのだと思う。芸術は主観的な行為なのだ。芸術性が高いということは、より個性的であり主観性が高いということではないのか。ここに客観性は存在しない。
心のおもむくままとは手技の治療に似ていないか。手技は客観的に行うべきものではなく主観で行うものではないのか。
前の項で、私が均整師になりたての頃の、客観化できなくて困ったと書いたが、数年もすると、こんどは手の感覚が違ってくることに戸惑いを覚えた。手の感覚が以前より鋭敏になってくるのだ。均整専門学校を卒業したての頃はよく分からなかった異常箇所が苦もなく感じられるようになってくる。さらに10年をへた今では、時として手を直接ふれなくても感じてしまうことさえある。
例えば、いつもはさわらない所に指が行くときがある。「あれ、俺はなぜここに手をおくのか」と後から気づく。そんなとき「よくわかりますね」と患者さんから言われるが、当人は首をかしげているのである。なぜ、そこを押したのかよくわからない。おそらく無意識での行動だと思うのだが、こういうことが最近よく起こるようになった。
また、こんなこともあった。ある時、当時中学2年になる娘が、テニスボールを頭にぶつけて痛がっていた。頭骨操法の簡略版?でもやってみるかと、娘の頭に触れるともなく両手を当てていると、左の前頭部にV字型のするどい波動を感じてきた。どこにぶつけたか事前に聞かなかったのだが、その部分が痛いのかと聞くと「そうだ」と言う。しばらく両手でその波動を感じていると、2分ほどしてその波動が側頭部が静かに広がるような穏やかな波動に変化した。「あれっ」と思い「今、痛みがなくなったのでは」と聞くと「そうだ」と言う答えである。気のせいかなと思うほどのかすかな感じなのだが両者の感覚が一致するのだから、実際に起こったことであり、事実なのだと思う。
このように経験とともに自分の手の感覚が違って来る。おそらく治療家であれば誰もが体験することだと思うが、こうしたセンサーとしての手の感覚をどのように定量化すればいいのだろうか。
もうずいぶん前になるが、オーディオ評論家の長岡鉄雄氏が「私の聴覚は一般の人の1000倍ある」といったことがあった。氏はスピーカーやアンプなどのオーディオ器機からでてくる音を瞬時に聞き分けることができるそうだが、私は氏の文章を読んだだけだから真偽のほどはわからないが、職人の感覚が千倍というのはあながち誇張ではないと思っている。
それは、ある町工場で「きさげ」という技術を見た時の経験からである。スクレッパという一種のナイフで金属の表面を削りながら平らにしてゆく技術だが、職人が腰だめにスクレッパを使い、碁盤のような金属の板の表面を平らにしてゆくと、驚いたことに、すでに平らにされた別の定盤をその上に重ねあわせると、二つはぴたりとくっついて離れなくなってしまった。
合わさった境界面に真空状態ができたためである。おそらく手の感覚のみで1ミリの千分の一ぐらいの精度をだしたのではないかと思う。したがって長岡氏の千倍説はあながち誇張ではない。くる日もくる日も同じことに注意の心を向けることによって、その部分の感覚が鋭敏になり、しまいには五感のレベルを超えて六感のレベルの微妙な差が識別、弁別できるようなるのではなかろうか。
第六感という感覚があるならばこれによる刺激は考えられないか。以下はこのことについての仮説である。
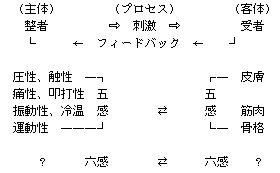
治療をする者と受ける者との関係を考えれば上図のようになる。このように考えると、治療とは治療をする者と受ける者との間において交換される何かである。この何かというのが刺激であるが、均整師は手により7種類(圧性、触性、痛性、叩打性、振動性、運動性、冷温)の刺激を患者に与えることになる。それは受者(患者)の皮膚にある感覚受容体や筋肉、骨格などにある筋紡錘や腱紡錘などを通じて受け取られると考えられる。
これらの刺激は受者と整者の五感を通してやりとりされているわけだが、これ以外に六感を通して刺激がやりとりされることが考えられないかとというのがこの項の目的である。それには六感という感覚が存在が証明されなければならないが、その実験がすでに行われ、有力な根拠を提供してくれている。
ある時、テレビの市民大学講座を見ていたら、第六感を科学的に証明する方法として興味深い方法が述べられていた。それはテレビモニターを使い、その画面を四分割し、その四分割の画面には同じパターンの模様が表示されるが、四つのうちの一つに、パターンの乱れをわずかにつくっておく。その乱れは落ちついて目を凝らさなければ発見できないような乱れである。この画面を確か1秒の十分一位の時間で被験者に見せて、乱れの場所を当てさせるのである。
被験者はあっと言う間の時間なので確かめることはおろか、よく見ることさえできない。視覚の情報を脳に認識させるには十分な時間がないのである。普通ならば、こういう状態で当たる確率は四分の一の25パーセントのはずである。しかし、よく当たる人では60パーセントになるという。この現象は従来の視覚の概念では説明できない。五感を越えた感覚で認識していると考えざるを得ないというのである。
こうした感覚を治療に応用し昇華させたものの一つに脈診がある。WHOが民間治療の重要性と保護を訴える声明を世界の国々に向けて発したことがある。厚生省にもそれは届いているはずだが、そのきっかけをつくったのが、インドのアユルベーダーの医師トリグナ博士の脈診だった。
博士は視察官の脈を診て、その人の診断をしたばかりではなく、その場にいない上司の数年(正確な数字は忘れた)前の脾臓の摘出手術まで言い当てた。上司の脈の影響が部下に出ているというのである。
また、別の話で、漢方の脈診の例では、ルーマニアで子供のエイズ患者の治療に当たる谷博士のことをテレビで見た。谷博士はエイズ患者にAZTなどの現代の新薬の投与をすることなく、ただ漢方薬のみ、それも木の根や葉を土鍋で煎じる昔ながらの方法で投与し、さらにそれを患者の一人一人の脈を診ながら微妙に微調整し、一人一人に別々の薬を投与しながらエイズ患者に治療にあたっておられた。
その成果だが現代の新薬を投与するよりも遥かに生存率が高く、新薬でも2、3年の延命しかできないところを、その方法では子供が成人に達する可能性もでてきている。さらに印象的だったのは、その番組の最後で、その病院に二人の5、6歳くらいの子供が連れてこられた。エイズの末期で、そこで死を迎えるためだという。その子達の脈を診た谷博士は一人の子は助かるかもしれないというのである。みたところ二人はぐったりとして動くこともできない状態だったが、一人の子の脈にはまだ生きる力が残されているというのである。
番組はその6カ月後を映す。その子は細い体ながら、他の子供と元気に遊んでいた。その姿を見た時、感動し思わず涙が出た。
その脈診(アユルベーダー)のトレーニングを昨年受けた。それは橈骨動脈に三本の指を当てて、さらに各指に4段階の圧力をかけて、その微妙な変化を感じとり、体の状態を診るのである。マハリシ・アユルベーダー協会の高橋先生より習うが、高橋先生はラージュ博士に8年ぐらい前にすでに習っている。その教わり方が変わっていた。
脈を診るのに、ラージュ博士が最初に脈を診て、次に高橋先生が診るのだが、ラージュ博士は決して高橋先生に自分の診た結果を教えない。高橋先生は自分の診た脈がはたして正しいのか間違っているのわからない。結局、最後までわからずじまいだった。その変わり10分おきに自分の脈を取れといわれたという。寝ているときはどうするのかという質問には10分おきに起きて診なさいと答えられたということである。もちろん冗談だが、それほど頻繁に脈を診なさいということだと思う。
そうしているうちに脈の中の内部構造が自然にわかってくるというのである。ラージュ博士が教えたのでは先生の見解が先入観になり、学ぼうとする者の内側から育ってくる微妙な感覚を疎外するらしい。この方法が確実に脈を診るための確かな方法だというのである。脈診のトレーニングの例は主観を極めたところに客観があるといっているようである。
手技も客観よりも主観に徹したとき信頼性が増すように思う。そこで、しまいには開き直って、手技は客観の問題ではなく主観の問題と決めてしまった。手技は心のおもむくままにおこなう。これが均整にたずさわり11年目の結論である。われわれ手技者は科学者よりも芸術家あるいは職人に限りなく近い存在だと思うのである。われわれは体の調律師なのだ。
これは手技のみならず鍼灸やカイロプラクティックを含めた東洋医学全体にいえることではないかと思う。カイロプラクティックの創始者D.D.パーマーの言葉に「カイロプラクティックは、椎間孔を通過するところで圧迫されて、病気という機能異常を起こしている神経を解放する目的で、300ある人間の関節、特に脊椎の関節のサブラクセーション(Subluxation)を手でアジャストメント(Adjustment)する『芸術』である」という言葉があるが、まさに至言だと思う。英文の原典を観たわけではないから「芸術」という言葉に英語のどんな言葉が使われたのか確かめる時間がなかったが、「Art」であればまさにわが意を得たりということになる。
世に認められてもらうためには手技を科学化しなければならないというのが、わが師である亀井先生の願いだったが、そして、それは東洋医学を志す者にとっての命題だったが、その方向は見当はずれとは言わないが方向が間違っていたのではないか。手技をふくめた東洋医学は主観に頼らざるを得ない医学、いや主観に頼ってこそ成功する医学なのだ。手技を世に認めさせようとするには科学化、客観化の方向ではなく、主観化し、芸術として、あるいは職人芸とし確立する方向だと思う。
以上をふまえた上で保健医療について考えてみたい。現在、鍼灸や按摩・マッサージ・指圧、柔道整復師は国家資格があると言っても、医業類似行為という差別的な名前がついている。それは本来の医療ではなく、あくまでも類似なのだ。
この言葉に私は反発を抱く。東洋医学だって立派な医療だ。そこで次の提案をしてみたい。医療行為を「生命医療行為」と「保健医療行為」に分けてはどうかという提案である(もっとも聞いてもらえるとは想わないが)。現在、医師がおこなっている医療は「生命医療」とし、医業類似行為といわれるものを名前を変えて「保健医療」とするのである。
すでに述べてきたように、均整法などの手技療法をふくめ東洋医学は主観的で芸術的な側面を持つ。対する西洋医学は客観的で科学的である。両者は正反対の側面を持った医学なのだ。これまで科学一辺倒の医学の元では西洋医学しか認められなかったが、主観を重視する医学が考えられても良いわけで、その考えに基づけば西洋医学にはない側面を持つ東洋医学は十分に存在を主張する事ができるわけである。
|
保健医療 |
生命医療 |
|
東洋医学 |
西洋医学 |
|
保健を第一に考える |
生命に対する責任を持つ |
|
主観的 |
客観的 |
|
技芸的 |
科学的 |
|
全体的でバランスを重視 |
局所的で部分を重視 |
|
手の感覚を重視 |
新薬の特徴や新しい技術習得 |
|
基礎的な知識で通用 |
高度な専門的知識が必要 |
|
経験的 |
学理的 |
|
感性が重要 |
記憶力、頭の良さ |
|
EQ |
IQ |
|
過去を見つめる |
未来を見つめる |
|
慢性症に有効 |
急性、重篤な疾患に有効 |
|
安全である |
危険をともなう |
|
社会的責任は軽い |
社会的責任は重い |
すでに述べた事柄につけ加えると、西洋医学は人間を脳外科、神経科、泌尿器科、肛門科などのように細分化してみようとするが、東洋医学は人間をトータルでとらえそのバランスを重視する。
また、西洋医学では新薬の特徴や新しい技術の習得など高度な専門的知識が要求され多くの事柄を学ばねばならない。医学生は6年間勉学した後、インターン制度の2年を経て一人前の医者になるようだが、当然、学習期間も長くなる。学理の修得が大事な要素となる。記憶力、頭の良さが重要でIQの善し悪しが問題となる。
しかし、東洋医学は、手の感覚と使う個々の技術の知識さえ身につけ、それと生理や解剖の基礎的知識を学べば、けっこう通用する世界である。経験と手の感性がものをいう世界であるから、学習期間も短くてすむ。このことからIQよりもEQが重要視される。総じて西洋医学は現在の最先端の技術や新しく開発される技術に目が向けられるので常にその目は未来に向けられている。対して、経験を尊ぶ東洋医学はその目が過去に向いている。
バランスを重視する東洋医学は、まだ病気にならない前の未病の段階を重視し、また慢性症とかの治療にたけている。用法を間違っても患者の生命に危険が及ぶことはない。安全性が高い。難しい患者は西洋医学の医師に任せればいいのだし、何よりも難しい患者を抱え、その患者の現代医療を受ける機会を損ねないように注意する義務がある。保健を第一に考えるので保健医療という。
対する西洋医学は急性や重篤な疾患を治すのに最適である。しかし、西洋医学は手術とか薬とか用法を間違えが患者の健康を損なう危険もあるわけで、例えば喘息の薬のフェテロノールを使って死亡した人が出たとかという薬害の例もあるわけで、常に危険と隣り合わせの医療である。患者の命の責任を負うので生命医療という。
以上のことから、危険の責任を負う西洋医の社会的責任、地位が高くなるのは当然で、保健におもむきをおく東洋医学はそれより低いのも当然と考える。このような認識にたてば東洋医学だって立派な医療である。それは西洋医学を欠陥を補完する医療なのだ。だから保健医療として認めろと主張するわけで、もちろんそこには手技も当然のごとく含まれる。
現在、高騰する医療費は大きな問題となっている。また、AIDSなどの薬害の根本には厚生省、製薬会社、医師会の癒着という悪しき部分があるようで、医療をとりまく環境の構造改革も望まれている。東洋医学を保健医療として認めようとする政策は、そこへ新風を吹き込むことにならないか。構造改革と医療費削減などの変化を求める時、一石二鳥にも三鳥にもなる効率的な方法になると思うのだが。